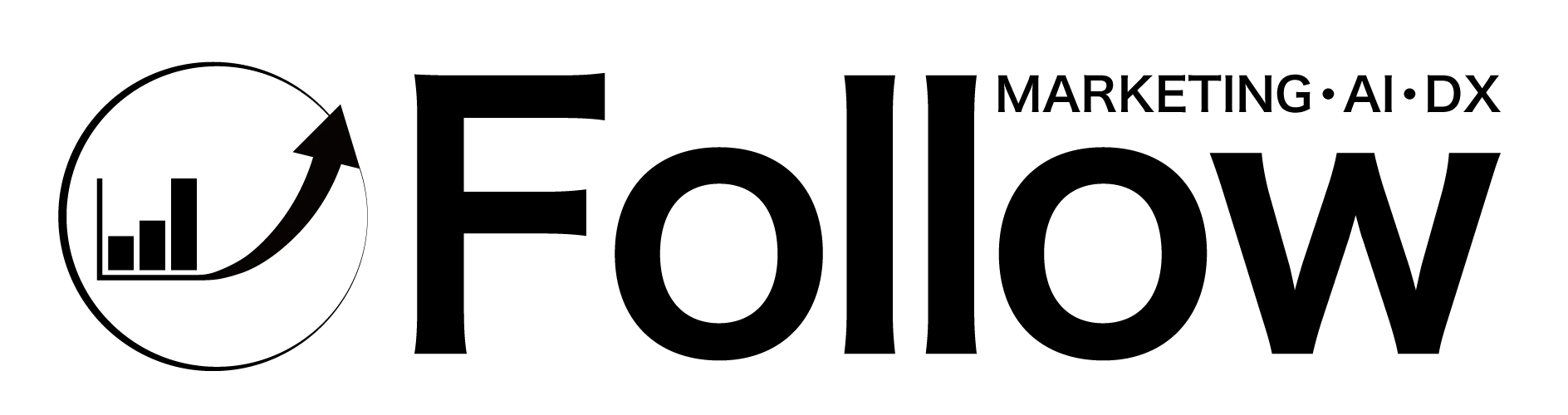2026年1月30日から2月5日にかけて発表されたDX(デジタルトランスフォーメーション)関連のニュースをまとめました。資生堂から独立したファイントゥデイが1年強でIT環境を完全独立させた事例、社内DX大学1年目の失敗から学ぶ教訓、2026年がAIエージェント「実行」の年となる7つのトレンド、OKIと船井総研による物流DX新システム、広島県の文書管理システムと電子署名の連携事例など、中小企業の経営判断に役立つ情報をお届けします。
1. ファイントゥデイ、資生堂からの独立後1年強でIT環境を完全構築
概要
2021年7月に資生堂パーソナルケア事業から独立したファイントゥデイが、わずか1年強で親会社のIT環境から完全独立を果たした事例が報じられました。同社は年間売上高約1074億円、海外売上比率約60%を誇り、TSUBAKI、fino、SENKA、unoなどの主要ブランドを展開しています。IT部門長の入社が2021年10月、TSA(移行サービス契約)期限が2023年1月という極めてタイトなスケジュールの中、当初10人弱という限定的なIT体制で大規模プロジェクトを推進しました。財務・SCM領域にOracle Fusion Cloud Applicationsを導入し、SaaSファーストとFit to Standard戦略を採用することで、11の国・地域におけるシステム統一を実現しています。
中小企業への影響
この事例は、限られたIT人員でも短期間での大規模システム導入が可能であることを示しています。成功の鍵となったのは、カスタマイズを最小化し、システムの標準機能に業務を合わせるFit to Standard戦略です。中小企業においても、SaaS導入時に標準プロセスを積極的に採用することで、導入スピードと効率を両立できます。また、IT人材が不足している場合はマネージドサービスを活用することで、専門的な運用を外部に委託しながらプロジェクトを推進できます。さらに、SaaS導入はAIレディな業務体系を構築する近道となり、将来的なAI活用の礎を築くことにもつながります。
経営者の視点
経営者が取るべきアクションとして、まずSaaS導入時には標準プロセスの積極採用を検討することが挙げられます。カスタマイズ要求を抑制し、標準機能での運用を推進することで、導入コストと期間を大幅に削減できます。IT人員が限定的な場合はマネージドサービス活用を優先し、組織横断的なBITA活動で経営と現場の橋渡しを構築することも重要です。一方で注意すべき点として、グローバル展開時には地域ニーズと統一性のバランスを取る必要があります。また、AI時代に向けた継続的な業務設計の見直しを怠ると競争力低下のリスクがあるため、SaaSの進化に追従してTo-Beを継続的に更新していくことが求められます。
参考リンク
EnterpriseZine:1年で資生堂のIT環境から完全独立したファイントゥデイ──”システムに合わせた業務”がAI活用の礎に
2. 社内DX大学1年目の失敗「木こりのジレンマ」から学ぶ教訓
概要
ある製造業企業が社内DX大学を設立し、全社展開として27名が参加したものの、1年目は期待した成果を得られなかったという事例が紹介されました。全社Slackの告知投稿に対するリアクションはわずか2個、27名中自主的に動いたのは5名のみという結果でした。同社の組織構成は60代・50代と20代が多く、30代・40代の中間層が欠落した「逆ひょうたん型」であり、ナレッジシェアが皆無で属人化が常態化していました。この失敗の背景には「木こりのジレンマ」があります。これは目の前の業務(木を切る作業)を優先し、自己研鑽や学習の時間(斧を研ぐ作業)を無駄と見なしてしまう心理状態を指します。
中小企業への影響
この事例から得られる教訓として、全社展開が必ずしも効率的とは限らないことが挙げられます。中小企業では小規模なパイロットから始めて成功体験を積み上げる方が効果的な場合があります。また、任命制よりも公募制の方が参加者の内発的動機を引き出せることが明らかになりました。2年目に公募制へ転換したことで、自発的な参加者による学習コミュニティが形成されています。DXの本質は技術導入ではなく組織文化の変革にあり、属人化を解消するには心理的安全性の確保が前提条件となります。失敗を恐れず意見を述べられる組織環境がなければ、ナレッジシェアリングは進みません。
経営者の視点
経営者が検討すべきアクションとして、まず任命制から公募制への転換があります。やらされ感を生むと逆効果になるため、参加者の内発的動機を重視したプログラム設計が重要です。また、デジタルスキル教育だけでなくマインドセット教育を重視し、対話型の組織文化への意識的な転換を推進することが求められます。上司の理解とサポート体制を構築し、中間管理層がDX推進の意義を理解することも成功の鍵を握ります。注意点として、研修参加と日常業務のバランス問題への配慮が必要であり、業務優先の文化が根強い場合は、学習時間の確保を経営課題として位置付ける必要があります。越境学習など異なる経験を通じた学びの場を設けることも有効な施策です。
参考リンク
EnterpriseZine:社内DX大学1年目の失敗「木こりのジレンマ」をどう乗り越えるか
3. 2026年はAIエージェント「実行」の年へ、UiPathが説く7つのトレンド
概要
UiPathが2026年のAIエージェントに関する7つのトレンドを発表しました。経営層の78%が新しいオペレーティングモデルが必要と回答し、73%が12ヵ月以内にROI創出を予測しています。7つのトレンドは、再発明の原動力は必要性、AIによるROI実現、業務特化型AIエージェントの本格化、マルチエージェントシステム、コマンドセンター確立、攻めと守りの両立、データのメタ化です。マルチエージェント導入でエラー率60%削減、プロセス40%高速化が期待されており、2028年までに70%の企業が中央集約型オーケストレーションを採用すると予測されています。
中小企業への影響
中小企業にとって朗報なのは、特化型エージェントのパッケージ化により自社開発不要でROI達成が可能になることです。金融KYC(本人確認)や保険料請求処理など、業界特化型の事前構築ソリューションが登場しており、ゼロから構築する時間を短縮して迅速にROIを達成できます。マルチエージェントシステムとは、特化型AIが役割分担して協働するシステムであり、単一の万能型エージェントより複雑な業務に適しています。外部ソリューションを活用することで、中小企業でもAIエージェント導入が現実的な選択肢となりつつあります。2025年はパイロット段階だったのに対し、2026年は本番運用への舵切りが求められる「実行」の年となります。
経営者の視点
経営者が取るべきアクションとして、オペレーティングモデルの抜本的再設計が挙げられます。従来の人中心型からAIエージェント中心型への転換を見据え、高インパクト領域への集中投資を検討することが推奨されています。小さく始める戦略ではなく、ビジネスインパクトの大きい領域での本格導入が求められます。また、組織内にコマンドセンター機能を整備し、設計段階からセキュリティとガバナンスを組み込むことが重要です。注意すべきリスクとして、自律的AIエージェントが組織ガバナンスを逸脱するリスクや、野良AIエージェントの増加があります。事後対応ではセキュリティ負債が蓄積するため、メタデータとオントロジー構築によるデータ構造化を進めることも不可欠です。
参考リンク
EnterpriseZine:2026年はAIエージェント「実行」の年へ UiPathが説く、7つのトレンドと日本企業の勝ち筋
4. OKIと船井総研が物流DX新システム「青-Doプロジェクト」を発表
概要
OKIと船井総研がコンソーシアムを組み、物流DX新システム「青-Doプロジェクト」を第5回スマート工場EXPO(2026年1月21-23日、幕張メッセ)で発表しました。本格展開は2027年を目標としています。このシステムは保管、流通、配送、製造という物流の複数フェーズを統合的にカバーするもので、TMS(運搬管理システム)で保管から配送まで一元管理し、SHO-XYZで位置情報と在庫を統合管理します。従来、物流業界では各プロセスが異なるシステムで管理され、データがサイロ化していました。サイロ化とは部門やシステムごとにデータが分断され横断的な活用ができない状態を指します。
中小企業への影響
中小物流企業にとって、このシステムの登場は大きな意味を持ちます。従来、物流企業ごとにカスタマイズが必要だったシステムが、パッケージ化されたソリューションとして提供されることで、導入期間と負担が軽減されます。単一システムで複数プロセスを管理できるため、規模が小さい企業ほどシステム投資の負担軽減効果が大きくなります。配送コスト最適化シミュレーション機能を活用することで、最適な配送ルートとタイミングを自動算出でき、ドライバーの運用効率化と在庫保管の最適化を一元的に実現できます。統合的な物流管理により、これまで分散していたデータを横断的に活用した意思決定が可能になります。
経営者の視点
経営者が検討すべきアクションとして、まず自社の物流デジタル化の現状を診断することが挙げられます。複数システムが並立している場合は、統合による効率化機会を検討することが有効です。2027年の本格展開に備えて情報収集を開始し、サイロ化したデータの統合戦略を策定することも重要です。配送・保管・流通の各プロセスを横断的に見直し、パートナー企業との協業によるソリューション導入を検討することが推奨されます。一方で注意すべき点として、大規模システム導入のため初期投資が必要となること、既存システムからの移行には課題が伴う可能性があることが挙げられます。カスタマイズ範囲の明確化も、導入成功の重要な要素となります。
参考リンク
MONOist(ITmedia):OKIが物流DXを「新たな収益の柱」へ 船井総研と組んだ新システムを公開
5. 広島県、文書管理システムと電子署名を連携し一気通貫でデジタル化
概要
広島県がコニカミノルタジャパン構築の文書管理システムとGMOサインを連携させ、契約書の決裁から署名、文書管理まで一気通貫でデジタル化する取り組みが発表されました。連携サービスはGMOサイン行革DX電子契約とGMOサイン行革DX電子公印で、2025年10月に運用開始、2026年3月に連携サービス開始予定です。当事者型電子署名を活用し、処分通知などの行政文書もデジタル化します。当事者型電子署名とは、署名者本人の身元確認を行った上で発行される電子署名で、法的効力が高く重要文書に使用されます。広島県は既存の文書管理システム更新時期を迎えており、利便性向上とガバナンス強化を目指しています。
中小企業への影響
自治体における一気通貫のデジタル化事例は、民間企業にとってもモデルケースとなります。部門別に分かれていたシステムを統合することで、コスト削減と業務効率化を同時に実現できることが示されました。電子署名を導入することで郵送コストと時間を大幅に削減でき、ペーパーレス化により印刷・保管・廃棄コストも削減可能です。文書管理を一元化することで、過去の契約書や文書の検索・参照が容易になり、業務効率が向上します。また、行政との取引において電子署名対応が求められる可能性が高まっており、自治体のデジタル化動向を把握しておくことは、今後の取引対応においても重要です。
経営者の視点
経営者が検討すべきアクションとして、システム更新の時期を捉えた統合的な導入戦略の検討があります。既存システムの更新タイミングは、文書管理と電子署名を連携させる好機となります。ペーパーレス化の段階的推進計画を策定し、電子署名の利用権限管理体制を構築することで、不正利用を防止しながら利便性を向上させることができます。取引先である自治体がデジタル化を進めている場合、自社も対応を求められる可能性があるため、動向把握が重要です。注意点として、複数ベンダーシステムの統合には技術的課題が伴う可能性があり、導入後の運用体制の整備が重要です。電子署名の権限管理を適切に設計しないとセキュリティリスクが生じる点にも留意が必要です。
参考リンク
EnterpriseZine:広島県、コニカミノルタ構築の文書管理システムとGMOサインを連携──契約から署名、文書管理まで一気通貫でデジタル化
まとめ
今回のDXニュースでは、システム導入における戦略的なアプローチと組織文化の重要性が浮き彫りになりました。ファイントゥデイの事例では、Fit to Standardの考え方でカスタマイズを抑え、標準プロセスに業務を合わせることで短期間での大規模導入を実現しています。一方、社内DX大学の事例では、技術導入だけでなく組織文化の変革とマインドセット教育が不可欠であることが示されました。AIエージェントについては2026年が「実行」の年となり、パイロット段階から本番運用への移行が求められています。物流DXや行政のデジタル化においても、複数システムの統合による効率化が進んでおり、中小企業にとってもパッケージ化されたソリューションの活用機会が広がっています。経営者は、自社の状況に応じてこれらのトレンドを参考に、DX推進の戦略を検討することが求められます。