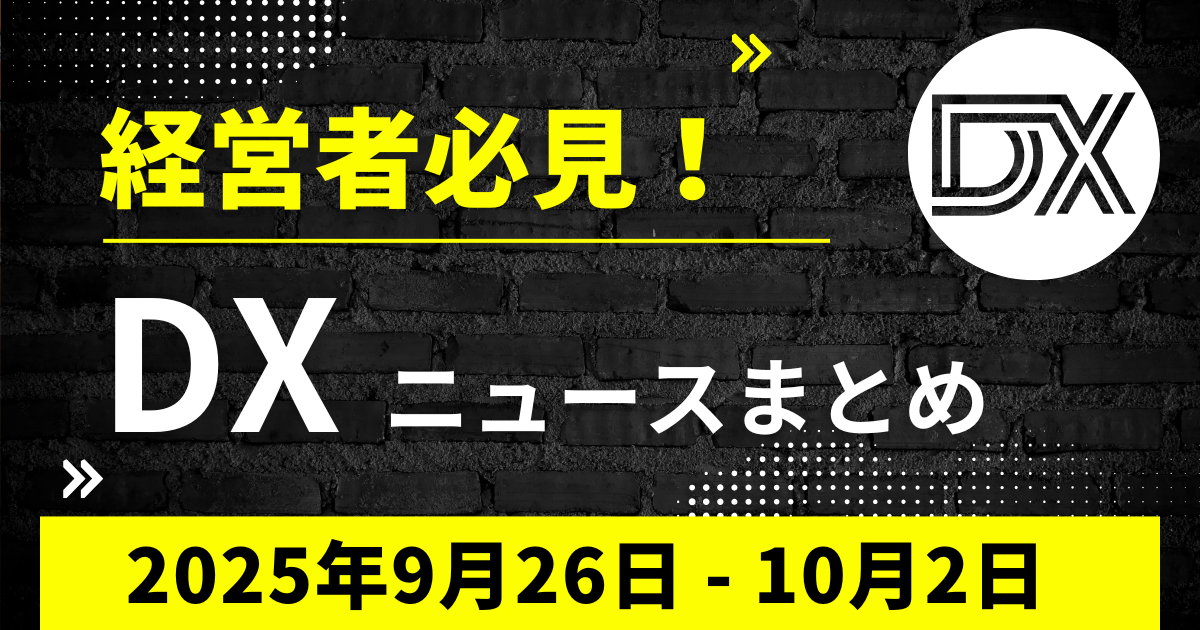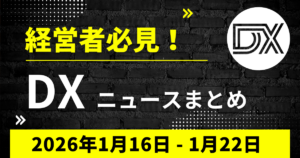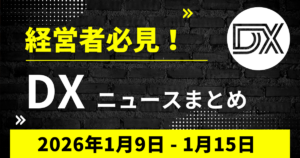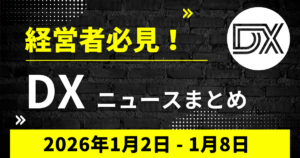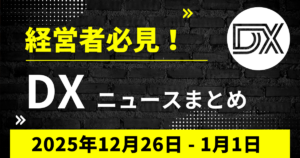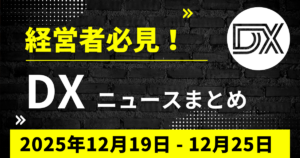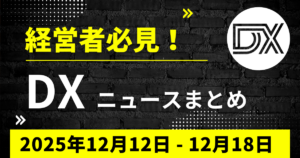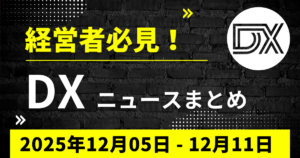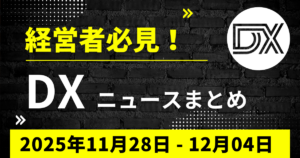DXニュースまとめ(2025年9月26日〜10月2日)
生成AIや業務データの活用が一段と現実味を帯びてきました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、行政のAI基盤拡充(デジタル庁「源内」にOpenAI追加)、大学×自治体のAI・DX連携(東京工科大と八王子市)、現場を壊さない“変えないDX”(ネクスウェイ)、オフィス設計の自動生成(プラス×テクノフェイス)、DX内製化の実態(ドリーム・アーツ調査)です。いずれも、投資判断のスピード、人材育成、セキュリティ標準の整備に直結します。本文で「自社で何をすべきか」を具体的に示します。
1. 行政AI基盤「源内」がOpenAI対応、府省連携を加速
概要
デジタル庁は10月2日、職員向けの生成AI利用環境「源内(げんない)」にOpenAIのLLMを追加する方針を公表しました。これまで選べたモデルはAmazon Nova Lite、Claude 3 Haiku、Claude 3.5 Sonnetでしたが、選択肢が拡充されます。あわせて、政府横断のAI基盤「ガバメントAI」を各府省庁へ展開する取り組みも加速するとしています。源内は2025年5月から運用が始まり、汎用の文章生成や校正、翻訳に加え、「国会答弁検索AI」「法制度調査支援AI」など行政実務に直結するアプリ群を提供してきました。利用状況としては5〜7月の3カ月で延べ6万5千回超、職員約950人が活用したとされ、業務でのAI浸透が具体的な数字で示されました。
中小企業への影響
行政のAI活用が進むと、調達要件やセキュリティ水準の事実上の基準が明確になります。ガイドラインや運用ノウハウが公開されれば、民間でも安心してAIを利用しやすくなり、RFP(提案依頼書)にも反映されるでしょう。また、OpenAIを含む複数モデルの並存は、費用対効果や品質を比較しながら最適なモデルを選ぶ発想を促します。中小企業にとっては、用途別にモデルを使い分ける“マルチモデル前提”の体制づくりが鍵になります。加えて、政府案件で要件化の進むISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)やデータ所在の取り扱いに関する議論が進むほど、国内ベンダーの準拠製品や監査対応サービスも充実していきます。結果として、中小企業が外部委託に頼らず、自社の責任で安全にAIを利用できる余地が広がります。
経営者の視点
まずは自社の業務で機密度の高い領域と低い領域を仕分けし、社内ポリシーを短く明文化しましょう。次に、見積書の下書き、与信チェックの要約、マニュアルの改訂など低リスク・高頻度タスクからAIを実装します。将来の調達基準に備え、監査ログやプロンプト管理、モデル切替の手順もテンプレート化しておくと、のちのセキュリティ審査に対応しやすくなります。最後に、学習データの取り扱いと個人情報のマスキングは必ず社内ルールに落とし込み、年1回は訓練と点検を実施する計画を立てましょう。
参考リンク
IT Leaders:デジタル庁、職員向け生成AI基盤「源内」にOpenAI追加
2. 私大最速級AIスパコン「青嵐」公開—八王子市とAI・DX連携
概要
東京工科大学は10月2日、NVIDIAの最新GPUアーキテクチャを搭載したAIスーパーコンピュータ「青嵐(SEIRAN)」を公開し、同日に八王子市とAI・DX連携協定を締結しました。システムはDGX B200を12台、合計96GPUで構成し、私立大学として最大級の計算能力を備えます。生成AIや大規模言語モデルの学習、画像認識などの高度なワークロードに対応し、地域の人材育成や共同研究の基盤として活用される見通しです。本格稼働は11月上旬を予定し、スパコンランキング「TOP500」申請に向けた準備も進めているとされています。
中小企業への影響
「大学×自治体×企業」の連携が具体化した事例です。地域の大学が高性能計算資源と研究者コミュニティを持つと、製造、建設、観光、医療など地場産業のデータ利活用に弾みがつきます。例えば、小売の需要予測、建材の不良検知、観光動線の最適化など、小規模でも検証しやすいテーマが多数あります。自治体の支援メニューや補助制度と組み合わせれば、コストを抑えたPoC(実証)が可能になり、採用や産学連携の面でも好循環が生まれます。さらに、大学側が生成AIの学習・評価を一括で引き受けられるため、企業が扱いづらい著作権・個人情報の論点や、ハード/ソフトの最新動向をキャッチアップできるメリットがあります。ハンズオン講座や共同講義を通じて、社員のリスキリング機会も得やすくなります。
経営者の視点
まずは大学の産学連携窓口に自社データの棚卸し表を持参し、「90日で効果を測れる課題」を一つ選んで相談してみましょう。要件定義は「使う人の現場」を主語にシンプルにし、効果指標(売上・歩留まり・工数)を事前に決めます。外部の計算資源は“借りる前提”で、成果が見えたらクラウドへ移行、もしくはオンプレ最適化を検討すると無理がありません。契約面では、成果物の知的財産の帰属、再利用範囲、学術発表の可否を覚書で明確化しておくと、のちの商用展開がスムーズです。
参考リンク
PC Watch:東京工科大学、私大最速級AIスパコン「青嵐」公開と八王子市と連携協定
3. 「壊さず進める」ネクスウェイの“変えないDX”
概要
通信・通知系SaaSを手がけるネクスウェイは10月2日、「変えないDX」構想を発表しました。テーマは、現場の運用や紙・FAX・電話など既存の業務慣行を前提にしつつ、段階的にデジタル化の効果を出すというものです。創業以来、FAXやメール、SMSの一斉配信など“連絡の基盤”を提供してきた同社は、デジタルとアナログの橋渡し役として、現場に負担をかけない移行方法を提唱。デジタル月間に合わせた発表会では、顧客の多様な実情に即した「壊さず進める」アプローチを前面に出しました。
中小企業への影響
「すべてをクラウドへ」「紙をゼロへ」と唱えるより、“今ある強みを活かすDX”は実装しやすく、費用対効果も測りやすいのが利点です。例えば、取引先の大半がFAX運用なら受信側だけをAPI連携に置き換え、社内ではPDF化と自動仕分けまでに留める、といった部分最適の一歩が現実的です。段階を踏めば、教育コストや現場の反発、切替時の混乱を最小化できます。通知や督促、出荷連絡、検収回答のようにルールが明確で繰り返し頻度が高い業務から着手すれば、短期で成果が見え、現場の納得感も得られます。逆に、取引先や社内部門が多岐にわたる“調整コストが高い工程”は後回しにするのが賢明です。
経営者の視点
自社の“変えない核”と“変える周辺”を可視化するため、業務フロー1枚絵と費用と工数のヒートマップを作りましょう。着手は「転記・待ち・探しもの」が多い工程から。連絡・通知・照会の自動化で平均処理時間をまず20%短縮するKPIを掲げ、成功したら次の工程に波及させます。ベンダー選定では、SLAとサポート窓口の実力を重視し、現場責任者を巻き込んだ段階導入計画で“壊さず進める”を徹底しましょう。なお、紙やFAXを残す場合の情報漏えい対策(廃棄・保管・権限制御)と、電子化部分の監査ログ/バックアップはセットで設計してください。リスクを抑えつつ“壊さない”を実現することが、長続きするDXのコツです。
参考リンク
EnterpriseZine:ネクスウェイ、現場に優しい「変えないDX」を提唱
4. プラス×テクノフェイス、オフィスレイアウト自動生成へ
概要
オフィス家具のプラスは10月2日、AI研究開発のテクノフェイスとオフィスレイアウト自動生成エンジンの共同開発に着手したと発表しました。事前に収集したオフィス面積や動線、座席数、チーム構成などのパラメータを入力すると、レイアウト案を複数自動生成する狙いです。将来的には、席配置とコミュニケーション量の相関、来客導線とセキュリティの両立、フリーアドレスの稼働率予測など、運用データと連動した高度な最適化も見据えています。移転や改装の初期検討にかかる期間とコストを大幅に圧縮できる可能性があります。
中小企業への影響
レイアウト設計は、意思決定のたびに図面修正と関係者調整が発生し、見えない工数が膨らみがちです。自動生成で“たたき台”が早く出ると、意思決定スピードが上がり、サンプル数も増えるため「より良い案」を見つけやすくなります。さらに、来客の動線、会議室利用率、倉庫の作業効率といった運用データの可視化と組み合わせれば、空間投資の費用対効果(ROI)を数値で語れるようになります。小規模オフィスでも、増員・減員・レイアウト変更を反復可能なプロセスにできる点は大きな利点です。
経営者の視点
まずは現行オフィスの平面図データ(CAD/PDF)、座席台帳、会議室予約ログ、来客記録を集めて“現状の数字”を整えましょう。次に、将来の人員計画と在宅率の仮説を置いた3パターン(成長・横ばい・縮小)で条件を作り、ベンダーに自動生成の試作を依頼します。評価指標は「1席あたりコスト」「動線長」「会議室の過不足」「倉庫動線の安全」の4つに絞ると判断しやすくなります。なお、個人情報や機微な会話が想定されるスペースでは、遮音・視線配慮・入退室ログの設計も忘れずに。AIが提案する案は“最適っぽく見える”ことがあるため、避難導線や法令順守(消防・建築基準)の最終確認は人の責任で行う体制を決めておくことが重要です。
参考リンク
ITmedia Built:オフィスレイアウト自動生成エンジンの共同開発に着手
5. 調査:8割がDX内製化志向、4割超が外部委託—“ハイブリッド”が現実解
概要
@ITは10月2日、ドリーム・アーツが実施したDX内製化に関する調査の結果を紹介しました。見出しのポイントは「約8割が内製化を推進したいのに、4割以上が外部委託を選んでいる」という現実です。役職によって課題の捉え方に差があり、経営層はコストや投資対効果、現場は人材不足やノウハウ欠如を障壁に挙げる傾向が示されました。システム開発の内製化は、すべてを自社で賄うことではなく、領域を切り分けて“コアは内製・周辺は外部”とするハイブリッド型が実態に沿うことも読み取れます。
中小企業への影響
この結果は、“内製を志向しつつ現実には外注も併用する”企業が多数派であることを裏づけます。中小企業では、要件定義・データ設計・業務プロセス変更など中核の意思決定を内製し、専門性が高い実装やセキュリティ監査は信頼できる外部に任せるのが合理的です。重要なのは、外注依存ではなく内製の指揮能力を持つこと。ドキュメント標準、コード所有権、引継ぎ条件、ベンダーロックイン回避を最初に取り決めておけば、選択肢を確保できます。
経営者の視点
1年で3つの小規模プロジェクト(例:見積自動化、在庫可視化、問い合わせ要約)を回し、失敗から学ぶ設計を制度化しましょう。社内にプロダクトオーナー役を立て、権限と時間を正式に付与します。スキルはローコード/ノーコードで土台を作り、難所のみ専門家を呼ぶ“ハイブリッド内製”が現実的です。予算は人件費と学習費用を固定費として見える化し、短期の外注費と比較できるダッシュボードを作ると投資対効果を説明しやすくなります。さらに、人材の裾野を広げる採用・育成の作法として「18時間の基礎研修→30日伴走→90日で成果物」を固定化し、リポジトリ運用(レビュー/CI/権限管理)を全社標準にしておくと、外部委託の増減があっても品質を保ちやすくなります。途中で方向転換しやすいよう、要件は2〜4週間サイクルで見直すアジャイル前提の契約にするのも有効です。
参考リンク
@IT:約8割がDX内製化を望む一方で4割以上は外部委託、ドリーム・アーツ調査
まとめ
今回取り上げた5本は、標準(ルール)・基盤・人材・現場実装の4点が同時に動いていることを示しています。経営者は、①社内のAI/DXポリシーを1枚で整備、②90日で効果を測る小さな実証を回す、③外部と内製の役割分担を明文化、④データとログの管理を“最初から”仕組みに組み込む、の4点を実行に移しましょう。