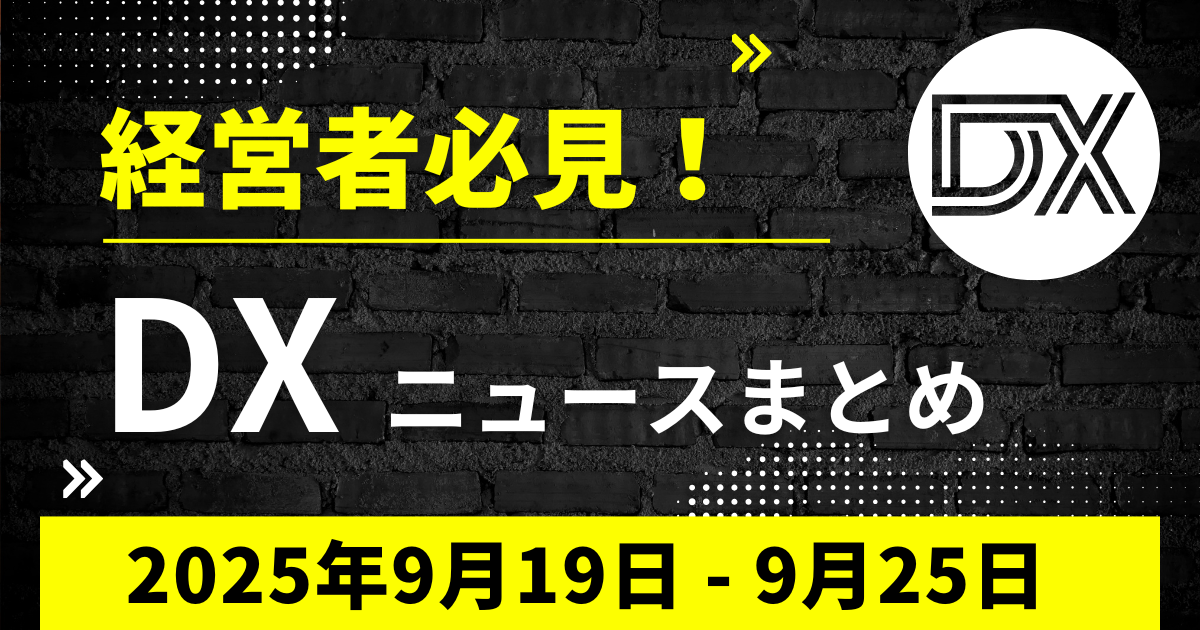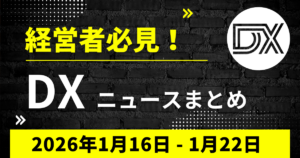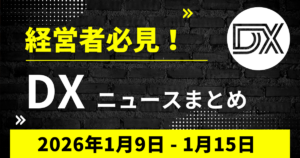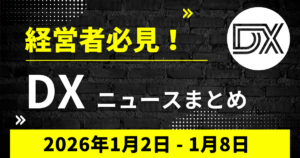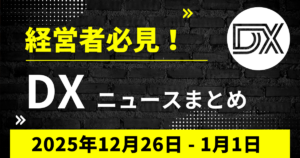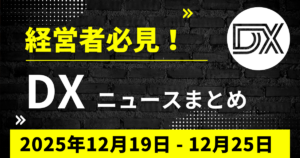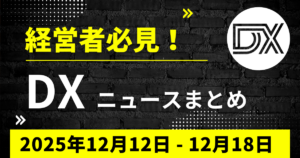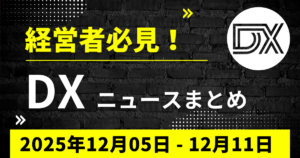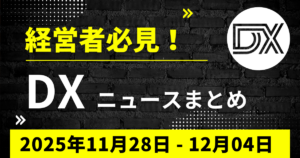DXニュースまとめ(2025年9月19日〜9月25日)
DX(デジタルトランスフォーメーション)をめぐり、実装と基盤整備のニュースが相次ぎました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、三菱UFJ信託の生成AIアシスタント本格導入、NTT東日本の工場向けセキュアネットワーク支援開始、WEFによるグローバル・ライトハウスの12拠点追加、SCSKのECM変革支援「SuccessChain for ECM」提供開始、日本郵船の配船最適化AIの本格運用です。いずれも「探す時間の削減」「止まらない工場」「工程横断のデータ連携」「需要変動への強さ」といった、現場の生産性に直結するテーマです。この記事では、各ニュースの要点と中小企業への実装ヒントを、経営目線で短時間で理解できる形に整理しました。
1. 三菱UFJ信託、営業店に生成AIアシスタント本格導入——「探す時間」を削減し、属人化も解消へ
概要
三菱UFJ信託銀行が、営業店の業務マニュアルやFAQを横断検索できる生成AIアシスタントを本格導入しました。約2000人が常時利用し、年間6万5000時間の業務時間創出を見込むとしています。複雑な文書構造を解釈し、回答ログの活用で精度を継続的に改善できる点が特徴です。
中小企業への影響
要領の良い人に聞かないと仕事が進まない——そんな「属人化」を崩すヒントになります。社内の手順書や取扱説明、顧客対応テンプレートを一箇所に集約し、自然文で聞けば探して答えが返る環境は、小規模組織ほど効果が表れやすいです。検索に費やしていた時間が削減され、問い合わせ対応も標準化。新人のOJT支援やナレッジ共有にも直結します。一方で、誤回答や機密情報の露出といったリスク管理は必須です。アクセス権管理、監査ログ、回答根拠の提示をセットで設計しましょう。
経営者の視点
まずは「質問が多い業務領域」を特定し、対象文書の棚卸し→権限設計→PoC→横展開の順で進めるのが現実的です。KPIは「検索〜回答までの平均時間」「一次回答解決率」「新人の立ち上がり日数」。ベンダー任せにせず、回答ログを経営資産として育てる運用が投資対効果を左右します。外部LLMを使う場合はプロンプトやベクトルDBの管理、モデル更新時の再評価プロセスもルール化してください。
補足として、同行では約2600本のマニュアル、600ページの補足資料、100件超の通達、約1000件のFAQが存在し、年間1万2000件の事務問い合わせが発生していました。AIアシスタントはこうした情報群をRAG(社内文書検索+生成)で参照し、回答の根拠も併記する運用です。
リスク対策としては、個人情報のマスキング、センシティブ文書の除外、回答根拠のURL/版数管理、定期的な再学習・評価をセットに。社内説明会で「どんな聞き方をすれば正確さが上がるか」を共有すると、早期に定着します。
参考リンク
DIGITAL X:三菱UFJ信託銀行、営業店における情報検索に生成AIアシスタントを本格導入
2. NTT東日本が「工場向けセキュアネットワーク」導入支援を開始——設計・構築・運用をワンストップ
概要
NTT東日本は、工場の有線・無線ネットワークを耐環境性や産業用プロトコルに対応させつつ、設計→構築→運用・保守まで一括で支援する「BizDriveファクトリーネットワーク」を開始しました。現状診断でリスクを可視化し、適正な機器選定とセキュリティ対策まで含めて伴走するサービスです。
中小企業への影響
製造現場のデータ活用や自動化はネットワークの堅牢性が前提です。実は、無許可機器の接続や設計不備による遅延・断が、ライン停止や品質劣化の温床になりがち。OT(製造設備)とIT(基幹)の分断がある工場ほど、誰が設計・保守を担うかが曖昧で、更新時に脆弱性が残ります。本サービスのようにアセスメント→優先度整理→段階的刷新を外部の専門家と行うことで、停止リスクの低減、将来の拡張に耐える配線・VLAN設計、ゼロトラスト対応が進みます。予算の読みやすさや、メーカー横断の保守窓口も中小には有効です。
経営者の視点
投資判断は「ライン停止コスト×発生確率」「リードタイム短縮」「セキュリティ事故の回避額」で定量化しましょう。現場ヒアリング→可視化→3年更新計画を策定し、まずは重要ラインから冗長化と段階的更改。クラウド連携やAI活用を見据え、時刻同期、ネットワーク遅延SLA、監視の標準化を要件に入れると後戻りが防げます。OTと情シスの合同ガバナンスも明文化を。
さらに、運用局面ではEoL(サポート終了)OSへの対応や他社構築環境の引き継ぎにも対応するとされ、無線LANの計画設計まで含めた現場の通信品質と可用性の底上げに重点を置きます。製造業では世界的にランサムウェア起因の操業停止が増えており、境界突破を前提とした監視・分割は急務です。資産台帳の整備、変更管理、バックアップ設計をネットワーク計画と同時に固めることで、復旧の早さが競争力になります。料金は個別見積もりのため、まずは試験ラインでの小規模導入→全体展開の順で単価感を掴むと良いでしょう。
参考リンク
DIGITAL X:工場にセキュアなネットワークを構築するための導入支援サービス、NTT東日本が開始
3. WEF「グローバル・ライトハウス」、12拠点を新規認定——日本の新規認定は2020年以降ゼロ
概要
世界経済フォーラム(WEF)は9月16日、製造の先進拠点を選ぶグローバル・ライトハウス・ネットワークに12拠点を追加し、総数は201になったと発表しました。対象は中国6、メキシコ、シンガポール、タイ、トルコ、カタール、フランスから各1拠点。全体として労働生産性40%向上、リードタイム48%短縮などの成果が示されています。一方、日本は2020年の認定を最後に新規追加がありません。
中小企業への影響
ライトハウスは「生産性」「レジリエンス」「サステナビリティ」「人材」「顧客中心」の5領域で優れた拠点です。先進事例の多くが、データ統合→可視化→AI最適化→現場定着を高速ループで回し、KPIと投資回収を現場起点で積み上げています。国際競争の視点では、日本の中小が工程横断のデータ連携や技能のデジタル化に踏み切る必要性が高まっています。生成AI×品質(検査、自動原因分析)や需要変動に強いサプライチェーン計画は、まずは一工程・一製品ラインからでも効果が見えやすい領域です。
経営者の視点
「自社版ライトハウス」を目指し、①価値連鎖マップの作成、②3指標(QCD)+CO2+人材のKPI設計、③90日で効果検証できるスモールスタートを掲げましょう。重要なのはベンダー任せにしない運用設計と、横展開テンプレートの早期整備です。補助金や共同実証を活用しつつ、データ定義・ID設計・現場教育に先に着手することで、投資回収の確度が上がります。
参考リンク
世界経済フォーラム:グローバル・ライトハウス・ネットワーク2025(12拠点を新たに認定)
4. SCSKが「SuccessChain for ECM」を提供開始——PLM基盤で設計〜製造データを連携、QCDを底上げ
概要
SCSKは9月19日、製造業のECM(エンジニアリングチェーンマネジメント)を最適化する伴走型サービス「SuccessChain for ECM」を開始しました。PLM(製品ライフサイクル管理)を中核に、設計図、CAE結果、EBOM/MBOM/BOPなどの技術情報を一元管理。アセスメント、業務テンプレート、基盤導入、定着化支援をワンパッケージで提供し、将来的にはAIエージェントやデジタルツインまで適用範囲を拡張するとしています。
中小企業への影響
設計変更が現場に伝わらない、解析ノウハウが属人化して再利用できない——多くの中小製造で起きている問題に直球で効きます。図面→部品表→工程表が同じ品目IDでつながり、改定履歴が自動で連動するだけで、手戻りとムダ工数が大幅に減ります。PLMは「大企業向けで高価」というイメージがありますが、テンプレートと伴走支援があると導入障壁は下がります。試作・少量多品種の現場ほど、設計品質と納期の安定化に効くはずです。
経営者の視点
まずは現行の図面・BOM・工程の整合率を測り、改定リードタイムや不具合起因の再作業時間をKPI化。その後、品目マスタと版数ルールを先に固め、段階移行(設計→生産技術→製造)の受け渡しチェックリストを標準化します。PLM導入はIT選定だけでなく、現場の命名規則・権限・承認フローの再設計が肝です。パイロット製品で90日検証→横展開のリズムを意識しましょう。
なお、基盤ソフトにはAras Innovatorを採用。ナレッジDB由来の業務テンプレートをPoC段階から提供し、2030年3月までに50社導入を目標としています。PLMの価値は導入後の定着化にあります。変更要求(ECR/ECO)の運用やCAEワークフロー共有を早期に整えると、設計の判断根拠が蓄積され、再利用性と教育効率が一気に上がります。
参考リンク
DIGITAL X:PLMシステムを基盤にエンジニアリングチェーンの最適化を支援するサービス、SCSKが開始
5. 日本郵船が配船最適化AIを本格運用——数百万通りの計画を約10分で試算、CO2削減にも寄与
概要
日本郵船は、自動車専用船の配船計画を最適化するAIシステムを本格運用しました。顧客需要、船隊の稼働・整備予定、港湾混雑、カーボンプライスなどを考慮し、数カ月先までの数百万通りの案を約10分で試算。最も合理的な計画を立案します。グループのMTIとAI企業グリッドと共同開発し、GHG排出削減や運航コストの最適化を狙います。
中小企業への影響
輸配送や工程計画でも、組合せ最適化×AIの有効性が示されました。車両、便、作業者、工程順序などの制約を同時に満たす「最適解」は人手では捻出困難ですが、制約条件を正しくモデル化できれば劇的な時間短縮が可能です。中小でも、配送ルート最適化、ピッキング順序、段取り替えなどでインパクトが出ます。加えて、燃費やCO2排出など外部コストを評価に入れると、省エネ補助金や顧客の脱炭素要件にも応えやすくなります。
経営者の視点
まずは「現状の計画作成に何分かかり、ムダ時間がどれだけあるか」を測定し、最適化で削りたいKPIを明確化。データ品質(在庫、位置、時間、容積)を揃え、ビジネスルールを数式化する準備が成否を分けます。早期に人が最終判断する運用を決め、例外処理フローを設計すると現場が安心して使えます。試行段階では1エリア・1商品のみでROIを見せ、段階展開で全社適用を目指しましょう。
同社は100隻超の自動車専用船を運航し、数百の航海予定に対し、港での滞船リスクや修繕計画、荷主の急な需要変動など相反する条件を同時に満たす必要があります。これまでは熟練者の経験に依存しがちでしたが、AIに複雑制約を明示し、次世代燃料船の稼働も加味して計画できることで、稼働率とサービスレベルの両立がしやすくなります。結果として、輸送コストの最適化と排出量の見える化が進み、サプライチェーン全体のレジリエンス強化にもつながります。
参考リンク
DIGITAL X:日本郵船、自動車専用船の配送計画を策定するAIシステムを導入
まとめ
生成AIの実装、ネットワーク基盤、工程データの一元化、国際的な先進事例、最適化AIの活用——9月19日〜25日の動きは、“現場で成果を出すDX”が主役でした。重要なのは、どれも小さく始めて素早く検証し、定着させる運用が成果の源泉だという点です。
行動の一手は明確です。①“探す時間”を測り、社内検索×生成AIで削減、②工場ネットワークのアセスメントで停止リスクを見える化、③PLM/BOM/工程の整合を計測してテンプレートを整える、④最適化のPoCを配送・工程のどちらかで着手、⑤KPIとログを経営資産として残す——の順に、90日単位で回していきましょう。
次回も、最新のDXニュースを経営者の意思決定に直結する観点で解説します。