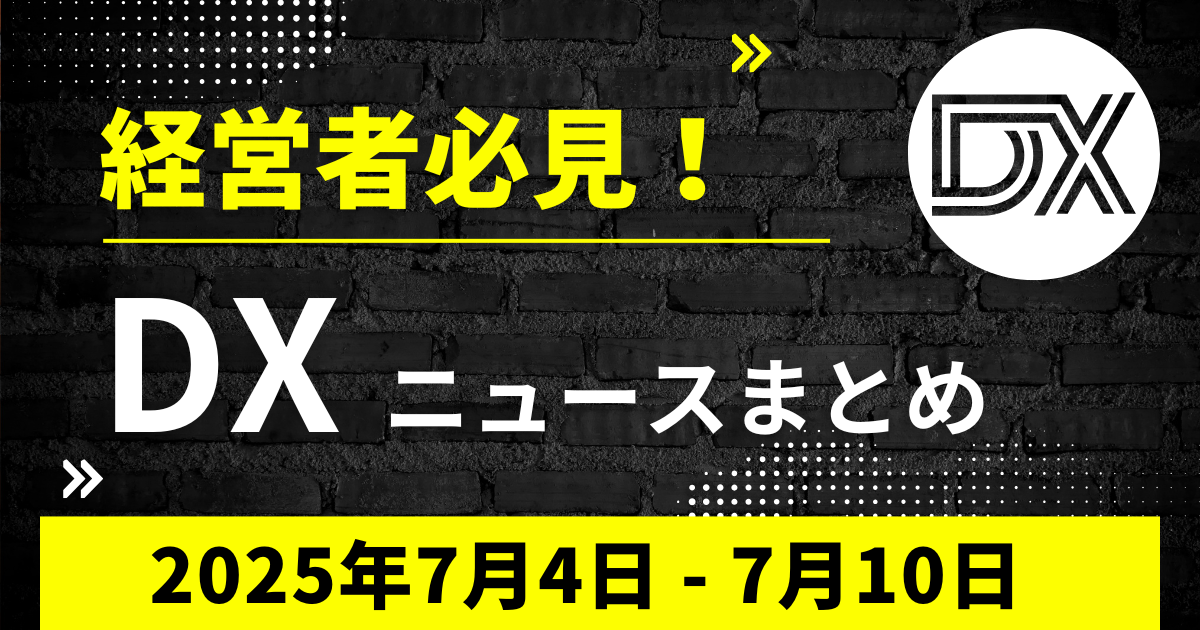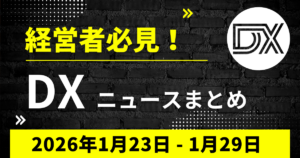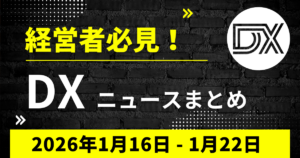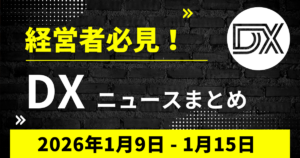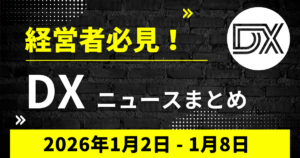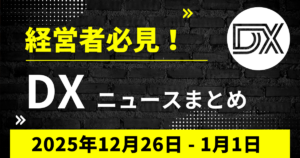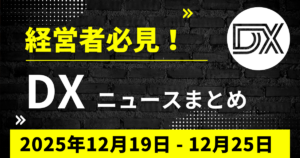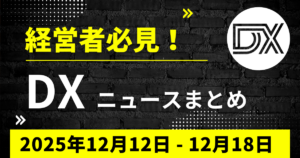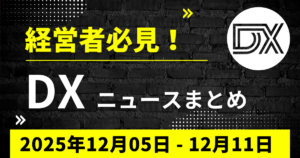DXニュースまとめ(2025年7月4日〜7月10日)
デジタルトランスフォーメーション(DX)分野では、日本国内で中小企業に関わる重要な動きが相次ぎました。地方自治体は専門企業と組んで中小企業のデジタル化支援に乗り出し、通信大手はAIを駆使した新会社で流通の効率化を図っています。また、IT企業からは中小企業向けのDX人材サービスが登場し、人材企業は地方拠点を開設して地域のIT人材不足に対応を始めました。さらに、地方銀行も連携して小規模事業者の課題解決に取り組む動きを見せています。今回は注目の5つのニュースをピックアップし、その概要とポイントを中小企業目線で解説します。経営者の皆さんが自社のDX戦略を考える上で役立つ情報ばかりです。それでは、それぞれのニュースを見ていきましょう。
1. 中小企業向けDX研修、千葉県で本格始動
概要
千葉県が中小企業のデジタル化推進に向けて新たな支援事業を開始しました。県の産業振興センターによる「令和7年度中小企業デジタル技術活用支援事業」の実施業務を、ITコンサル企業のフォーバルが受託しています。同社は県内中小企業に対し、デジタル技術の活用法を学べるセミナーや、個別企業に寄り添った伴走型の研修プログラムを提供します。セミナーではDXの必要性や成功事例、AIを使った業務改善などを分かりやすく解説し、研修では専門家が各社の課題分析から解決策の提案・実践まで約半年にわたり支援します。これにより「何から手を付ければいいか分からない」という企業にも具体的なロードマップが示され、県内のDX底上げにつなげる狙いです。
中小企業への影響
行政主導で無料のDX研修機会が提供されるのは、中小企業にとって追い風です。自社だけでは人材やノウハウ不足で遅れていたデジタル化に、専門家のサポートを受けながら取り組めるようになります。例えば紙の書類が多い業務をオンライン化する方法や、顧客管理にITツールを導入する手順など、実践的な知識を学べるでしょう。また、このような公的支援事業は成果が出れば他の自治体にも広がる可能性があります。地域全体でDXが進めば、取引先とのデジタル連携がスムーズになるなど経営効率の向上にもつながります。一方で、研修で学んだ内容を定着させるには経営者自身の継続的なコミットメントが必要です。支援を受けっぱなしにせず、自社の実情に合わせて計画を実行し、社員と一緒に地道に改善を進める姿勢が求められます。
経営者の視点
経営者としてまず注目すべきは、「使える支援は積極的に活用する」という姿勢です。今回のような県のDX支援事業に自社が参加できるなら、ぜひ手を挙げましょう。専門家のアドバイスを得ることで、自社の課題を客観的に把握しやすくなります。また、研修で得た知見は社内に共有し、社員とDXの重要性を再認識する機会にしましょう。仮に自社が千葉県外であっても、類似の支援策や補助金がないか自治体や商工会議所に問い合わせてみる価値があります。「まず小さく試す」ことも大切です。一度に大きな投資をせず、研修で紹介されたツールの一部を試用してみる、社内の紙業務を一つ電子化してみるなど、小さな成功体験を積み重ねましょう。行政の後押しという追い風を受けつつ、自社のDXを前に進めるのは経営者次第です。このチャンスを逃さず、自社の競争力強化につなげていきましょう。
参考リンク
フォーバル、千葉県「令和7年度中小企業デジタル技術活用支援事業」を受託(株探ニュース)
2. NTT、大手流通と連携しAI活用の新会社を設立
概要
NTTグループが流通業界向けのDX新会社「Retail-CIX(リテール・シーアイエックス)」を設立しました(7月8日発表)。NTT子会社のAI企業と、小売チェーン大手トライアルHD傘下のRetail AI社が共同出資し、小売業のサプライチェーン最適化サービスを展開します。この新会社では、POSデータなどを活用した需要予測と、複数のAIを連携させて発注・配送・棚卸しを自動で最適化する「連鎖型AIエージェント」という技術を提供します。例えば、天候や販売ペースをAIが予測して最適な発注量とタイミングを算出し、在庫過多や品切れを防ぐといった機能です。実証実験では店舗作業コストや在庫量を約20%削減する成果も出ており、今後は小売だけでなく卸売・メーカーとも連携して、生産計画の効率化や食品ロス削減などサプライチェーン全体の効率アップを目指すとしています。
中小企業への影響
このニュースは一見大企業の話に思えますが、流通業界のDX加速は中小の小売店や製造業者にも影響を及ぼします。大手チェーンがAIで在庫管理を高度化すれば、取引先である中小メーカーや卸業者も迅速で柔軟な対応を求められる可能性があります。例えば、これまで月単位だった発注が需要予測に基づき細かくなれば、生産計画の調整力が問われるでしょう。一方で、こうした高度な仕組みに中小企業が取り残されないよう、新会社のサービス自体が手頃に利用できる可能性もあります。クラウド型で提供されれば、IT投資に余裕がない中小店舗でも部分的にサービスを導入し、売れ残り削減や欠品防止といったメリットを享受できるかもしれません。また、AIが物流効率を上げれば配送コストが下がり、地域の小売店にも商品が安定供給されるなどプラスの波及効果も期待できます。重要なのは、大企業のDX動向を他人事とせず、自社のビジネス環境がどう変わり得るかアンテナを張ることです。
経営者の視点
小売業や製造業の経営者にとって、データに基づく意思決定は今後避けて通れない流れです。今回の取り組みはAI活用で在庫管理や物流を効率化するものですが、中小企業でも規模に応じたデジタル活用は可能です。例えば小さなお店でも、POSレジの販売データを分析して発注判断に活かす、といったことから始められます。経営者は「勘と経験だけに頼った経営」から一歩進み、数字やAIの助言を取り入れる経営にシフトしましょう。また、大手が構築するデジタルネットワークに自社も参加できないか注視することです。サプライヤーであれば取引先のDX施策に対応するため、自社の商品マスタや在庫情報をデジタルでやり取りできるように準備する必要があるかもしれません。逆に自社がお客様に商品を卸す立場なら、発注システムの導入やECサイト整備など、取引の電子化を進めておくと競争力につながります。AI時代の波は大企業から中小企業まで押し寄せます。怖がるよりも上手に乗るつもりで、自社に活用できる部分を見極め、徐々に取り入れていきましょう。
参考リンク
NTTがリテールDX新会社「Retail-CIX」を設立(BUSINESS NETWORK)
3. “DX職”サービス登場、中小企業に専門人材を提供
概要
IT人材サービス企業のシードテック(ギークスグループ)が、中小企業向けのデジタル化支援サービス「DX職(デジショク)」を7月7日付でリリースしました。これは、デジタル推進を担う社内DX人材を持たない企業に対し、同社がその役割を丸ごと引き受けるユニークなサービスです。具体的には、まず専門スタッフが企業を訪問し現状を診断する「デジショク診断」を実施。その結果をもとに企業ごとの「DX地図」(ロードマップ)を作成し、目標設定から施策立案を支援します。さらに、必要なITツールの導入や業務フロー改善、社員へのIT研修、導入後の保守運用まで、一連のプロセスをワンストップで伴走します。初期提供エリアは神戸市を中心とした関西ですが、将来的には全国の中小企業へ展開予定とのことです。まさに「DX版の社外CTO」をレンタルするようなサービスであり、人材不足でDXが進まない企業の課題解決を目指しています。
中小企業への影響
多くの中小企業にとって、DX推進の最大の壁は人材です。専門のIT担当者もいない中で新しいシステム導入や業務改革を進めるのは難しく、結果としてデジタル化が後回しになりがちでした。このサービスが普及すれば、そうした企業でも外部の専門家チームの力を借りてDXに着手できるようになります。例えば「紙の在庫台帳をどう電子化すれば?」と悩んでいた企業も、DX職サービスの診断で最適なソフトを提案してもらい、導入・設定まで任せられるでしょう。また、単なるコンサルで提案をもらうだけでなく、実行支援や定着化までフォローする点は心強い特徴です。一方で、中小企業側にも意識改革が必要です。外部任せにするのではなく、社内にDXの知見を蓄積する努力も並行して行わないと、プロジェクト終了後に元の木阿弥となりかねません。サービス利用には一定のコストもかかるでしょうから、効果を最大化するために社長含め社員が一丸となって取り組むことが重要です。総じて「人がいないから無理」という状況を打破できるサービスとして、中小企業に新たな選択肢を提供すると言えます。
経営者の視点
経営者としては、「できる人がいないなら外部の力を借りる」という柔軟な発想が求められます。DXの必要性は感じていても、人材不足で動けないままでいるより、専門サービスを活用してまず一歩踏み出す方が建設的です。このサービスを利用すれば、自社の弱点を知り尽くしたプロが伴走してくれるわけですから、安心感があります。ただし任せきりではなく、自社内にDX推進の文化を育てる機会と捉えましょう。例えば診断結果や提案を社員と共有し、なぜその施策が必要なのか理解を深めてもらうことです。経営者自身もITに明るくなくても構いませんが、積極的に学ぶ姿勢を見せることで社員の意識も変わります。また、今回のサービス名にもなっている「DX職」という考え方は、将来的にはどの企業にも必要になるかもしれません。いずれ自社でデジタル担当を置ける規模に成長することも見据え、外部の支援者をパートナーとして扱うことが大切です。ゴールは単にITシステムを入れることではなく、デジタルを活用して自社の生産性や競争力を高めること。その視点を忘れずに、外部の知恵を借りながら自社ならではのDXを進めていきましょう。
参考リンク
中小企業向けデジタル化支援サービス「DX職 -デジショク-」をリリース(PR TIMES)
4. 人材企業レバテック、地方拠点で地域DXを支援
概要
IT人材サービス大手のレバテック株式会社は7月7日、広島県と北海道に新たな拠点を開設しました。同社はフリーランスのITエンジニアと企業をマッチングする事業で知られていますが、今回の新拠点開設により地方企業へのDX支援とIT人材確保支援を一段と強化します。背景には、都市部への人口流出で地方のIT人材不足が深刻化している状況があります。レバテックはこれまで東京・大阪など大都市圏中心に展開してきましたが、蓄積したノウハウを地方にも広げることで、地域の企業と優秀なIT人材の橋渡しを目指すとのことです。具体的には、地方企業に対してリモートも含めたフリーランスエンジニアの活用提案を行ったり、IT人材の採用コンサルティングを行う計画です。「日本を、IT先進国に。」というビジョンのもと、同社は地方創生とデジタル化促進に貢献したい考えです。
中小企業への影響
地方の中小企業にとって、人材企業の地域進出は頼もしいサポートとなり得ます。これまで地方では「そもそもIT人材が応募に来ない」「専門の制作会社が近くにない」といった理由でDXが進みにくい側面がありました。レバテックのような仲介役が地元にできることで、必要なスキルを持つ人材を全国からリモートで紹介してもらえたり、短期プロジェクト単位でフリーランスに依頼したりと、人材確保の選択肢が広がります。例えば、小規模なメーカーがECサイトを立ち上げたい場合でも、都心の優秀なエンジニアにオンラインで協力を仰げるかもしれません。また、同社が地方企業向けにDX推進の相談窓口になることで、「何から始めれば?」という漠然とした悩みに対しても適切な人材やサービスを案内してもらえる可能性があります。一方、こうしたサービスを活用する際には費用対効果を考えることも重要です。スポットで専門家を呼ぶ場合、成果物の品質管理や自社メンバーへの引き継ぎも考慮しなければなりません。しかし総じて、地方企業にとって地理的ハンデを超えて人材を得る手段が増えるのはDX推進に追い風となるでしょう。
経営者の視点
地方で事業を営む経営者にとって、「人材がいないからできない」はもはや言い訳にできなくなりつつあります。今回のように専門サービス側から地域に歩み寄ってきている今こそ、自社の課題にマッチした人材リソースを柔軟に活用するチャンスです。経営者はまず、自社のDXニーズを明確にしましょう。「どんなスキルがあれば業務改善できるのか」「IT専門家に何を手伝ってほしいのか」を言語化した上で、レバテックのようなサービスに相談すると話が早くなります。また、非常駐の専門家とも上手に協働する体制づくりもポイントです。例えば週に数時間のリモート支援でも効果を出すには、社内に窓口担当を決め、依頼内容や進捗をしっかり共有することが欠かせません。経営トップ自らがITに詳しくなくても、こうした外部人材を使いこなすことで成果を上げている企業も増えています。さらに、将来的には紹介を受けたフリーランス人材を正社員としてスカウトするようなケースも考えられます。「必要な時に、必要なスキルを借りる」発想で、まずは足りない部分を埋めつつ、自社内の人材育成も並行して進めればベストです。地域にいながら全国レベルの人材と仕事ができる時代を積極的に活用し、地方発のDX成功例をぜひ生み出していきましょう。
参考リンク
レバテック、広島・北海道に新拠点開設で地方企業のDX・IT人材支援を強化(PR TIMES)
5. 地銀9行が結集、小規模事業者のDX支援で連携
概要
地方銀行がDX支援のために横の連携を強める動きもありました。ベンチャーキャピタルのファーストライト・キャピタルは7月10日、地方銀行9行(常陽銀行、静岡銀行、山陰合同銀行、中国銀行、山口銀行、四国銀行、福岡銀行、佐賀銀行、鹿児島銀行)と共同で「地域課題解決DXコンソーシアム」という勉強会を東京都内で開催しました。この全体会合では、小売・サービス業など地域の中小店舗事業者が直面する課題をテーマに、DXによる解決策を探るディスカッションが行われました。各銀行から延べ25名の行員が参加し、それぞれの地域企業の現状や取り組み事例を共有したと伝えられています。銀行同士が枠を超えて情報交換し合うことで、効果的なDX支援策を模索するのが狙いです。例えば、ある銀行が成功させた商店街のキャッシュレス導入支援策などを他行が学び、自地域に応用するといった協業が期待されています。
中小企業への影響
地域の金融機関がDX推進に関与を深めることは、中小企業にとって頼もしい追い風です。銀行は企業の資金繰りを見る立場から、取引先の生産性向上や経営安定に強い関心を持っています。9行が知恵を出し合う今回のような取り組みを通じて、例えば商店向けのデジタル化支援パッケージや、簡単に使える業務効率化ツールの紹介制度などが生まれるかもしれません。また、銀行員自らがDXに詳しくなれば、普段の融資相談や訪問の際に企業へ有益なアドバイスができるようになるでしょう。すでに千葉県では銀行主導のDXコミュニティが始まっていますが、複数県にまたがる広域連携は全国的にも珍しく、これが成功すれば他地域への波及効果も期待できます。中小企業側から見ると、「銀行がDX相談に乗ってくれる」時代が来る可能性があります。従来は資金繰りの話が中心だった金融機関との対話に、IT活用や業務改善といったテーマが加わるわけです。ただし、具体的な支援策が形になるには時間もかかるでしょう。まずは経営者が自社の課題を銀行担当者に伝え、情報提供や専門家紹介を依頼するなど、双方向のコミュニケーションが重要になります。
経営者の視点
経営者にとって銀行はお金を借りるだけの存在ではなく、経営パートナーとして活用できる時代になりつつあります。今回のコンソーシアムのように銀行がDXに本腰を入れる背景には、取引先企業に元気になってもらわないと銀行自身も成長が見込めないという事情があります。これは裏を返せば「銀行は本気で中小企業の改善を支援したがっている」ということです。経営者は遠慮せず、自社のDXに関する悩みや計画を金融機関に相談してみましょう。「伝票処理を電子化したいが良い方法は?」「補助金情報が欲しい」など具体的に聞けば、行員がネットワークを駆使して情報を集めてくれるかもしれません。銀行によってはITコンサル部署を持つところも増えており、場合によっては専門家を派遣してくれることもあります。また、今回テーマに挙がった小売・サービス業のように、自社の属する業界特有の課題についても銀行と意見交換すると視野が広がります。例えば商店経営者であれば、「他地域ではどんなデジタル集客をしているか」を銀行経由で知るチャンスがあるかもしれません。重要なのは、銀行からの提案を待つだけでなく、経営者自ら情報発信しに行く姿勢です。金融機関という心強い後ろ盾を得て、自社のDXを推進する道をぜひ切り拓いてください。
参考リンク
ファーストライト・キャピタルと地銀9行、DXコンソーシアム開催(ニッキンONLINE)
まとめ
今週取り上げたニュースから見えてくるのは、中小企業のDXを支えるエコシステムが各方面で動き出していることです。自治体による直接支援から、大手企業の新サービス提供、人材会社の地方進出、金融機関の連携まで、あらゆるプレーヤーが中小企業のデジタル化促進に関わり始めています。これは裏を返せば、それだけ中小企業のDXが日本経済全体にとって避けて通れない課題になっているということです。
経営者の皆さんに共通して言えるのは、「使えるリソースは積極的に使い、学べることはどんどん学ぶ」という姿勢でしょう。国や自治体の支援策があればまず情報をキャッチし、可能なら活用する。他社が導入した新しいサービスは自社でも使えないか検討する。銀行や専門企業から提案や協力の申し出があれば前向きに耳を傾ける——そうしたオープンマインドが、自社のDXを前進させる原動力になります。一方で、外部の力に頼りすぎず自社にノウハウを蓄積する努力も忘れないことが重要です。デジタル化はゴールではなくスタートです。ツールを導入して終わりではなく、使いこなして業績向上につなげるまで継続的な改善が必要です。
幸いなことに、今は情報も支援も豊富に手に入る時代です。今回のニュースにあったような取り組みをヒントに、自社に足りないものは何か、今どんな一歩を踏み出せるかをぜひ考えてみてください。小さな一歩でも動き出せば、社内の意識が変わり、新たなチャンスが見えてくるはずです。