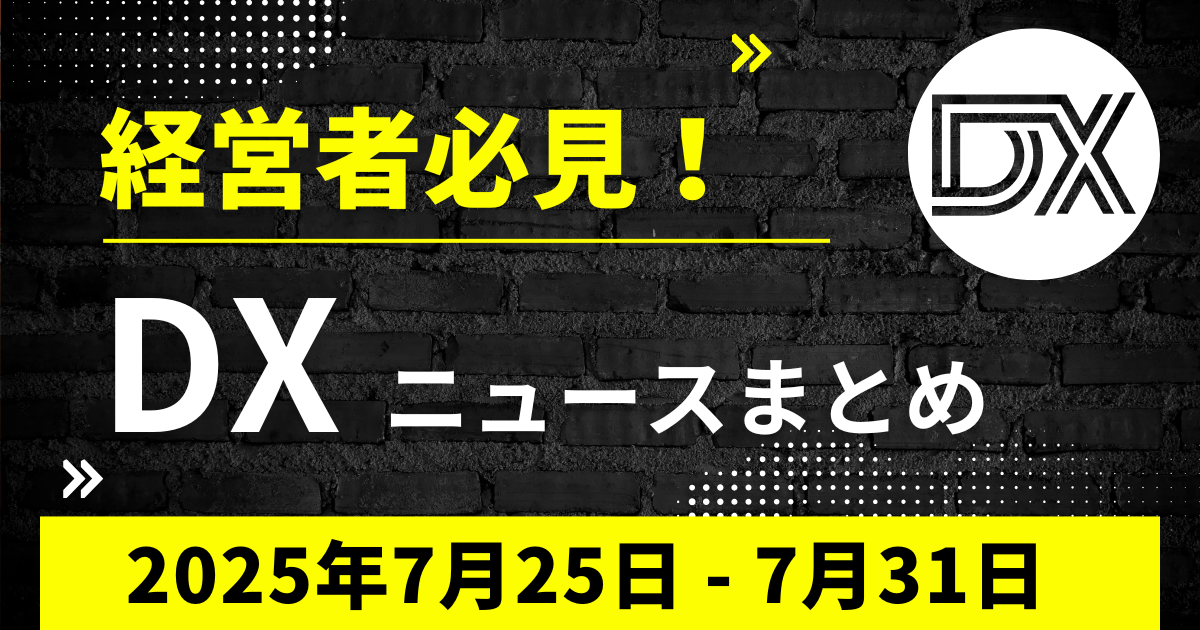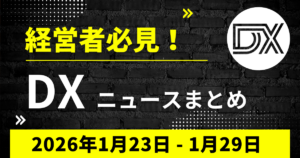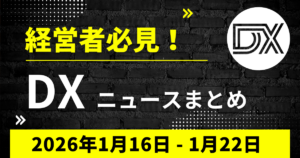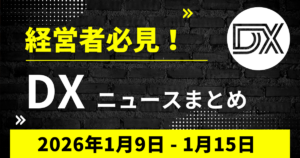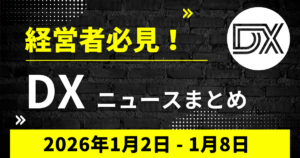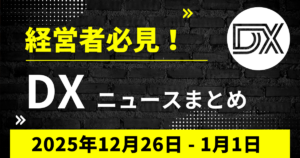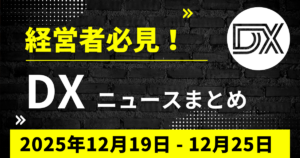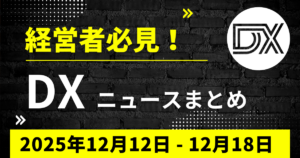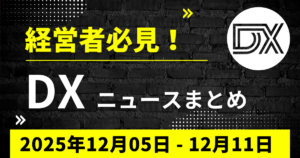DXニュースまとめ(2025年7月25日〜7月31日)
DX(デジタルトランスフォーメーション)分野では、中小企業に関連する重要な動きが相次ぎました。長野県須坂市が専門家伴走型の中小企業DX支援策を開始し、国のIT導入補助金では店舗運営DXツールが新たに認定を受けています。また、DX支援企業同士がサイバーセキュリティ分野で提携し、大手企業キリンHDの全社DXからは「失敗データの活用」という示唆が得られました。さらに、製造業向けのDXソリューションが一挙に公開されるなど、幅広い領域でDX推進の動きが進んでいます。注目の5つのニュースとそのポイントを、中小企業への意味合いとともに解説します。経営者の皆さんが自社のDX戦略を考える一助になれば幸いです。
1. フォーバル、長野県須坂市の中小企業DX推進支援業務を受託
概要
長野県須坂市が、中小企業のデジタル化を支援する新たなプロジェクトを開始し、経営コンサルティングのフォーバルがその実施業務を受託しました。DXの基礎知識や導入事例を紹介する普及啓発セミナーの開催、専門家による約5か月間の伴走支援、そして成果発表会の実施を通じて、地域企業の生産性向上や経営課題解決を図ります。フォーバルは既に県内各地でDX支援を展開しており、今回の取り組みにより地域資源を活かした「DXの地産地消」モデルをさらに推進するとしています。
中小企業への影響
行政主導で専門家によるDX支援を受けられることは中小企業にとって大きな追い風です。自社のみでは遅れていたデジタル化も、こうした支援を活用すれば取り組みやすくなるでしょう。DX診断や専門家のアドバイスによって自社の課題が可視化され、適切なITツール導入や業務改善に繋げられます。また、このような自治体支援が成果を上げれば他地域にも広がり、地域全体で取引や業務のデジタル連携が進む可能性があります。注意点として、外部の助けに頼りきりでは変革は定着しません。提案で得た改善策を社内で継続実行するには、経営者自身の強いコミットメントが不可欠です。支援をきっかけに自社のDXを地道に推進する姿勢が求められます。
経営者の視点
経営者にとって重要なのは「使える支援は積極的に活用する」ことです。今回のような公的DX支援に応募できるならぜひ手を挙げ、専門家の助言で自社課題を客観的に把握しましょう。また、支援で得た知見は社内で共有し、社員とDXの必要性を再認識する機会にしてください。仮に自社が対象地域外でも、自治体や商工会議所に同様の支援策がないか問い合わせてみる価値があります。まずは大きな投資をせず、小さな部分からデジタル化を試すことも大切です。行政の後押しという追い風を受けつつ、DXを前に進められるかどうかは経営者次第。この好機を逃さず、自社の競争力強化につなげましょう。
参考リンク
フォーバル—長野県須坂市の令和7年度「中小企業DX推進支援業務」を受託(株探ニュース)
2. Shopify連携の店舗運営DXプラットフォーム「shopikin」、IT導入補助金2025対象ツールに認定
概要
Shopifyと業務システムを連携し店舗運営を効率化するプラットフォーム「shopikin(ショピキン)」が、経済産業省・中小企業庁のIT導入補助金2025における認定ITツールに選ばれました。これにより対象となる中小企業・小規模事業者がshopikinを導入する際、最大150万円(費用の1/2、要件次第で2/3)の補助金を受けられ、ECと店舗を一元管理するDXツールを低コストで導入できます。shopikinはShopifyのECデータと店舗の顧客・販売情報をクラウドデータベース(キントーン)で一元管理し、受注から発送までのバックオフィス業務の省力化や、顧客購買データの集約によるマーケティング力強化を実現するサービスです。さらに、自社の業態に合わせてアプリの追加や機能拡張が可能なセミオーダー式で、成長に応じたカスタマイズにも対応しています。
中小企業への影響
補助金認定により、デジタルツール導入のハードルが下がることは小規模事業者にとって朗報です。特に店舗とECを併営する小売業では、受発注や在庫、顧客情報を別々に管理して非効率になりがちですが、shopikinのような統合プラットフォームを補助金を活用して導入すれば、業務効率と顧客サービスの向上が期待できます。また、今回の認定は政府が中小企業のDXを具体的な形で後押ししている例と言えます。自社に合うITツールが補助金対象となっていないか定期的に情報収集することで、思わぬ助成を受けながらデジタル化を進めるチャンスを見逃さずに済むでしょう。
経営者の視点
経営者は国や自治体のDX支援策を積極的に活用すべきです。IT導入補助金はその代表例で、今回のように自社の業務効率化に役立つツールが認定されたなら、導入コストを大幅に抑える好機です。補助金申請には事前準備や支援事業者との連携が必要ですが、多少の手間をかけても得られるメリットは大きいでしょう。自社の現場でどんな作業が手間になっているかを洗い出し、それを解決するITツールが補助対象になっていれば導入を前向きに検討してください。公的支援を賢く使って、省力化や売上向上につながるDXを一歩ずつ進めましょう。
参考リンク
Shopify・店舗運営DXプラットフォーム「shopikin」が「IT導入補助金2025」対象ツールに認定(PR TIMES)
3. DX支援のセルプロモート、AIセキュリティ企業スライスチーズと業務提携
概要
中小企業のDXコンサルティングを手がけるセルプロモート株式会社と、AIを活用したセキュリティサービスを提供する株式会社スライスチーズが、サイバーセキュリティ分野で業務提携しました。DXの加速やリモートワークの普及に伴い、中小企業を取り巻くサイバー脅威は一段と深刻さを増していますが、多くの企業でセキュリティ人材や対策が不足しているのが実情です。今回の提携では、セルプロモートのDX支援ノウハウとスライスチーズのAIセキュリティ技術を組み合わせ、脆弱性診断から対策導入支援、インシデント対応までワンストップで提供する体制を構築します。両社が協力することで、中小企業が迅速かつ安心してデジタル化を進められるよう支援し、DX推進に不可欠なセキュリティ水準の向上を目指します。
中小企業への影響
DX推進においてセキュリティ強化は避けて通れません。しかし中小企業では専門知識や人材が不足し、自社だけで万全の対策を講じるのは難しいのが現状です。今回の提携により、中小企業向けに特化した包括的なセキュリティ支援が身近になることは大きなメリットです。例えばクラウド活用やリモートワーク拡大で懸念される情報漏洩リスクも、外部専門家による診断やAI技術を使った監視サービスで低減できるでしょう。安心してITを活用できれば、DXによる業務効率化やサービス向上にも一層専念しやすくなります。一方で、経営者も「自社は大丈夫」と油断せず、社員へのセキュリティ教育や基本対策の徹底といった取り組みは引き続き欠かせません。
経営者の視点
経営者はDX推進とサイバーセキュリティをセットで考える必要があります。新たなITツールを導入する際にはセキュリティ面の確認や対策を怠らないようにしましょう。専門企業との提携サービスは、自社に不足するセキュリティ知見を補う有効な手段です。今回のセルプロモートのようにDX支援企業が安全面まで提供してくれるなら、安心してデジタル化を進められます。まずは社内でも機密データのアクセス権管理や定期的なバックアップ、社員へのセキュリティ教育など基本の対策を実施してください。守りを固めつつDXを推進することで、万一の事故による信用失墜を防ぎ、安心して成長戦略に集中できるでしょう。
参考リンク
中小企業向けDX支援のセルプロモートと、AIセキュリティ支援のスライスチーズが業務提携を締結(PR TIMES)
4. キリンHD、全社DXの取り組みから「失敗データは宝」の教訓
概要
キリンホールディングス(HD)はAIを活用した「AI面接官」や全社員が使える社内AIツールの導入など、全社規模でDXに取り組んでいます。こうした様々な挑戦を通じて、同社の経営陣が気付いたのは「失敗したデータこそ宝」だという点です。例えば新しいAIシステムの試行が期待通りの成果に繋がらなくても、その過程で蓄積されたデータや知見は次の改善に繋がる貴重な資源となります。キリンHDでは現場から経営層まで社員がDXに参加し、試行錯誤で得た学びを社内で共有する文化を築くことで、持続的なイノベーションを生み出そうとしています。
中小企業への影響
この事例は、DX推進におけるチャレンジ精神と学習の重要性を教えてくれます。大企業の話とはいえ、中小企業にとっても「小さく試す→学ぶ→改善する」という機動力は見習うべきポイントです。デジタル化の取り組みがうまくいかなかったとしても、そこで得られた洞察を分析すれば次の打ち手が見えてきます。「失敗を恐れずトライし、失敗から学ぶ」姿勢は、リソースが限られた企業こそ持ちたい強みと言えるでしょう。また、キリンのように社員全員がDXに関わる環境づくりも参考になります。現場の声を反映すればツールの定着率も上がり、小さな成功体験の積み重ねがDX推進の原動力となるはずです。
経営者の視点
経営者はDXにおいて「短期間で完璧を目指す」のではなく、俊敏に試し、失敗から学ぶマインドセットを組織に根付かせましょう。例えば新しい業務システムやAIサービスを導入する際には、限定的な範囲でパイロット運用し、結果を検証してから本格展開するといった方法が有効です。仮に期待通りの成果が出なくても、その理由を分析することで次の選択肢が明確になります。社員には改善提案や気付きの共有を促し、DX推進を全員参加型のプロジェクトにしてください。トップが失敗を咎めず学びを称賛すれば、挑戦する風土が醸成されます。小さなPDCAサイクルを回し続けていけば、やがて自社なりのDX成功モデルが築かれていくでしょう。
参考リンク
「失敗したデータこそ宝」 AI面接官に全社向けAIツール、キリンHDが気付いた全社DXの真髄(ITmediaビジネスオンライン)
5. 製造業向けDXソリューションを13種提供開始、ポータルサイトも開設
概要
ソフトウェア品質保証で知られる株式会社SHIFTは、製造業のDX課題を解決する13種類のソリューション提供を開始し、情報発信のための「製造DXポータル」サイトも開設しました。製造業では製品にソフトウェアを組み込み、単なるモノ売りから顧客体験価値を高めるコト売りへの転換が進んでおり、DXの重要性が増しています。SHIFTはこれまでに延べ350社以上の製造企業を支援してきた実績を活かし、研究開発から調達・生産、アフターサービスに至るバリューチェーン全体をカバーする多様なソリューション群を用意しました。ソリューションには生成AIの活用による競争力強化支援、製品開発におけるソフトウェア品質向上支援、WebサイトのUX改善による顧客満足度向上策などが含まれ、各企業の状況に応じて選択できます。新設のポータルサイトでは、事例やノウハウを公開し、業界全体のDX促進を図るとしています。
中小企業への影響
製造業の中小企業にとって、自社DXを進めるうえで頼りになる選択肢が増える形です。高度なIT人材を抱えない企業でも、SHIFTのような外部専門家の伴走支援を受けることで、設備の自動化や品質向上といったDXプロジェクトを効率的に進められる可能性があります。ポータルサイトに掲載された先進事例やソリューション情報は、何から手を付けるべきか悩んでいる経営者にとって有益なヒントになるでしょう。大手だけでなく中堅・中小の製造業もDXの波に乗り遅れないために、こうした情報を参考に自社に合った変革プランを検討してみてください。
経営者の視点
製造業界ではDXによって生産性向上だけでなく、新たなビジネスモデルへの転換や人材不足への対応も期待されています。経営者は自社の課題を洗い出し、解決につながる技術やサービスを積極的に調べましょう。今回のように専門企業が多数のソリューションを公開している場合、自社に近い規模・業種の導入事例を探すのがおすすめです。身近な成功例は社員にも共有し、自社でもやればできるという意識改革につなげましょう。また、いきなり大規模な設備投資をするのではなく、まずは安価なクラウドサービスの試用や一部工程のデジタル化から始めるなど、段階的にDXを進めるとリスクを抑えられます。外部の知見も取り入れつつ、継続的に改善を重ねて、自社の強みにフィットしたDXを実現していきましょう。
参考リンク
製造業350社超を支援した実績を活かし、13種類の製造DXソリューションの提供を開始(PR TIMES)
まとめ
今回紹介した動きを振り返ると、行政から大企業、専門サービス企業まで、多方面からDXの波が押し寄せていることが分かります。中小企業にとって重要なのは、一度に完璧を目指すのではなく、自社の状況に合った施策から一歩ずつ着実にデジタル化を進めることです。国の補助金や自治体の支援策、外部のDXパートナーなど利用できるものは賢く活用し、初期負担を減らしながら前進しましょう。また、他社の成功事例や大企業の教訓から学び、自社なりにアレンジして取り入れる柔軟性も欠かせません。
経営者としては、社内の意識改革と継続的な取り組みへのコミットメントがDX成功の鍵を握ります。今回のニュースにあったように、挑戦と失敗からの学びをポジティブに捉え、社員とともに試行錯誤を重ねる姿勢が求められます。今後も新たな支援策や技術トレンドが次々登場するでしょう。ぜひアンテナを高く張って情報収集を続け、適切なタイミングで自社のDX戦略に取り込み、俊敏に行動に移してください。それが中小企業がデジタル時代を生き抜き、成長につなげていく秘訣と言えるでしょう。