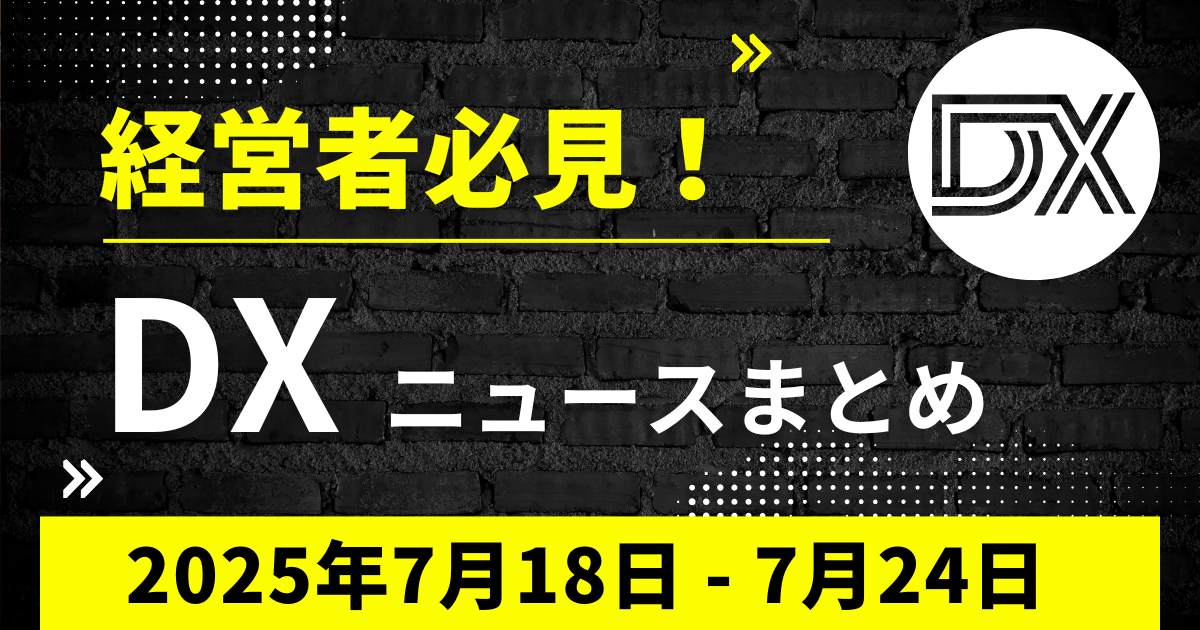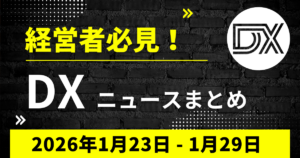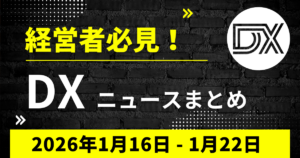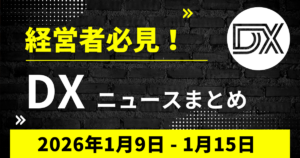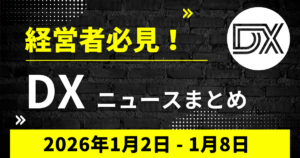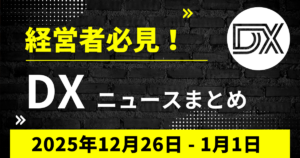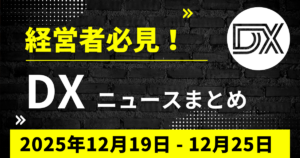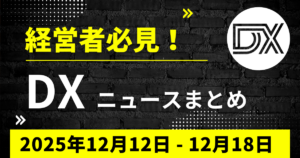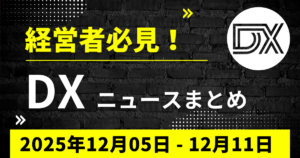DXニュースまとめ(2025年7月18日〜7月24日)
DX(デジタルトランスフォーメーション)分野では国内で中小企業に関連する重要な動きが見られました。静岡市が民間企業と連携した中小企業DX支援策を開始し、全国規模では先進的なDX事例が表彰されています。また、限られた資金や人材でも工夫してデジタル改革を成し遂げた中小企業の例も注目されました。千葉県の小規模自治体が専門家とともに地域企業のデジタル化支援に乗り出し、地方銀行も最新システム導入で業務のDXを推進しています。以下、注目の5つのニュースを取り上げ、その概要と中小企業への示唆を解説します。経営者の皆さんが自社のDX戦略を考えるヒントになれば幸いです。
1. フォーバル、静岡市の中小企業DX支援業務を受託
概要
静岡市が中小企業のデジタル化支援に向けた新プロジェクトを開始し、経営コンサル企業フォーバルがその実施業務を受託しました。人材不足や資金制約、ITリテラシー不足といった課題を抱える地域企業に対し、単なるITツール導入に留まらず内在的な変革を促す伴走型支援を行う点が特徴です。具体的に企業ごとの課題を可視化し、意思決定プロセスの見直しや業務改善の提案を行い、経営者や社員の意識改革と自走型のDX推進をサポートします。セミナー開催、モデル企業選定、補助金申請支援など支援内容は多岐にわたり、市内企業の競争力向上や地域経済活性化が期待されています。
中小企業への影響
行政主導で専門家によるDX支援を受けられることは中小企業にとって大きな追い風です。自社だけでは遅れていたデジタル化にも、こうした支援を活用すれば取り組みやすくなるでしょう。例えば紙の受発注をオンライン化する方法や顧客管理のIT化など、実践的なDXノウハウを学び自社に応用できます。また、このような自治体支援が成果を上げれば他地域にも広がり、地域全体で取引や業務のデジタル連携が進む可能性があります。注意点として、外部の助けに頼りきりでは変革は定着しません。研修や提案で得た改善策を社内で継続実行するには、経営者自身のコミットメントが不可欠です。支援をきっかけに自社のDXを地道に推進する姿勢が求められます。
経営者の視点
経営者にとって重要なのは「使える支援は積極的に活用する」ことです。今回のような公的DX支援に応募できるならぜひ手を挙げ、専門家の助言で自社課題を客観的に把握しましょう。また、支援で得た知見は社内で共有し、社員とDXの必要性を再認識する機会にしてください。仮に自社が対象地域外でも、自治体や商工会議所に同様の支援策がないか問い合わせてみる価値があります。まずは大きな投資をせず、小さな部分からデジタル化を試すことも大切です。行政の後押しという追い風を受けつつ、DXを前に進められるかどうかは経営者次第。この好機を逃さず、自社の競争力強化につなげましょう。
参考リンク
フォーバル—静岡市の令和7年度「中小企業DX支援業務」を受託(株探ニュース)
2. 日本DX大賞2025、官民の先進事例を32件表彰
概要
7月16・17日に開催された日本DX大賞2025では、官民各部門で全国の優れたDX事例が発表・表彰されました。公的機関部門と民間企業部門あわせて32件のプロジェクトが選ばれています。例えば宮崎県都城市(庁内DX部門 大賞)は、デジタルに頼り過ぎずアナログ業務改革から着手し、市民の待ち時間削減など具体的成果を上げた点が評価されました。民間部門では福岡市の屋台DXプロジェクトが、生成AIやIoTで伝統の屋台に新たな付加価値を生み出したとして注目されています。こうした先進事例からは、技術導入だけでなく現場の創意工夫や文化への配慮がDX成功の鍵と読み取れます。
中小企業への影響
表彰事例は中小企業にとってDXのヒントの宝庫です。都城市の例は「まず業務フローを見直す」という基本の重要性を示しています。大きなIT投資が難しくても、現行業務の無駄を洗い出し簡易なデジタル化から始めれば大きな成果につながる可能性があります。また福岡市の例からは、伝統的なビジネス領域でもデジタル技術で新しい価値を創出できるとわかります。自社でも紙の台帳を電子化する、簡単なチャットボットを導入して顧客対応の一部を自動化するなど、小さな工夫でDXの恩恵を得られるでしょう。重要なのは、先進事例を「自社にも応用できるとしたら?」という視点で捉え、規模に応じて取り入れてみることです。
経営者の視点
経営者は全国のDX成功例から積極的に学ぶ姿勢が求められます。自社と業種が違っても、業務改善の手法や社員の意識改革など参考になるポイントは多々あります。社内で事例研究を行い、自社に活かせるアイデアを議論してみましょう。また、自社独自のDXが進んでいるなら地域のコンテストや事例発表会に応募し、客観的な評価を得てみるのも一案です。いずれにせよ、「DXは大企業だけのものではない」ということが今回の受賞結果から改めて示されました。限られた予算や人員でも工夫次第で成果を出せると心得て、前向きに自社のDXにチャレンジしてみてください。
参考リンク
「日本DX大賞2025」全32件の受賞プロジェクトを発表(PR TIMES)
3. 資金・人材不足でも挑戦、広島の中小企業が「身の丈DX」で成功
概要
資金や人材が不足しがちな中小企業でも、自社に合った形でDXを実現した成功例があります。広島県のある金属加工企業は、大企業向け生産管理システムを導入するも自社の少量多品種生産には合わず失敗を経験しました。そこで同じ課題を持つ地元企業と共同出資でシステムを一から開発し、現場に最適な形でデジタル化を進めたのです。この“身の丈DX”によって作業効率が向上し、長時間残業やミスの頻発といった問題も解消されました。高価な最新ツールに頼るのではなく、自社の業務に合わせて持続可能な変革を起こした点がモデルケースとして注目されています。
中小企業への影響
この事例は「背伸びしないDX」の大切さを教えてくれます。多くの中小企業がDX推進で直面する資金・人材不足という壁に対し、必ずしも大企業と同じやり方を取る必要はありません。広島の企業のように複数社で協力してシステムを開発・共有すれば、一社では難しい投資やノウハウを補えます。要は自社の業務プロセスを丁寧に分析し、過不足のない範囲でデジタル化を図ることです。DXというと最新AIや巨大システムを思い浮かべがちですが、小さなExcelマクロの活用や在庫管理アプリ導入でも立派な一歩です。限られたリソースでも創意工夫でDXを実現できる余地は十分にあります。
経営者の視点
経営者として学ぶべきは「自社の身の丈に合ったDX戦略を描く」ことと「あきらめない姿勢」です。専門部署がなくても、外部の知見や他社との連携で補う道があります。例えば同業者と情報交換し合う、商工会経由で共同のIT導入を提案する、といった動きも有効でしょう。また、一度や二度DX施策が上手くいかなくても粘り強く最適解を探すことが肝心です。現場に合ったシンプルな手段でも構わないので、経営者自ら試行錯誤の先頭に立ち、小さな改善を積み重ねてください。高価な最新技術がなくても、現場の困りごとをデジタルで解決していけばそれが積み上がって自社なりのDXとなります。背伸びしすぎず足元からDXを進めることで、最終的には大きな成果を得られるでしょう。
参考リンク
同じ悩みを抱える企業と共同出資してシステムを開発。資金も人材も足りない中小企業が選んだ“身の丈”DX(ダイヤモンド・オンライン)
4. 南房総・館山市、専門家伴走のデジタル化支援事業を開始
概要
千葉県南房総市と館山市が共同で、中小企業のためのデジタル化支援事業をスタートさせました。全国で「DX学校」を展開する株式会社ディグナに運営を委託し、セミナー開催、専門家によるIT活用診断、市独自の補助金支給、導入後の伴走支援まで、4ステップで企業のDXを一貫支援する内容です。注目は両市の「デジタル化トライアル補助金」で、ソフト導入費なら最大50万円、ホームページ制作費なら25万円を上限に経費の2/3を補助する手厚い制度となっています。さらにIT導入後もDX学校の専門家が約4ヶ月間にわたり月1回の頻度で企業を訪問し、ツールが現場に定着するまで継続サポートするのが特徴です。
中小企業への影響
このような包括的支援により、DXに初挑戦の企業でも安価かつ安心してデジタル化に踏み出せます。導入後の専門家伴走支援によって「導入したが使いこなせない」という事態を防ぎ、結果が出るまで寄り添ってもらえます。DX未経験の企業でも挫折せず効果を出せる可能性が高まるのは大きなメリットです。また、こうした取り組みが全国に広がれば、中小企業全体のDXが加速するでしょう。
経営者の視点
南房総・館山地区の経営者はこの支援事業にぜひ参加しましょう。セミナー等で自社の課題に合う解決策や補助金情報を入手できます。採択されたら、支援をフル活用しつつ経営者自ら社内DXを牽引してください。専門家任せにせず、社員とともに改善策を実践することが重要です。対象地域外の企業も、自治体に働きかける・商工会に情報を問い合わせるなどして、他地域の支援策を探ってみましょう。自ら動いてチャンスを掴みにいきましょう。
参考リンク
「DX学校®」が「南房総市・館山市 市内事業者デジタル化支援事業」の実施・運営の委託を受けました(PR TIMES)
5. 島根銀行、次世代システム稼働で地域金融のDXを推進
概要
島根銀行は7月22日、SBIグループと共同開発した次世代勘定系システムの稼働を開始しました。昨年の福島銀行に続く導入第2号で、構築開始から約1年という短期間で本番稼働に至っています。新システムはフルオープンAPI対応のクラウド型で、外部サービスとの連携を柔軟かつ迅速に行えるのが特長です。従来は維持管理に追われがちだった銀行ITを戦略的サービス拡充へシフトさせ、店舗窓口業務の電子化や人員再配置による効率化を図るのが狙いです。統合データのリアルタイム活用により、新商品の開発や経営判断の迅速化も期待されています。
中小企業への影響
取引銀行のDX推進は中小企業にとって見逃せない変化です。まず、銀行の業務効率向上により融資審査や各種手続きの迅速化が進み、資金調達や日常の金融取引に要する時間と手間が減る可能性があります。さらにオープンAPI対応によって、銀行のオンラインサービスと企業の会計ソフト等を直接連携させる新たな金融サービスも期待できます。銀行と企業システムが繋がれば、入出金や請求・支払いの情報が自動連係され、経理業務の負担が大幅に軽減されるでしょう。金融機関のDX競争が進むことで、金融サービス全体のレベルアップにつながり、中小企業が受けられる利便性も高まるでしょう。
経営者の視点
経営者はメインバンクが提供するデジタルサービスに積極的に適応すべきです。オンラインでの融資申請や残高照会など新機能が始まったら活用し、経理・資金管理の省力化につなげましょう。また、可能であれば銀行APIと自社システムを連携し、入出金消込などを自動化することで業務効率を飛躍的に高められます。さらに、金融取引のデジタル化は企業間の商取引にも波及します。請求書や支払いが電子化されれば、ペーパーレスで迅速な取引が当たり前になるでしょう。その流れに乗り遅れないよう、自社も紙書類のやり取りを減らし、取引先とデジタル連携できる体制を整えておくことが大切です。
参考リンク
フューチャーアーキテクト、島根銀行に導入した「次世代バンキングシステム」が稼働開始(PR TIMES)
まとめ
今回取り上げたDX関連の動向からは、中小企業にとっても現実的かつ効果的なデジタル変革の道筋が見えてきます。行政支援、民間の先進事例、地域の協働、金融機関の変革と、多方面からDXの波が押し寄せています。
重要なのは、すぐに完璧なシステムを導入することではなく、自社の課題に合った現実的な取り組みから始めることです。補助金や伴走支援といった制度を活用すれば、初期投資を抑えて確実に前進することが可能です。また、他社の成功事例をヒントに、自社に応用できる形で取り入れていく柔軟な姿勢が求められます。
経営者としては、社内の意識を変え、継続的に取り組む覚悟がDX推進の鍵です。今後も新たな政策や支援策が登場する可能性が高いため、常にアンテナを張って情報収集し、最適なタイミングで行動に移すことが重要です。