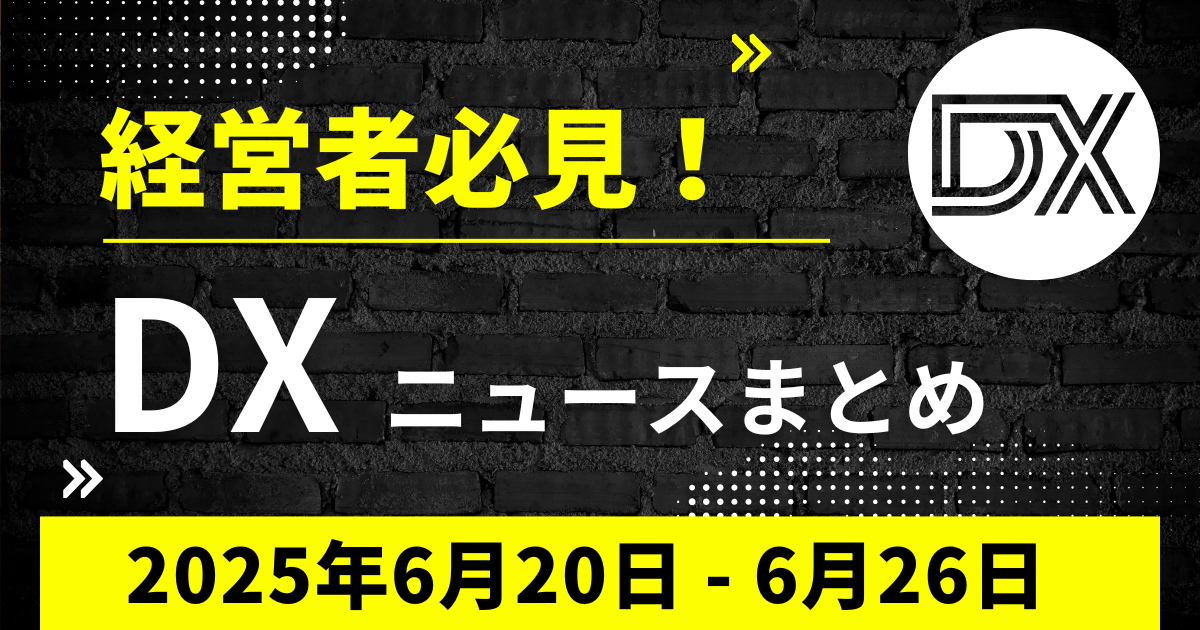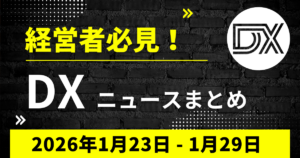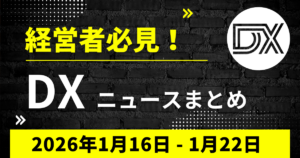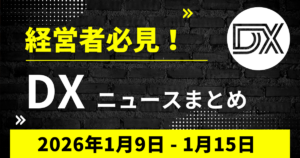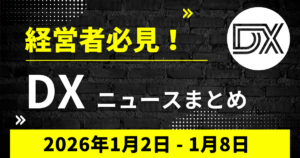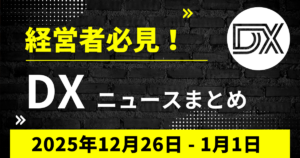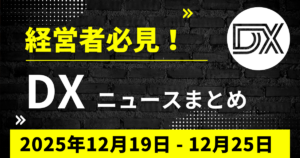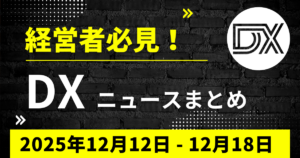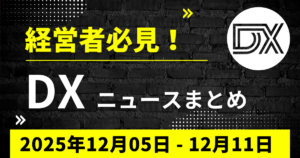DXニュースまとめ(2025年6月20日〜6月26日)
2025年6月下旬、日本国内でデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する注目すべきニュースが相次ぎました。IPA(情報処理推進機構)の報告書では、日本企業のDXが依然として内向き志向に留まり、米国・ドイツ企業と比べて成果が限定的である実態が浮き彫りになっています。また、企業の「2025年の崖」への対応状況を調査したデータからは、多くの企業でレガシーシステム(旧来の基幹システム)が残存し、このままでは経営に負の影響を及ぼすと懸念されていることが明らかになりました。一方、大手IT企業のアマゾンジャパンは地方の高等専門学校(高専)と連携し、深刻化するデジタル人材不足への対策に乗り出しています。さらに、DX人材育成サービスの新展開や、中小企業自らがDXに取り組み現場の見える化を実現した成功事例も登場しました。この記事では、これら5つのDX関連ニュースの概要とポイントを、中小企業経営者の視点でわかりやすく解説します。最新動向を把握し、自社の経営にどう活かせるか一緒に考えていきましょう。
1. IPA調査: 日本企業のDXは内向き、成果が出た企業は6割弱
概要
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が6月26日に発表したレポート「DX動向2025」により、日本・米国・ドイツ企業のDX推進状況の比較結果が明らかになりました。本調査によると、日本企業でもDXに取り組む企業の割合自体は米独と肩を並べる水準に達しています。しかし、DXによる経営面の成果が出ている企業の割合は日本が6割弱にとどまり、米国・ドイツでは8割を超えるという大きな差がついています。日本企業はDXによって達成した成果内容としてコスト削減や業務効率化を挙げるケースが多く、一方の米独企業は売上増や顧客満足度向上といった「バリューアップ」に直結する成果を挙げる割合が高い点も特徴です。つまり、日本のDXは社内改善など“内向き”の取り組みに偏りがちなのに対し、海外では市場や顧客に価値をもたらす“外向き”のDXで全社最適を図っている傾向が鮮明になりました。
中小企業への影響
この結果は、中小企業にとっても他人事ではありません。日本企業全体がDXで十分な成果を上げられていない背景には、部分最適に留まりがちな企業文化や目標設定の問題があります。中小企業でも、DXといえば社内業務の効率化やコスト削減だけで満足してしまうケースが少なくありません。しかし市場環境が激変する現代、単なる効率化だけでは競争力強化に直結しない可能性があります。日本の大企業がDXで苦戦しているという現状は、取引先や業界全体のデジタル化が進みにくい土壌を意味し、中小企業に波及するDXの恩恵も限定的になりかねません。また、大企業からのDX要求(データ共有やシステム連携など)が今後高まる可能性もあります。自社がそうした流れに対応できていなければ、ビジネス機会の損失につながるでしょう。
経営者の視点
経営者として注目すべきは、DXの目的を社内の効率改善にとどめず、如何に顧客価値や売上向上につなげるかという点です。今回のIPA調査は、日本企業のDXが「内向き」で終わりがちな課題を示しました。中小企業経営者も、自社のDX施策が単なるIT導入や業務効率化で終わっていないか見直す必要があります。例えば、顧客向けサービスの強化、新商品の開発スピード向上、データを活用した市場開拓など、DXの先にどんなビジネス成果を目指すのか明確なゴール設定が重要です。幸い政府や支援機関もDX推進策を強化しており、参考になる成功事例や指標が公開されています。自社のDX成熟度を定期的にチェックし、社内だけでなく市場に価値を生み出すDXにステップアップしていくことが、これからの生き残り戦略と言えるでしょう。
参考リンク
マイナビニュース:様相が異なる米国・ドイツ企業と日本企業のDX、課題の本丸に「全体最適」【22日付】
2. インフォマート調査: 「2025年の崖」知らない企業6割、8割が負の影響を懸念
概要
BtoBプラットフォーム事業を手掛けるインフォマート社は6月25日、「2025年の崖とDXに関する実態調査」の結果を公表しました。この調査は企業のIT部門や経営層など360名を対象に実施されたものです。その結果、調査回答企業の約58.6%が「2025年の崖」という言葉を十分に理解していないことが分かりました。一方で、「2025年の崖」が自社事業に与える影響については、「非常に大きな負の影響がある」「ある程度負の影響がある」「多少は負の影響があるかもしれない」を合わせた回答が80.4%に達し、8割以上が何らかの負の影響を懸念している状況です。さらに、回答企業の6割以上で旧式のレガシーシステムが社内に存在していることも明らかになりました。
中小企業への影響
「2025年の崖」とは、既存の古い基幹システムがこのまま残り続けると2025年以降に莫大な経済損失を招きかねないという警鐘です。この調査結果から、中小企業経営者も自社のIT基盤を見直す必要性が改めて示唆されます。大企業だけでなく、規模の小さい企業でも長年使っている販売管理ソフトや会計システムなどが更新されずに残っていれば、それは将来的なリスクの火種となり得ます。特に中小企業はIT専門人材が限られ、システム刷新が後回しになりがちです。しかし今回の調査が示すように、多くの企業が同様の課題を抱えつつ懸念を深めています。万一レガシーシステムの障害やサポート終了が起これば、業務停止やセキュリティリスク増大など深刻な影響を受けるのは中小企業ほど甚大です。取引先のDX化に遅れて信用を失う恐れもあります。
経営者の視点
経営トップとしてまずすべきは、自社に「2025年の崖」問題に該当する古いシステムがないか棚卸しすることです。仮に古い基幹系システムを抱えているならば、その刷新計画を早急に検討しましょう。調査ではレガシー刷新の壁として「日々の業務に手一杯で要員を割けない」「現行システムへの執着」「システムがブラックボックス化している」といった点が挙げられています。これらは中小企業にも思い当たる節があるでしょう。人手や予算の制約がある中小企業こそ、外部ベンダーやクラウドサービスの活用も視野に入れて、段階的にでも古いシステムの置き換えを進めることが重要です。また社員への危機意識の共有も欠かせません。「今は動いているから大丈夫」ではなく、将来を見据えてIT投資を増やし、経営のデジタル基盤を強化することが、長期的な事業継続の鍵となるでしょう。
参考リンク
IT Leaders:6割が「2025年の崖の問題を知らない」、8割はそれが事業に与える負の影響を懸念【25日付】
3. アマゾン、高専と連携 – 3年で地方デジタル人材100人育成へ
概要
アマゾンジャパン(AWSジャパン)は6月25日、旭川工業高等専門学校(北海道)および富山高等専門学校と連携し、地域のデジタル人材育成を推進することを発表しました。日本ではDXが進展する一方でIT・AI分野の人材不足が深刻な課題となっています。経済産業省の試算によれば、2040年にはAIやロボットを扱える人材が約326万人も不足する見通しです。AWSの調査でも、日本企業の68%がAIスキル人材の採用を優先事項としながら、82%の企業が必要なAI人材を確保できずに苦労していると報告されています。今回の連携で旭川高専と富山高専は、最新のAI・データサイエンス教育を提供するモデル校となり、3年間で100人以上のデジタル人材を地域から育成する計画です。
中小企業への影響
地方におけるデジタル人材の育成強化は、中小企業にとって将来的に大きなプラスとなるでしょう。現在、多くの中小企業がDX推進に二の足を踏む要因の一つに「適切なIT人材が社内にいない」ことがあります。特に地方企業では都市部に比べてデジタル人材の採用が難しく、人材流出も深刻です。今回のアマゾンと高専の取り組みは、その構造的課題に立ち向かうものです。数年先には地元で最新ITスキルを持った若い人材が輩出され、地域の中小企業もそうした人材を採用・活用できるチャンスが増える可能性があります。また、AWSが関与することで、高専発のプロジェクトに地域企業が参画したり、新しい産学連携のDX案件が生まれることも期待できます。
経営者の視点
中小企業の経営者として、このニュースから得られる視点は2つあります。まず、自社の人材戦略を長期的に考える重要性です。DXを進めるにも結局は人が必要です。地元でIT人材育成の機運が高まる今、自社もインターンシップの受け入れや高専・大学との連携に関心を持ちましょう。将来有望な学生を早期に囲い込んで育成することが、中長期的な競争力につながります。二つ目は、自社内の既存社員のスキルアップです。人材不足を嘆くだけでなく、現在働いている社員に対して積極的なDX研修や学習機会を提供することも有効です。アマゾンが大規模な人材育成に乗り出した背景には、「人材なくしてDXなし」という危機感があります。経営者もこの動きを他人事と捉えず、人材への投資が将来の事業成長に直結するという視点で社内の人材育成計画を立てていきましょう。
参考リンク
日本ネット経済新聞:アマゾンジャパン、デジタル人材育成推進 旭川高専・富山高専と連携【27日付】
4. スタディメーター、DX研修動画のセミオーダーサービス提供開始
概要
オンライン研修事業を手掛けるスタディメーター社は6月25日、企業のDX人材育成を支援する研修動画のセミオーダー型制作サービスを開始しました。同社代表の箕輪氏はUdemy上でDX講座を提供しており、2023年までに累計25万人以上が受講する実績を持っています。この豊富なコンテンツを生かしつつ、企業ごとに異なる学習ニーズに対応するために講座内容を細かいマイクロラーニング単位に分解し、組み合わせ自在な研修動画を制作できるようにしたのが新サービスの特徴です。
中小企業への影響
DX推進において人材育成は重要な柱ですが、中小企業には研修専門部署もなく、自前で教材開発や講師確保をするのは難しいのが実情です。そのため外部サービスを活用した社員研修は有力な選択肢となります。このスタディメーターのサービス開始は、そうした中小企業のDX研修ニーズに応える新たなソリューションと言えます。セミオーダー形式で無駄を省いた研修はコスト面でも割安になる可能性があり、予算が限られる中小企業にも導入しやすいでしょう。また、オンライン動画研修であれば全国どこからでも受講できるため、地方の事業所や現場スタッフにも一斉に教育を行いやすいという利点もあります。
経営者の視点
経営者にとって、人材への教育投資は直接的な成果が見えにくいため後回しにされがちです。しかしDX時代においては、社員一人ひとりのデジタルリテラシー向上が競争力の源泉になります。今回のような柔軟な研修サービスを活用し、忙しい現場社員でもスキマ時間で学べる仕組みを整えることは有効な戦略です。研修を受けっぱなしにせず、習得した知識を現場で試す機会を与えることも大切です。小規模企業の場合、DXと言っても業務改善の積み重ねが中心になるかもしれません。それでも社員がデータ活用やITツールに明るくなれば、生産性向上や新サービス創出のアイデアが生まれやすくなります。
参考リンク
ICT教育ニュース:スタディメーター、DX研修に取り組む法人向けに研修動画制作サービスを開始【27日付】
5. 長野サンコー、製造現場DX基盤導入で現場から経営まで見える化
概要
長野県の中小製造業である精密プレス金型メーカー「長野サンコー」は、製造現場のDXプラットフォーム「Smart Craft」を導入し、生産プロセスのデジタル化による業務改革を実現しました。従来、同社では紙の作業日報やエクセルでの進捗管理を行っており、作業工数の把握や情報共有に時間がかかる課題がありました。今回導入したプラットフォームにより、現場の作業者はタブレットでリアルタイムに作業データを記録できるようになり、紙ベース管理を大幅に削減しました。収集されたデータは自動で集計・可視化され、作業時間や進捗状況が即座に共有されます。さらにAPIやCSV連携を通じて基幹システムともデータが連動するため、現場から経営層までをつなぐ統合的な情報基盤が構築されました。
中小企業への影響
この事例は、地方の中小企業でもDXによって大きな効果を上げられることを示しています。製造業の現場では「熟練者のカンや経験に依存」「紙の指示書や日報が主流」という企業も多いでしょう。しかし、それでは現場で何が起きているか経営層が正確に掴めず、改善のスピードも限られてしまいます。長野サンコーは自社の課題を直視し、思い切ってDXツールを導入することで、情報の流れを変えました。近年は中小規模向けに価格や機能を調整したクラウド型サービスも増えています。本事例のSmart Craftも中小製造業に特化したSaaS型プラットフォームです。自社に合ったツールを選べば、大規模投資をしなくても段階的にデジタル化を進めることが可能です。
経営者の視点
経営者としてこの成功事例から学べるのは、「見える化」と「データの一元管理」が経営改善の起点になるということです。現場の状況がリアルタイムに見えるようになると、勘と度胸ではなくデータに基づいた経営判断が可能になります。DXは従業員に追加のIT業務を押し付けるのではなく、単純作業や情報伝達のムダを省き、本来の生産活動に集中できる環境を作ることが理想です。経営者は「現場第一」の姿勢で、現場が使いやすい仕組みを選定・導入することが成功の鍵となります。
参考リンク
MONOist:プレス金型製作メーカーが製造現場DX基盤を導入し、現場から経営まで見える化【25日付】
まとめ
今回取り上げたニュースから、DX推進の最前線で起きている動きを振り返ってみましょう。IPAの調査報告やインフォマートの実態調査は、日本企業のDXが依然途上であり、旧来システムや内向き志向という課題を克服する必要性を示しています。一方で、アマゾンジャパンの人材育成プロジェクトや新しいDX研修サービス、中小企業の現場DX成功例など、課題解決に向けた具体的なアクションやソリューションも数多く現れています。政府・大企業からベンチャー企業、そして現場レベルに至るまで、DXの波は幅広い層で起こっており、中小企業経営者にとって示唆に富む内容ばかりです。
共通して言えるのは、DXはもはや一部の大企業だけの取り組みではなく、あらゆる業界・規模の企業にとって避けて通れない経営課題になっているということです。重要なのは、それぞれのニュースから自社に活かせるポイントを見出し、具体的な行動につなげることです。例えば、自社のDX目的を見直して顧客価値創出に軸足を置く、レガシーシステムの更新計画を立てる、地域の人材育成施策にアンテナを張り将来の採用戦略に組み込む、手軽な研修サービスで社員のデジタル知識を底上げする、現場の紙業務を一つデジタル化してみる——できることから一歩踏み出すことが肝心です。最新情報にキャッチアップしながら、俊敏かつ柔軟にDXの取り組みを深化させていくことで、貴社の競争力強化と持続的成長につなげていきましょう。