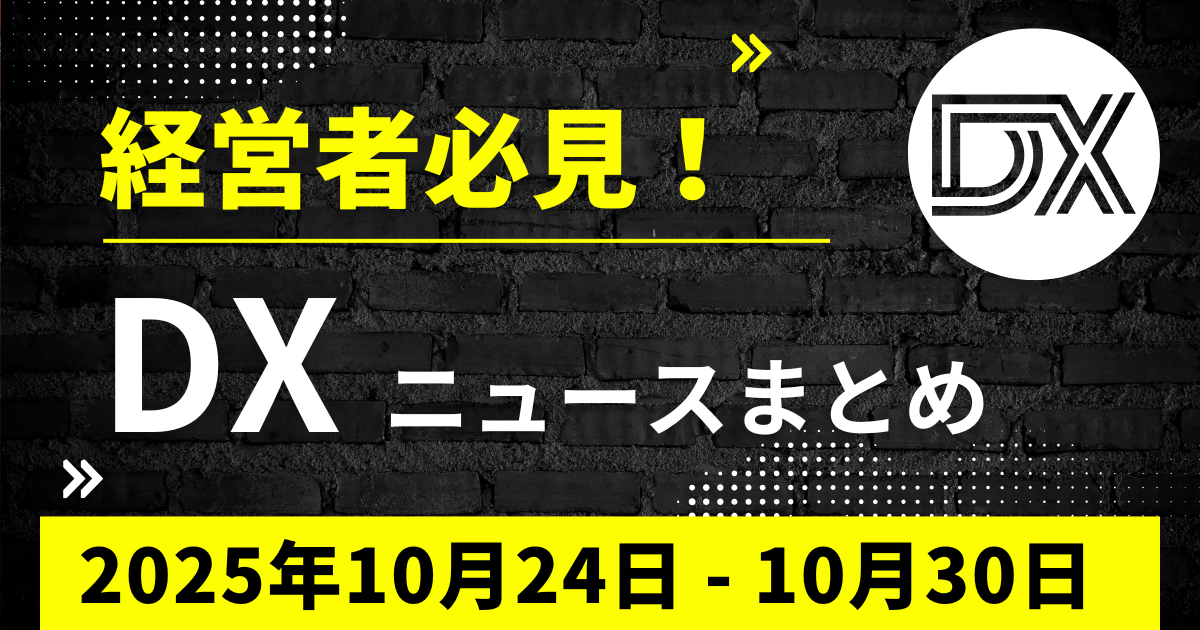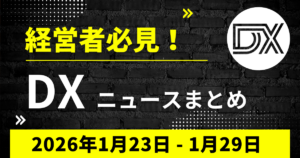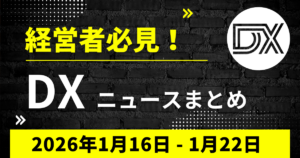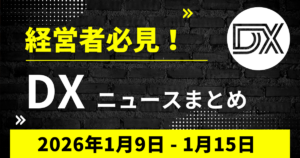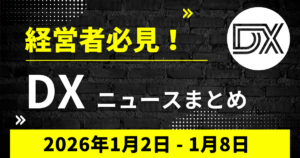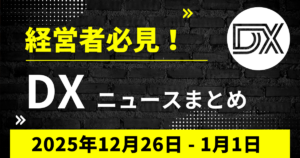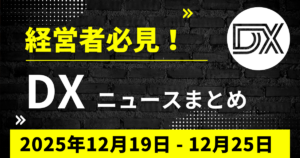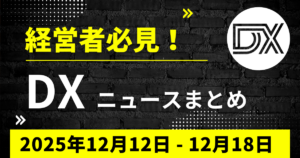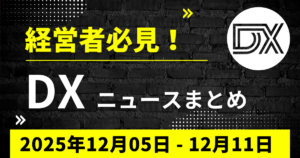DXニュースまとめ(2025年10月24日〜10月30日)
生成AIやAIエージェントだけでなく、行政・店舗・製造の現場で「実装フェーズ」のDXが広がっています。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、①自治体DXをテーマにした展示会の開催、②国内データに対応したクラウドの整備、③小売現場でのAIグラス実証、④省力化投資補助金のスケジュール更新、⑤自治体窓口DXSaaSの提供事業者募集の開始、の5つです。これらはいずれも2025年10月24日〜10月30日に国内で公表された動きで、官公庁と大企業が次の年度に向けた方針を固めつつあることを示しています。自社のDXを進める際の材料としてチェックしてみてください。
1. 大阪で「自治体デジタル化 支援EXPO」開幕、官民のDXを一体で推進(10月30日)
概要
10月30日、インテックス大阪で「自治体デジタル化 支援EXPO」を含む第5回デジタル化・DX推進展(ODEX)大阪会場が開幕しました。自治体の窓口業務オンライン化、職員の働き方改革、文書管理のクラウド化、生成AIを使った問い合わせ対応など、公共分野のDXに特化した展示が一堂に並びました。出展は約80社で、来場対象には自治体だけでなく地域の中小企業、建設・不動産・製造などの事業者も含まれ、官民連携でのDX加速を打ち出しています。
中小企業への影響
中小企業にとっては、自治体レベルで求められているセキュリティ基準や業務標準に直接触れられる場です。これらを理解しておけば、自治体と取引する際はもちろん、大手企業へのサプライチェーンとして製品やサービスを納入する場合にも説得力を持った提案ができます。加えて、自治体需要は景気変動の影響を受けにくいため、定期的に開催される展示会で商談リストを作っておくことは、受注の平準化にもつながります。また、展示会場で紹介されるAI・RPA・ワークフローの多くはサブスク型で初期投資が小さく、IT人材が不足する企業でも短期間で導入しやすいというメリットがあります。
経営者の視点
自治体や大手企業のDXテーマは地方の民間企業にも波及します。経営者としては、展示会で示されたキーワード――窓口DX、人材不足対応、AIチャットボット、文書電子化、セキュリティ統制――を自社の製品・サービス・業務にどこまで適用できるかを早急に検討してください。さらに、自治体の年度予算やデジタル庁の方針と連動したパッケージを作れば、価格よりも「調達しやすさ」で選ばれる可能性が高まります。自治体・地域企業の課題を並べて整理し、共同で提案できるパートナー企業をあらかじめ決めておくと案件獲得につながります。今回参加できなかった場合でも、主催者が公開するレポートや登壇企業の資料を確認し、自社の提案書テンプレートを最新化しておくと次の商談で差が付きます。
参考リンク
2. 富士通とPwC Japan、ソブリンクラウドで経済安保対応を強化(10月29日)
概要
10月29日、富士通とPwC Japanは、富士通が提供するソブリンクラウド「Fujitsu クラウドサービス powered by Oracle Alloy」の信頼性向上と市場浸透を目的に、経済安全保障対応で協業すると発表しました。重要インフラ向けに求められる法制度への対応を整理したリファレンスガイドを2025年12月に公開し、自治体や医療、製造など機密性の高い分野が安全にクラウドを使えるようにする計画です。日本国内のデータ主権を重視したクラウドでDXを進めたい組織にとって大きな選択肢になります。
中小企業への影響
一見すると大企業・官公庁向けの取り組みに見えますが、サプライチェーンの一部を担う中小企業にも波及します。取引先が「国内で閉じたクラウドでデータを授受したい」と求めてきた場合に、このような国産クラウドに対応していることが取引継続の条件になる可能性があります。また、ガイドラインが公開されれば、セキュリティ要件やログ取得の方法、バックアップの考え方などが明確になるため、自社の情報システムをどう設計すべきかを安価に学べます。SIerやITベンダーとしては、このガイドに沿ったパッケージを早く用意しておくことで、公共系・インフラ系の案件に参加しやすくなります。
経営者の視点
今後、機密性の高い図面・顧客データ・本人確認データを扱う企業は「どの国のクラウドに置くか」を取引先から問われるようになります。経営者は、取引先の業界がどの制度に該当するのかを早めに把握し、自社のクラウド利用方針を文章化しておきましょう。あわせて、国内クラウドに対応したSaaSやゼロトラスト環境を提供できるSIerと連携すれば、顧客に対して「安心してDXを進められる体制がある」と訴求できます。さらに、顧客の中には「生成AIを使いたいが海外リージョンは使えない」という企業も出てきます。こうした層に向けて、国内クラウド上で動くAIやデータ分析のメニューを一緒に提示できれば、単価の高いDX案件に広げられます。価格だけでなく、データ所在地やガイドライン準拠を競合との差別化要素にする発想が重要です。自社のプライバシーポリシーや情報管理規程もこのタイミングで見直し、クラウド事業者の名称や保存場所を明記しておくと、取引先からのチェック対応がスムーズになります。
参考リンク
3. KDDIとローソン、AIグラスで店舗業務を可視化する実証を開始(10月28日)
概要
10月28日、KDDIはローソンと連携し、AIグラスを使って店舗業務を撮影・可視化し、作業手順をその場でAIが支援する実証実験を開始しました。従業員がグラス型デバイスを装着して棚出しや調理を行うと、映像がクラウド上で分析され、作業時間や手順のばらつきが自動で記録されます。マニュアルをAIに読み込ませておけば、音声や画面表示で次の手順を教えてくれるため、経験の浅いスタッフでも同じ品質で作業できるようにする狙いです。実証は12月26日まで全国のローソン店舗で行われ、作業者の身体的負荷や使い勝手もあわせて検証し、量産化に向けた改善点を洗い出します。
中小企業への影響
小売・サービス業では人手不足が深刻で、教育にかける時間が取れないことが現場DXの大きな課題です。今回のように「作業を動画で集めてAIが分析する」仕組みが実用化されれば、飲食店や宿泊業、物流センターなどでも少人数で安定したサービスを提供しやすくなります。さらに、作業動画から自社固有のノウハウを抽出しておけば、将来的に多店舗展開する際の教育コストも減らせます。一方で、従業員のプライバシー保護やカメラ設置に関する説明が不十分だと内部反発を招くため、ルール整備もセットで進める必要があります。また、動画を扱うと通信量が増えるため、5Gやローカル5G、Wi-Fiの整備コストも見込んでおくと、後から「ネットが遅くて使えない」という失敗を避けられます。
経営者の視点
この実証が示しているのは、「AIを先に入れる」のではなく「現場データを動画で取る」ことがDXの第一歩という点です。経営者は、自社で動画を安全に保存・分析できる環境を用意し、どの業務をどの順番で自動化するかをロードマップにしておきましょう。特に加盟店ビジネスやフランチャイズを展開している企業は、標準作業をAIでチェックできるようにすれば、指導のばらつきが減り、ブランド価値の維持にもつながります。機器の価格がこなれてきたら、まずは社内の研修・点検業務から試すのが現実的です。社内に動画編集のスキルがない場合は、撮影・タグ付け・AI学習をまとめて請け負う外部パートナーを選定しておくと導入が一気に進みます。店舗や工場など複数拠点を持つ企業は、1拠点だけで終わらず、評価指標・教育動画・FAQを共通化して横展開できるように設計しておきましょう。
参考リンク
KDDI:AIグラスを活用した業務効率化実証をローソン店舗で開始
4. 中小企業省力化投資補助金、年度後半の公募スケジュールを公表(10月28日)
概要
10月28日、中小企業基盤整備機構が運営する「中小企業省力化投資補助事業(一般型)」で、第4回公募の申請スケジュールが公開されました。生産性向上に資するロボット、IoT、AIカメラ、クラウド型業務システムなどの導入費用が補助対象となり、慢性的な人手不足に悩む中小企業がデジタル技術で業務を自動化できるよう後押しします。すでに2025年度の早い段階で第1回・第2回の採択結果が出ており、今回の更新で年度後半の資金計画が立てやすくなりました。
中小企業への影響
この補助金の特徴は、あらかじめ登録された「カタログ製品」を選べば要件確認がスムーズで、短期間で導入できる点です。例えば、勤怠・給与・請求を一体管理できるクラウドや、製造現場の稼働状況を可視化するIoTツール、店舗の防犯と業務記録を兼ねるAIカメラなど、DXに直結する設備が多数掲載されています。ITベンダー側にとっても、自社製品がカタログに登録されれば提案の手間が大きく減り、価格を下げずに販売できるので、顧客とのWin-WinなDX投資を実現しやすくなります。第4回の公募時期が分かったことで、企業は他の補助金(ものづくり補助金、事業再構築など)との併用を検討しやすくなり、投資の時期を「支援制度に合わせる」ことが可能になります。特に、年度末に駆け込みで設備を入れると教育や社内調整が追いつかず失敗しがちですが、スケジュールが見えたことで秋以降にテスト導入→本導入という二段階の進め方を取りやすくなります。
経営者の視点
補助金は「採択されたら考える」ではなく、事業計画と一体で動かすと効果が高まります。経営者は、24時間稼働が必要な工程や、属人化している事務処理、紙で残っている申請業務を洗い出し、どの部分をカタログ製品で置き換えられるかを先に決めておきましょう。さらに、補助金で導入したシステムを使いこなすには従業員教育も必要になるため、マニュアルやeラーニングを同時に整備し、導入後3か月以内に効果測定を行う仕組みを用意しておくと投資が無駄になりません。申請書作成を外部に任せる場合も、自社のDXの方向性だけは経営層が明確に伝えることが重要です。採択後の報告や現地確認に対応できる体制もあわせて決めておけば、急な修正依頼にも落ち着いて対応できます。
参考リンク
5. デジタル庁、ガバメントクラウドで「自治体窓口DXSaaS」提供事業者を募集開始(10月24日)
概要
10月24日、デジタル庁は令和8年度のガバメントクラウドで自治体に提供する「自治体窓口DXSaaS」の提供・準備事業者の募集を開始しました。住民票や各種証明書の交付、子育て・福祉の申請など、住民が窓口で行う手続きをクラウド上で共通化し、自治体ごとに個別開発していた業務システムを標準化するのが目的です。これにより、自治体は自前で大規模なサーバーを持たなくても最新のSaaSを使えるようになり、セキュリティアップデートや機能追加が一括で行える体制が整います。
中小企業への影響
自治体向けのIT市場は大手ベンダーが中心でしたが、ガバメントクラウドで標準的なSaaSが採用されれば、中小のIT事業者でも一部機能や周辺サービスを提供しやすくなります。例えば、住民に対するチャットボットやAIによる問い合わせ対応、各種証明書のオンライン決済、マイナンバーカードとの連携といった周辺機能は、地域の実情に合わせて地場企業が担う余地があります。また、自治体職員の業務がクラウドで統一されれば、紙のやり取りや出張が減り、地元企業との手続きもスムーズになります。自治体との取引で課題になりがちな「担当者異動のたびに説明が必要」という手間も、業務が共通化されることで減少し、長期にわたる保守サービスを提供しやすくなります。
経営者の視点
自治体を顧客に持つ、もしくはこれから参入したい企業は、今回の募集要項を早めに確認し、自社のサービスをどのレイヤーに位置づけるかを決めておくべきです。特に中小企業の場合、すべてを自社で作るよりも、標準SaaSとAPI連携する形でニッチな機能を提供した方が開発コストを抑えられます。自治体の予算編成スケジュールを考えると、2026年以降に市場が一段と広がる見込みなので、今のうちに実績となる小さな案件を作り、導入後の運用サポート体制を整えておくと継続受注につながります。住民向けサービスを開発している企業にとっても、行政手続きのデジタル化が一気に進む好機です。逆に言えば、行政側の標準仕様に合わせられないサービスは早い段階で選択肢から外される可能性があるため、仕様変更への追随力を経営課題として捉えておくことが求められます。自治体のDX需要は地域振興や観光とも密接に関わるため、地場産業向けのアプリやデータ連携サービスを持つ企業は積極的に連携先を探しておくとよいでしょう。
参考リンク
まとめ
今回取り上げた5つの動きは、どれも「来年度に備えたDXの土台づくり」という点でつながっています。展示会で最新ソリューションを知り、補助金で投資のタイミングを整え、自治体や大企業が求めるクラウド要件に合わせておくことで、2026年度以降の案件をスムーズに獲得できます。まずは自社の業務でクラウド化・動画活用・API連携のどれが遅れているかを棚卸しし、使えそうな展示会や公募情報には必ずエントリーしてみてください。小さな実証でも実績として語れるようになれば、顧客からの信頼が高まり、DX関連の相談が集まりやすくなります。