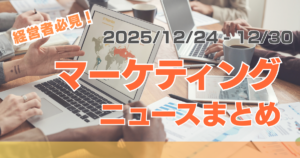マーケティングニュースまとめ(2025年10月22日〜10月28日)
生成AIや匿名化データの活用が当たり前になる中、広告の可視化・統合運用・コンテンツ運用の再現性がキーワードとして浮かび上がりました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、広告経路の可視化「AaaS with TTD」、若年層のポイ活加速、LOWYAのSNS動画運用、DNP×StackAdaptの統合プラットフォーム、ShopifyのAI導入意向92%です。限られた予算で“効く配分”を作り、運用を仕組み化するヒントを解説します。
1. 広告の“仕入れ”を見える化――博報堂×The Trade DeskのSPO
概要
博報堂とThe Trade Deskが、広告配信の経路(サプライパス)を可視化・最適化する新サービス「AaaS with TTD」を発表しました。媒体社やSSPを経由して配信されるまでの手数料や重複在庫、無駄な仲介を分析し、広告主側の効率改善と品質向上を狙う取り組みです。第三者データやブランドセーフティの観点も織り込み、成果指標(CPA/ROASなど)と直接結び付けて配信経路を選べるのが特徴とされています。近年重視されるSPO(サプライパス最適化)を国内で本格運用する文脈で、可視性と検証プロセスを一体化した点に新規性があります。
さらに、運用現場の負担軽減も見逃せません。経路が可視化されることで、入札やブロックリスト運用が勘と経験に依存しにくくなり、意思決定がデータドリブンに変わります。無駄な仲介を外せば、クリエイティブや検証予算に振り向けられる比率も高まります。SPOは一度やって終わりではなく、市場側の変化に合わせた継続的な棚卸しが必要です。ベンダー任せにせず、社内で最低限の理解を持つことが成功の条件になります。また、経路の透明性は“媒体品質の健全化”にも寄与します。広告主が選別眼を持つほど、不透明な在庫は自然と淘汰され、結果として市場全体の品質が底上げされます。自社だけでなくエコシステム全体の改善に参加する姿勢は、長期的な調達コスト低減にもつながります。
中小企業への影響
限られた広告費で成果を最大化したい中小企業にとって、仲介コストの見える化は純粋なメディア費の増加につながります。同じ予算でも質の高いインプレッションを買える可能性が高まり、無効トラフィックや重複配信の抑制にも寄与します。代理店を活用する場合でも「どの経路で配信され、どんな手数料が発生しているか」を問い、SPOの観点でKPIとの因果を確認する姿勢が重要です。可視化レポートは仕入管理に近い発想で、広告を“原価管理”する文化づくりを後押しします。
経営者の視点
まずは自社の主要ターゲットに効く媒体・面を仮説化し、配信経路の違いで実効CPAがどう変わるかを検証しましょう。シンプルに「媒体別×経路別」の二次元で比較し、①在庫の質、②手数料、③ブランドセーフティ、④リーチの広がりの4観点で評価表を作ると意思決定が早まります。少額でもよいので検証用予算を確保し、運用パートナーと“見える化→改善”のサイクルを定例化することが、費用対効果の継続的改善に直結します。
参考リンク
MarkeZine:博報堂とThe Trade Desk、「AaaS with TTD」提供 最適な広告パスを可視化
2. 若年層で“実質値引き”が効く――10・20代の65%がポイ活を強化
概要
広告視聴環境の物価高の中、10・20代の65%がポイント獲得(いわゆる「ポイ活」)をこれまで以上に意識しているという調査結果が公表されました。日常の決済やECでポイント還元を重視する動きが強まり、特に楽天とPayPayの二極が若年層で優勢という構図です。クーポンやスタンプなどのライトなインセンティブも購買行動の後押しに機能しており、値上げ局面での“実質的な値引き”として選好が高まっています。ポイント発行の可視化が進み、ユーザーの情報感度が高いことも行動変容の背景にあります。
中小企業への影響
若年層への販売では、価格訴求だけでなく「還元体験の設計」が成果を左右します。大手のエコシステムと連携せずに独自ポイントだけで勝負すると認知・利用頻度の壁が高い一方、楽天やPayPayの連携特典、決済シナリオに寄り添うクーポン配布などは費用対効果を作りやすい打ち手です。併せて、獲得・利用履歴をLTV分析に回し、ポイント原価を“再来店・追加購入”で回収できているかを必ず点検しましょう。一方で、過度なポイント依存は粗利を圧迫します。短期販促とファン化のバランスを取るために、値引きではなく“体験価値”と結び付いた還元(来店体験、コミュニティ参加、レビュー投稿など)に振るのが得策です。還元財源は販促費だけでなく、配送効率化や仕入最適化で捻出する全社的な設計にすると持続可能性が高まります。
経営者の視点
短期の来店・CV増だけでなく、1回あたりのポイント原価を「90日LTV」や「チャーン率の改善」で必ず相殺できているかを確認してください。KPIは①還元施策によるCVR上昇、②初回購入後の2回目転換率、③ポイント失効率の3つを必須に。若年層向けには、SNS上での“貯まる・使える体験”の可視化(例:会計前の残高提示や友だち紹介ボーナス)をクリエイティブに落とし込み、告知だけで終わらせない運用を徹底しましょう。実店舗を持つ事業者は、オンライン還元とオフライン体験を連動させると効果が高まります。例として、来店時のアプリチェックインで“即時に使える小額特典”を付与し、精算時に体験価値を実感してもらう仕掛けは満足度を押し上げます。データ連携が難しい場合でも、簡易なクーポンコード運用やレシート応募で十分に検証できます。
参考リンク
MarkeZine:物価高で10・20代の65%がポイ活を「より意識」 楽天・PayPayが2強〖Skyfall調査〗
3. LOWYAに学ぶ“企画勝ち”動画の作り方――SNSで3,000万再生
概要
家具・インテリアのD2Cブランド「LOWYA」が、SNS動画でフォロワー120万人以上/累計3,000万回超の再生を生む運用術を紹介しました。短尺動画で“部屋の悩み→解決まで”を一気通貫で見せるストーリーテリング、コメントへの即応、ユーザー投稿の二次活用など、プラットフォームの文脈に最適化した制作・運用が鍵とされています。商品訴求を前面に出し過ぎず「見て得する情報」から入る編集で、自然な導線でECへ遷移させるのが成功要因です。
中小企業への影響
広告費をかけずに認知と信頼を獲得するうえで、教育的・実用的なコンテンツの定常発信は強力です。撮影機材やスタジオに投資しなくても、スマホ×自然光×簡易マイクで十分に“見られる品質”を担保できます。重要なのは、①1テーマ1メッセージ、②投稿後24時間のコメント返答率、③保存・共有率とEC遷移の関係の3点を運用KPIとして握ることです。失敗作は“学び”としてアーカイブし、勝ち筋の型化を進めましょう。また、プラットフォームごとの“勝ち尺”と冒頭3秒の掴みを設計することが離脱を防ぎます。撮影は縦型を基本にしつつ、キャプションは字幕で冗長説明を避けるのが鉄則です。社員やユーザーを“出演者”に巻き込み、リアルな生活導線の中で使い方を見せると共感が生まれます。コンテンツは資産です。広告出稿時にトップパフォーマー動画をクリエイティブルールとして再活用し、CPAの平準化を図りましょう。さらに、UGC(ユーザー生成コンテンツ)との掛け合わせで“第三者の声”を増やすと信頼が高まります。レビューやビフォーアフター写真の二次利用許諾を取り、ブランド側の投稿と交互に配置すると、売り込み感を薄めながら説得力を高められます。KPIは再生数だけでなく“保存・共有→サイト回遊→カート投入”の一連の行動連鎖で測る設計にすると、売上寄与が可視化できます。
経営者の視点
月4~8本の“企画勝ち”動画を作るために、ネタの発掘→台本→撮影→編集→配信→分析のワークフローを標準化してください。現場任せにせず、経営が「勝ちパターンの定義」を持ち、ダッシュボードで可視化することが再現性につながります。EC側では、動画視聴後のランディングを“動画の続き”として設計し、視聴コンテキストを途切れさせない導線(スクロール1回でカート到達など)を意識しましょう。
参考リンク
MarkeZine:フォロワー120万人越え、3000万回以上の再生を生み出す「LOWYA」のSNS動画活用術
4. 配信と計測を1つに――DNP×StackAdaptのマルチチャネル統合
概要
大日本印刷(DNP)がStackAdaptと協業し、ディスプレイ・動画・音声・CTVなど複数チャネルを横断して一元管理できる広告プラットフォームの提供を開始しました。企画から配信、効果計測までを統合し、オーディエンスの行動データを基にチャネル間の最適配分を行う狙いです。国内市場でもリテールメディアやCTVの台頭で媒体が細分化する中、単一の運用基盤で“同一ユーザーへの重複接触抑制”や“到達計測の統一”を図れる価値は大きいと言えます。
中小企業への影響
チャネルが増えるほど、個別最適での“ムダ打ち”が増えます。中小企業こそ配信と計測の基盤を一本化し、チャネル横断のフリークエンシー管理を徹底しましょう。DNPのような統合型プラットフォームを活用すれば、少額予算でも「最小限の接触回数で認知と態度変容を両立」させやすくなります。オーディエンスの重複を可視化し、費用をCV貢献の高い面に寄せる運用が、限られた予算のレバレッジを最大化します。運用面では、媒体ごとの最適化ロジックの違いを吸収できる点もメリットです。複数代理店やツールを跨いでいる場合は、指標定義のズレが意思決定を遅らせますが、統一ダッシュボードで“同じ物差し”に揃えることでスピードが上がります。中長期では、ファーストパーティデータ連携による効果計測の高度化(購買データ・会員データとの閉ループ)が力を発揮します。小さく始め、勝ち筋のみを拡大する“漸進型の全体最適”を心掛けましょう。一方で、統合の名の下に“やることを増やす”のは本末転倒です。配信先は明確な仮説に基づく少数精鋭から始め、テストで勝ったチャネルにのみ投資を拡大するルールを徹底します。成果が見えない場合は、KPIの置き方(短期CV偏重)やクリエイティブの共通言語不足を疑い、基盤ではなく運用プロセスを見直すのが近道です。
経営者の視点
まずは“チャネル別KPIと役割”を明文化し、配信前に「到達」「想起」「指名検索」「CV」のKGI連関を描いてください。計測はUTMだけでなく、ブランドリフトや検索リフトなどのアッパーファネル指標も併用し、週次で媒体配分を見直す体制を。少数プロダクトなら、広告・LP・CRMのクリエイティブとメッセージを統一して“同じ顔で接触する”ことが成果を押し上げます。
参考リンク
MarkeZine:DNP、StackAdaptと協業しマルチチャネル統合型広告プラットフォーム提供開始
5. 日本のAI導入意欲は世界トップ――Shopify調査「92%」
概要
Shopifyが公表したAI活用実態調査で、日本の事業者のAI導入意向が92%と世界トップだったことが示されました。生成AIやAIエージェントによる接客、在庫・需要予測、広告自動化などの領域で活用期待が高まり、特にECや小売での“運用負荷の軽減”と“顧客体験の平準化”が主要テーマです。国内では人手不足や生産性向上の要請が強く、AI活用が実務のボトルネックを解消する現実的な手段として認識されつつあります。
中小企業への影響
AIは「現場に一人分の手」を増やす感覚で導入すると成果が出やすいです。CSの一次応対やFAQ生成、広告文・商品説明の自動生成、検索連動の入札最適化など、費用対効果が見えやすい領域から着手しましょう。注意点は“過信しないこと”。誤生成や季節変動の読み違いを防ぐため、AIの出力を人が検証する体制と、学習データの更新サイクルを運用ルールに組み込みます。加えて、検索やレコメンドの“体感速度”を上げるだけでも離脱率は改善します。社内では、AIに任せる業務と任せない業務を線引きし、ガイドラインと教育をセットで導入してください。中小企業のアドバンテージは意思決定の速さです。短いサイクルで“試す→学ぶ→標準化”を回せば、大企業に負けない俊敏さで成果を出せます。実装後は、成功・失敗事例を“ナレッジカード”化し、社内に横展開しましょう。日々の改善ログが蓄積されるほど、AIの価値は逓増します。小さな一歩を早く踏み出すこと自体が競争力になります。また、現場の抵抗感を減らすには“人が最後に決める”運用にしておくことが重要です。AIが提案した入札やクリエイティブ案をそのまま適用するのではなく、承認フローで責任者が意図のズレを修正できる仕組みにします。ベンダー選定では、学習データの由来と更新方針、サポート体制、将来の料金体系(MAU課金/成果報酬など)も必ず確認してください。試験導入の段階で“撤退条件”も明文化しておくと、投資の健全性を保てます。
経営者の視点
導入前に「時間削減」「売上寄与」「コスト削減」の3本柱でROI仮説を置き、効果検証の設計(A/Bや段階導入)を先に決めてください。SaaSの選定では、①既存EC・広告・在庫のデータ連携、②ログの可視化、③セキュリティ・権限管理の3点を必須要件に。属人化しがちな運用作業をAIで標準化することで、人の創造的業務への時間配分を増やすことができます。
参考リンク
MarkeZine:Shopify、2025年の事業者AI活用実態調査を発表 日本の事業者の導入意向は92%で世界トップ
まとめ
今回のポイントは「見える化」「仕組み化」「再現性」です。
- 広告経路の可視化と統合運用で、同じ予算でも“効く配分”を作れるようになりました。
- 若年層には“実質値引き”の体験設計が効き、SNS動画は“企画勝ち”の型化で再現性が高まります。
- AIは“小さく早く試す→学びを標準化”で、人的リソース不足を補う現実解になります。
中小企業の経営者は、①可視化レポートの定例化、②LTVでの販促費回収チェック、③動画と広告の一体運用、④AI導入のROI設計という4点に着手してください。次回も、予算効率と成長確度を同時に高める実践トレンドをお届けします。