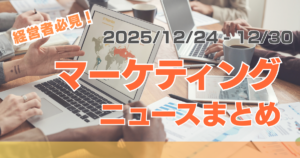マーケティングニュースまとめ(2025年10月15日〜10月21日)
マーケティング分野では、紙媒体の体験設計からリテールメディアの統合、ファンコミュニティ運用、コピー表現の最適化、OOHの効果測定まで、実務に直結する発表が相次ぎました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは「新聞広告の日」統一PR、「Shufoo!ブランド」統合、コミューンの新サービス、LINEリサーチの広告コピー調査、アナログOOHの可視化です。紙×デジタルの連携強化と“測定できる販促”が共通テーマで、少額からでも再現性を高めやすくなっています。この記事では、経営判断に活かせる要点と実装のヒントを簡潔に解説します。
1. 新聞協会が「ほぼじっすん、しんぶん。」統一PRを開始
概要
日本新聞協会は10月20日の「新聞広告の日」に合わせ、10月15日から18日にかけて全国46紙で“ほぼ実寸大”のビジュアルを誌面に展開し、二次元コードで特設サイトの“答え合わせ”に誘導する統一PRキャンペーンを始めました。アンバサダーにはモデルのゆうちゃみさんを起用し、TikTokやYouTubeでも動画を公開。紙面のサイズ感という体験価値をフックに、若年層への認知・興味喚起を狙う取り組みです。地域の名物や建造物を題材に、紙ならではの迫力と“見比べ体験”を組み合わせています。
中小企業への影響
紙×デジタルのハイブリッド活用は、地域商材や体験型サービスの訴求に相性が良いです。例えば、弁当箱・家具・工具・制服など“サイズで伝わる”商品の魅力は、実寸イメージの紙面とQR遷移先の短尺動画/レビューで補完できます。QR流入やクーポン利用で測定可能になり、紙媒体の投資対効果が可視化しやすくなります。特に地方紙の読者基盤とSNS広告の地理ターゲティングを掛け合わせれば、商圏内での到達と来店促進の両立が期待できます。観光・道の駅・直売所など“現地体験”の多い業態では、地場の話題化にも寄与します。
経営者の視点
①“実寸で驚き→QRで行動”の二段設計を基本に、遷移先で「限定特典」「来店予約」「LINE友だち追加」を置く。②KPIはQR流入数、CVR、来店計測(POS・会員ID・予約件数)を紐づけ、紙面ごとに比較。③クリエイティブは“サイズ感+用途シーン+価格/特典”を短い文で。④媒体は地元紙の1段・全段など枠を選び、SNSはエリア×興味関心で少額からテスト。⑤誌面校了前に計測用URL・UTM・QRの動作確認、販売現場の受け入れ体制(在庫・予約導線)まで点検。景表法・ステマ規制に留意し、広告表示の明確化と素材の実測・根拠管理を徹底しましょう。さらに、若年層向けの訴求では“出演者本人のSNS発信”や参加型のハッシュタグ施策を合わせると露出が累積し、UGCの自然増につながります。紙面の制作過程や撮影の裏側を短尺で見せると、広告の“熱量”が伝わりやすく、来店・購入の後押しになります。配布エリアは商圏と連動させ、QR遷移先のLPも地域別に文言と特典を出し分けると、同じ出稿量でも回収効率が上がります。制作・入稿の標準手順(UTM・QR・法的表示のチェックリスト)を整備しておくと、次回以降の工数も削減できます。
参考リンク
AdverTimes:新聞紙で“ほぼ実寸”を体感 ゆうちゃみが伝える『新聞広告の日』
2. ONE COMPATHがリテール向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統合
概要
電子チラシ「Shufoo!」を展開するONE COMPATHは、リテール向け6サービス(例:Shufoo! AI、LocalONE、来店分析の「ビジットトラッキング」など)を「Shufoo!ブランド」に統一すると発表しました。月間利用者は約1,600万人、参加店舗は12万店超。企画立案から配信、来店・購買データによる効果測定までを一貫で支援し、オムニチャネル時代の販促を“分断なく使える”形に整理する狙いです。カラーやブランド表現も統一し、意思決定者に分かりやすい提案構造に改めます。
中小企業への影響
電子チラシは依然として高い到達力を持ちますが、単発の掲載ではLTV最大化に結びつきにくいのが実情です。統合により、①商圏別のチラシ出し分け、②ID/会員と連動した来店・購買分析、③広告運用やレシートキャンペーンとの連携がしやすくなります。結果として、値引き依存から「指名買い・定期買い」を増やす運用に転換しやすくなります。スーパー、ドラッグ、家電量販のほか、専門店・飲食でも“来店前情報×来店後データ”の循環設計が現実的になります。統合の実務面では、商品マスタや価格・在庫の更新頻度をチラシ配信と同期させることが鍵です。媒体ごとの画像サイズや表記ルールを“テンプレート化”し、価格・特典の表現は景表法の根拠台帳と結びつけて属人化を防ぎます。
経営者の視点
まずは“最小構成”で検証を。①電子チラシ+店舗ID発行(LINE会員でも可)+簡易レシート連携の3点を回し、KPIは来店率、会員登録率、クーポン使用率。②成果が見えたら、商圏セグメント配信と在庫連動、レシート応募の景品設計まで広げます。③チラシ制作の体制は、写真の共通化と価格表現の標準ルールで工数を圧縮。④意思決定は「前週比の来店・粗利・在庫回転で判定」など簡潔な経営ダッシュボードに落とす。現場で回る運用に落とし込むほど、広告費の再現性が上がります。さらに、ID連携で得た購買履歴から“頻度高・粗利高”の商品群を特定し、クーポンやレコメンドを優先配分すると、同じ広告費でも粗利の伸びが変わります。オムニチャネルの最適化は、集客の山をつくる“特売”と、間を埋める“定番”の配分設計から始めるのがおすすめです。小商圏の単店運用でも、配布→来店→購買までの“ひとつの指標列”を毎週更新するだけで、施策会議が意思決定中心に変わり、少人数チームの生産性が上がります。
参考リンク
MarkeZine:ONE COMPATH、リテール向け6サービスを『Shufoo!ブランド』に統合
3. コミューンが「CLG Partners」を正式提供
概要
企業コミュニティ支援のコミューンは、10月15日にファンとの信頼を事業成長の原動力に変えるフルファネル型サービス「Customer-Led Growth Partners(CLG Partners)」の提供を開始しました。コミュニティの調査・戦略策定から運営、プロモーション、商品共創、効果可視化までを一気通貫で支援。ロイヤルユーザーの声と行動データを、商品開発や広告、CRMまでつなげる設計です。地域のファンコミュニティ事例では、投票を起点に新ツアーや宿泊プランの商品化にも踏み込み、収益に直結する動きを強化しています。
中小企業への影響
“フォロワーは多いが売上に効かない”悩みの打開策になり得ます。①クローズドな場でのN1インタビューとβテスト、②アンバサダー制度、③UGCの収集と二次利用、④ファンデータのスコアリングとリターゲティング――を一連で回すことで、広告依存を下げつつLTVを伸ばせます。顧客の声が商品改良や販促メッセージに直結するため、訴求の“的外れ”が減り、制作コストの無駄も抑えられます。運用設計の肝は“参加のハードルを下げる”ことです。初期は閲覧・投票だけでもOKにし、慣れたらレビュー投稿やライブ配信への参加を促します。
経営者の視点
スタート時は“小さく濃く”。既存の上位顧客50~200人をLINEオープンチャットやDiscordに招待し、月1回の試作品レビューと限定販売を実施。KPIは参加率、投稿数、レビュー回収率、テスト商品の再購入率、紹介コード経由売上。運用リスク(炎上・コンテンツ枯渇)には行動規範とモデレーション、FAQの整備で先手対応を。現場負荷は週1人日から開始し、成功の型ができたら自社アプリやECの会員基盤に拡張しましょう。コミュニティで得たインサイトは、広告やLPの見出し・FAQにも反映し、支援窓口の負担軽減とCVR向上を同時に狙います。参加特典は金銭以外(先行情報・限定体験・名入れ等)を中心に設計すると、値引き依存を避けられます。さらに、投稿やレビューの二次利用に関する同意と撤回手続き、荒らし対策のポリシー、画像の権利管理を明文化して、安心して参加できる場づくりを徹底しましょう。成果共有は月次で“学びの要約”を全社に配信し、商品開発・販促・CSが同じ前提で議論できるようにするだけでも、打ち手の質が一段上がります。
参考リンク
Web担当者Forum:コミューンが顧客との信頼構築で事業を拡大するサービス『CLG Partners』を正式提供
4. LINEリサーチ:購買意欲を高めるのは「割引率の明示」
概要
LINEヤフーは、全国15~69歳の男女3,152人を対象に広告コピーの印象を調査。もっとも「買いたくなる」表現は「〇〇%オフ/〇〇円引き」で5割強が支持し、次いで「送料無料」「期間限定価格」。一方で「有名人も使っている!」は6割強が“買いたくない(怪しい)”と回答し、年齢層にかかわらず警戒感が強いことが示されました。キャンペーン訴求では、金額の明確さや具体的なベネフィットが重視され、曖昧な権威付けは逆効果という結果です。
中小企業への影響
限られた制作費でも成果を上げる“型”が再確認されました。値引き・送料無料・期間限定といった明快な価値を、見出しとファーストビューで即伝えるだけでCVRは伸びやすくなります。逆に、根拠の薄い権威付けや過度な煽り文句は信頼低下と炎上リスクを招きます。SNS広告やLP、店頭POPまで一貫した表現ルールを設ければ、テストのスピードも上がります。注意点として、“割引率の連発”はブランド毀損や常時値引き期待を招きやすい点です。イベント・季節・在庫状況に応じて回数と期間をコントロールし、理由付け(新生活応援、周年祭など)を明示すると納得感が高まります。表記は『税込・条件・上限』を近接表示して誤解を避け、トリック的な小さな注記は避けましょう。
経営者の視点
まずは“チェックリスト運用”を導入しましょう。①価格・割引・特典の“数値”は最上段に配置、②配送や返品など“不安解消情報”は近接表記、③ステマ・景表法に反しない根拠資料を台帳管理、④A/Bテストは「割引率の出し方」「期間の表記」「送料無料の閾値」の3軸から。自社データでは顧客層によって最適解が違うため、週次でテスト→勝ちパターンを基準化→四半期で棚卸し、のサイクルで磨き込みましょう。クリエイティブの制作プロセスでは、ヘッドライン→サブコピー→CTAの3点を最初に言語化し、撮影やデザインは“言葉に沿わせる”順番にすると迷いが減ります。A/Bテストは最長でも2週間、勝ち負けの基準と予算停止条件を事前に決めると、学びが蓄積します。SNSでは配信面ごとのフォント可読性や文字数制限にも注意が必要です。Xは短く強い数値、Instagramはビジュアルとバッジ風の数値、リールは冒頭2秒で“金額と期限”を音声・テロップで伝えるなど、面(メディア)の文法に合わせましょう。店頭では棚帯・レジ前・入口POPで同一コピーを階層配置し、オンライン広告と文言を一致させると、来店後の迷いが減ってCVにつながります。計測はUTM・POS・会員IDをつなぎ、チャンネル別の売上貢献を四半期で棚卸しするのが現実的です。
参考リンク
MarkeZine:『割引率明示』が最も購買意欲を喚起、『有名人使用』は逆効果に【LINEリサーチ】
5. 電通ら4社:アナログOOHにDOOH指標を応用し効果を可視化
概要
LIVE BOARD、NTTドコモ、電通アドギア、電通は、サントリーの出稿事例を対象にアナログの交通・屋外広告(OOH)へデジタルOOH(DOOH)の指標を応用し、インプレッション/リーチ/フリークエンシーを算出する効果測定モデルを公表しました。ドコモの会員基盤データや「モバイル空間統計」「docomo Sense」を活用し、東京主要駅および地方18エリアでアンケート・スコアリングも実施。全国900超の媒体、鉄道180路線以上で広告接触とインパクトを定量化したとしています。
中小企業への影響
これまで“掲出したけど効いたのか不明”となりがちだった駅貼りや屋外ポスターの成果が、人数ベースで説明しやすくなります。Web広告のように到達コスト(CPM)や推定フリークエンシーが見えるため、エリア×期間×サイズの最適化が現実的になります。特に地方都市では、商圏内の駅・道路媒体に限定してもリーチの重複や最適接触回数を設計でき、少額予算のムダ打ちが減ります。実装時は、到達が多いが注意分散しやすい“動線の速い駅”と、滞在が長く読み込みやすい“乗換・終端駅”で役割を分け、コピー量とレイアウトを最適化します。
経営者の視点
①「駅1面×2週間+半径3kmのSNS配信+クーポンLP」で統合KPI(到達人数・LP訪問・来店/購買)を設計し、CPA/ROASで比較。②掲出前に対象駅の推定リーチとフリークエンシーを算出し、最低必要到達人数を逆算。③広告インパクトはクリエイティブのサイズ・設置位置・色数でスコア化し、AB比較で改善。④計測はプライバシー配慮・データ取扱の同意範囲を確認し、社内の個人情報管理ルールと整合。地域集客の再現性が高まれば、恒常的な“月次OOH”という選択肢も視野に入ります。WebやCTVとの重複リーチ管理では、広告識別子の連携や来店計測の重複除去のルールを決め、媒体ごとに“初回接触の役割”と“再想起の役割”を明確にすると、無駄打ちが減ります。B2Bでは展示会前後のOOHで商談化率が上がるケースもあるため、期間前後のアクセスや商談数の相関を見て来年の媒体選定に反映させましょう。創作面では、視認距離に合わせたフォントサイズと色面積、QRを置く場合は周囲の余白とコントラストを確保するのが基本です。なお、屋外でのQRは立ち止まりにくい場所では効果が薄いため、誘導先は“写真保存→後で開く”ができるようにし、URLの短縮表示や記憶しやすいハッシュタグも併記すると取りこぼしが減ります。
参考リンク
MarkeZine:電通ら4社、アナログ交通・屋外広告にDOOH指標を応用し広告効果を可視化
まとめ
今回取り上げた5本は、①体験設計(紙×SNS)、②販促基盤の統合、③ファン起点の成長、④コピー運用の型化、⑤OOHの見える化に集約されます。まず、(1)QRと計測設計を整える、(2)ID連携で来店データを貯める、(3)小さなA/Bテストを回す、の三点から始めましょう。経営の意思決定を“感覚”から“データと仮説”へ。次の施策に使う資源配分を、数値で語れる体制に移行することが、持続的な成長への近道です。