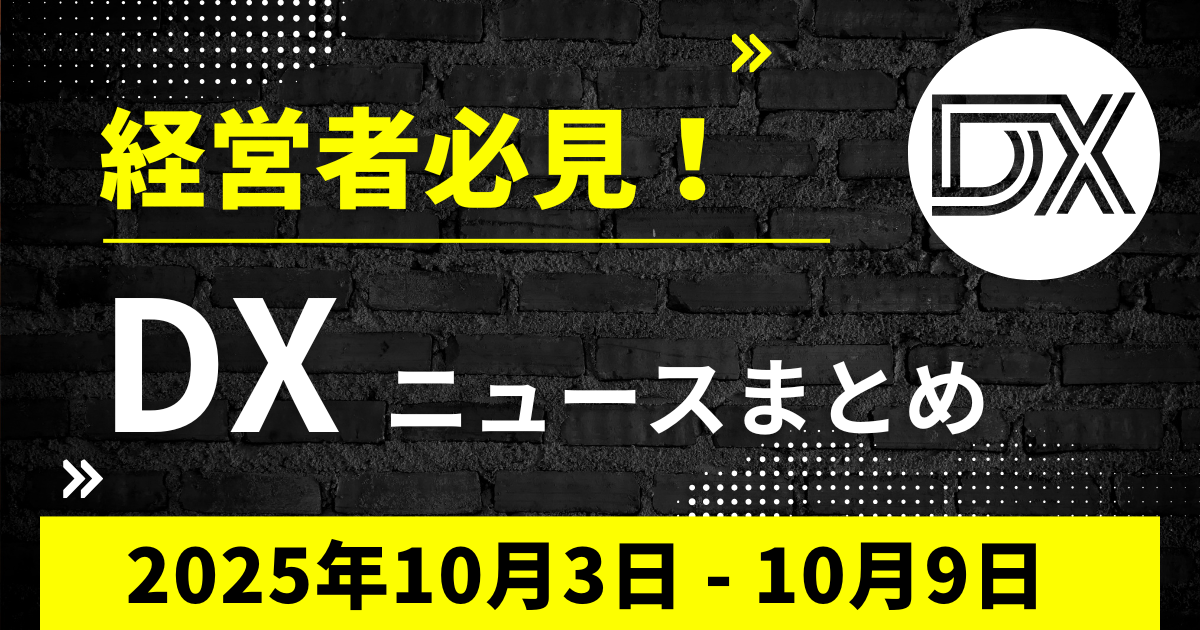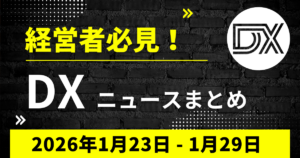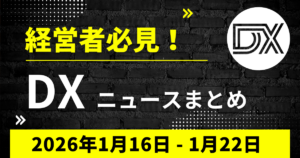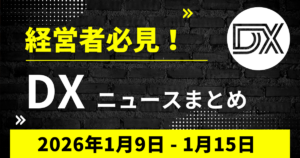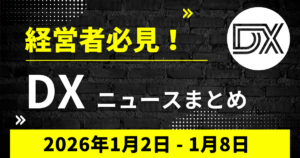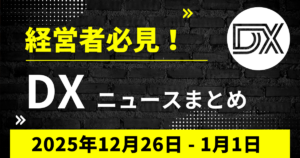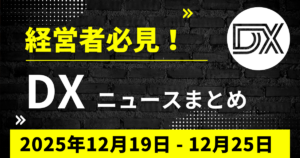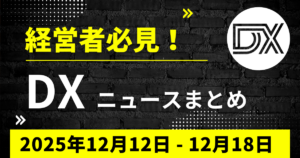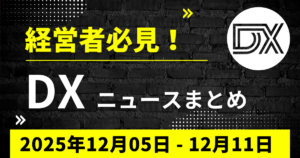DXニュースまとめ(2025年10月3日〜10月9日)
国内のDXでは、製造・物流・公共・日用品の現場で具体的な実装が進みました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、コクヨのBOM/BOP自動生成導入、積水化学のAI予兆保全、ナカノ商会の配車自動化、ライオンの独自LLM始動、国交省の上下水道DX技術カタログ拡充です。いずれも人手不足対策・品質安定・コスト最適化・調達の透明化に直結します。本記事では、それぞれの要点と中小企業への実務的な示唆を、専門用語をかみ砕きながら解説します。
1. コクヨ、BOM/BOPの自動生成で設計〜生産の“待ち時間”を1/10へ──現場知とデータをつなぐ
概要
コクヨは千葉・芝山工場で、受注仕様から必要部材と工程を自動ではき出すBOM/BOP自動生成システムを導入しました。長年の暗黙知をルール化し、個別仕様でも最適な部品表・工程表を作成します。これにより展開作業のリードタイムを最大1/10に短縮。1990年代からの独自ツールに依存していたため生じていた「ブラックボックス化」や属人化の課題を解消し、設計変更の反映速度と品質の両立を狙います。システムは今後、周辺のSCM/ERP/MESとの連携も拡大し、品種増と短納期に同時対応する基盤になります。
加えて、エクサの「SPBOM Suite」を採用し、ルールの登録・改訂を現場主導で回せる運用を志向。生成したBOM/BOPは将来的に購買・在庫・工順へ自動連携し、設計の一貫性を担保する計画です。紙帳票やExcelの置換だけでなく、部品共通化や代替提案の判断材料を可視化できる点も重要です。
中小企業への影響
多品種少量や個別受注の企業にとって、設計〜生産移行のボトルネックを崩せる動きです。ルールベースの自動展開は、ベテラン依存の作業を平準化し、図番・仕様ミスや手戻りを減らします。標準部品の置換、工程負荷の平準化、原価集計の精度向上など副次効果も期待できます。一方で、マスター整備と変更管理が不十分だと誤展開のリスクが増えます。導入前に命名規則や属性定義の棚卸し、承認フローを業務標準として固めることが不可欠です。
経営者の視点
最初から全品種に広げず、高頻度・高負荷・高リスクの領域に絞ってPoCを実施しましょう。効果測定は①展開時間、②変更反映リードタイム、③不具合・手直し率、④見積もり・原価の乖離で定量化。外部製品を選ぶ際はライセンス+内製運用の総コストと、将来の多工場展開に耐える拡張性/データ連携を重視します。現場の熟練者をルール策定の“筆頭著者”に据えると、定着スピードが上がります。
参考リンク
コクヨ、芝山工場にBOMとBOPを自動生成するシステムを導入
2. 積水化学、AI活用CBMで“突発停止ゼロ”に挑戦──重要設備から段階展開
概要
積水化学工業は、アズビルのAI予兆保全プラットフォーム「BiG EYES MM」を導入し、工場設備の振動・温度・電流などのデータから状態をリアルタイム判定する仕組みを構築しました。TBM(時間基準保全)では見抜けない異常の芽をとらえ、余寿命の推定や計画停止の前倒しによって、ラインの突発停止を抑制します。まずは故障影響が大きい回転機器から適用し、効果検証のうえで拠点横展開と高度化を進める方針です。
さらに、既設のPLC/DCSや設備センサーの時系列データと連携し、異常兆候のマルチモーダル解析を実施。解析結果は管理画面で可視化され、遠隔からの一次判断も可能です。設備ごとにしきい値学習を行い、製品切り替え時の挙動差も踏まえてモデルを更新します。これにより、保全計画・部品手配・作業割当のすり合わせが前倒しされ、停止の“痛さ”を小さくできます。
中小企業への影響
「1時間止まるといくら損か」を把握していれば、部分導入でも投資回収は十分に可能です。最初は監視点数を絞り、アラート閾値のチューニングと誤検知対策を重視。設備台帳と点検記録をデータ前処理して取り込むだけでも、傾向監視の質が上がります。熟練保全員の感覚をルールや特徴量に落とし込むことで、世代交代のギャップも縮小できます。一方で、アラート疲れが起きると現場は疲弊します。ダッシュボードの役割分担、通知の優先度、一次切り分けの標準手順を先に定義しましょう。
経営者の視点
KPIは①MTBF/MTTR、②計画停止比率、③部品在庫の滞留/欠品、④OEEの改善幅。効果が見えたら、保全SLAとサプライヤ契約を見直し、予兆→手配→作業までのリードタイム短縮で利益に直結させます。サブスク型の監視SaaSやレンタルセンサーを活用して初期投資を圧縮し、現場教育は「異常データの見本市」を作って学習コストを下げると定着します。
参考リンク
3. ヤマトGのナカノ商会、輸配送計画を自動生成──稼働率30%→50%超で“空気輸送”を削減
概要
ナカノ商会は、シマントと共同で輸配送計画自動生成システム「Auto Dispatch」を開発し、2025年10月1日に運用開始しました。荷主の配送データと物流事業者の空車情報をつなぎ、最適な組み合わせを算出。これにより、トラック稼働率は約30%から50%超へ向上したと公表しています。10万〜20万件規模のデータ処理に対応し、ベテラン配車担当のノウハウ(制約・優先度)をロジック化。ドライバーの拘束時間や回送距離の抑制と、幹線の安定運行を両立します。
また、ドライバーの時間外労働規制強化で注目される“2024年問題”への対応としても、荷待ち・手荷役の見える化や時間窓の厳守に貢献します。ピーク偏在の激しい業態では、ダイナミックプライシングや共同輸送の相手探しにも応用でき、CO2排出と燃料費の同時削減が見込めます。導入前には、地図・道路規制・車格制約など制約データの品質を点検し、ルール化の優先度を合意しておくことが成功の近道です。
中小企業への影響
荷主企業にとっては物流コストの平準化、運送会社にとっては実車率の改善が同時に狙えます。固定案件とスポット案件を同一基盤で割り付ければ、復路の空車を減らせます。課題は、データ提供に伴う取引先間の信頼と、アルゴリズムの“説明可能性”です。割当結果の根拠(積載率・時間窓・待機制約など)を明示できなければ、現場は納得しません。既存のTMS/WMSとAPI連携できるSaaSを選べば、段階導入でも投資効果を出しやすいです。
経営者の視点
自社の平均積載率・回送率・待機時間を定点観測し、閾値ベースのKPIで改善を回しましょう。荷主—運送—倉庫の三者でデータ項目を標準化し、契約書にデータ連携範囲とセキュリティを明文化。運行計画の日次レビュー→週次カイゼン会を継続すると、制度疲労なく根付きます。人手配車とAI配車の二重運用期間を設け、例外処理と緊急対応のベストプラクティスを残すのも有効です。
参考リンク
4. ライオン、AWS支援で独自LLM「LION LLM」開発へ──“知の継承”でものづくりDXを加速
概要
ライオンはAWSの生成AI実用化推進プログラムの協力を受け、研究・品質データなど社内ナレッジを学習した独自LLMの開発に着手しました。ベースにQwen 2.5-7Bなどの小規模モデルを活用しつつ、分散学習基盤と社内検索(RAG)を組み合わせ、配合検討や不具合解析、品質照会への回答精度向上を狙います。「Vision2030 2nd STAGE」の重点テーマとして“ものづくりDX”を掲げ、開発スピードと知識継承の両立を図る方針です。
さらに、社内展開に向けてはモデルガバナンスが鍵です。LoRA等の軽量微調整で用途別の派生モデルを作り、監査ログとPII/営業秘密のマスキングを仕組み化。回答は根拠文書の引用を必須にし、レッドチーミングで安全性を検証します。小規模でもGPUスポット活用やサーバレス推論を選べば運用コストを抑えられ、部門横断のナレッジ基盤としても機能します。
中小企業への影響
自社専用LLMと聞くと構えますが、まずは領域特化の小型モデル+RAGからでも効果が出ます。SOP、検査記録、規格票、法規対応文書を権限管理つきで正規化し、根拠リンクを返す回答にすればハルシネーションの懸念を抑えられます。紙・PDFのOCRや同義語辞書の整備をセットで行うと、検索精度が一気に改善します。肝はデータの権利・機密の扱いと、評価指標(回答正確性・再現性・コスト)の設計です。
経営者の視点
「この知識が失われると事業が止まる」という領域を特定し、データ整備→モデル選択→運用ガイドラインの順でロードマップ化しましょう。パイロットは1業務1ペイン(例:設計変更理由の根拠検索)に絞り、プロンプト設計とガードレールを業務フローに埋め込みます。費用対効果は、回答時間短縮×件数と再発防止で測るとブレません。クラウドのクレジット支援や外部評価も積極活用を。
参考リンク
独自AIで『ものづくりDX』を加速/オリジナル生成AIモデル開発を始動
5. 国交省「上下水道DX技術カタログ」を拡充──AI・ドローン等45件を新規掲載し調達を後押し
概要
国土交通省は、上下水道施設のメンテナンス高度化に資する技術を集約した「上下水道DX技術カタログ」を拡充し、AI解析・ドローン点検・非破壊探査など45件を新規掲載しました。老朽化・人材減少に直面する水道・下水道の維持管理で、導入候補の比較検討を容易にする狙いです。2025年3月のカタログ公開後、実務ニーズに合わせて内容を更新し、検索システムから技術を横断的に参照できます。
公式発表は2025年10月3日付の報道資料で、更新版では「管路内調査の無人化」「大深度空洞調査」「大口径管の管厚・強度測定」「継続モニタリング」などの重点テーマに紐づく技術を整理。事業者は導入条件・価格帯・適用範囲の目安を把握しやすく、自治体は要件定義と予算化を進めやすくなります。さらに、オンラインの検索システムが提供され、対象技術の横断検索や比較が可能です。これにより、調達の透明性と導入までの意思決定スピードが高まります。
中小企業への影響
設備保全・点検・土木系の事業者にとって、要件の可視化は提案速度の向上に直結します。カタログに沿って点検→解析→意思決定を一気通貫でパッケージ化できれば、サブスク保全や成果連動型の価格設計も可能になります。自治体側の個人情報・セキュリティ要件や、屋内・地下・狭所といった現場適合性の確認も事前に整理できます。掲載技術の適用条件/導入事例/測定限界を読み解き、自社の強みと組み合わせましょう。
経営者の視点
自社技術がカタログのどの分類に当たるかを棚卸し、評価指標(検出精度・再現性・安全性・作業時間)でPoC→本導入へ段階設計を。広域連携(複数自治体)を見据え、遠隔支援・教育・保守のSLAをテンプレ化すると成約率が上がります。入札では、要件×現場制約のマトリクスで“できる・できない”を明確化し、リスク分担と価格を透明にするのがコツです。
参考リンク
国土交通省が『上下水道DX技術カタログ』を拡充、AI・ドローン技術など45件を掲載
まとめ
生成AIや最適化、予兆保全、ドローン点検などの技術は、“待ち時間”“ムダな移動”“突発停止”“説明困難”といった現場の非効率を減らします。今回のポイントは、①暗黙知のルール化で早く正しく作る、②予兆保全で止めない、③配車最適化で運ぶムダを消す、④専用LLM×RAGで知を磨く、⑤公共カタログで提案と調達を加速、の5つです。
次の一手として、1つのボトルネック工程を選び、可視化→標準化→自動化の順で60日計画を設計してください。効果測定のKPI(時間短縮、コスト削減、不良・回送・停止の減少)を事前に決め、小さく試して早く学ぶ姿勢が成功の近道です。継続的に情報をキャッチアップし、貴社のDXロードマップをアップデートしていきましょう。