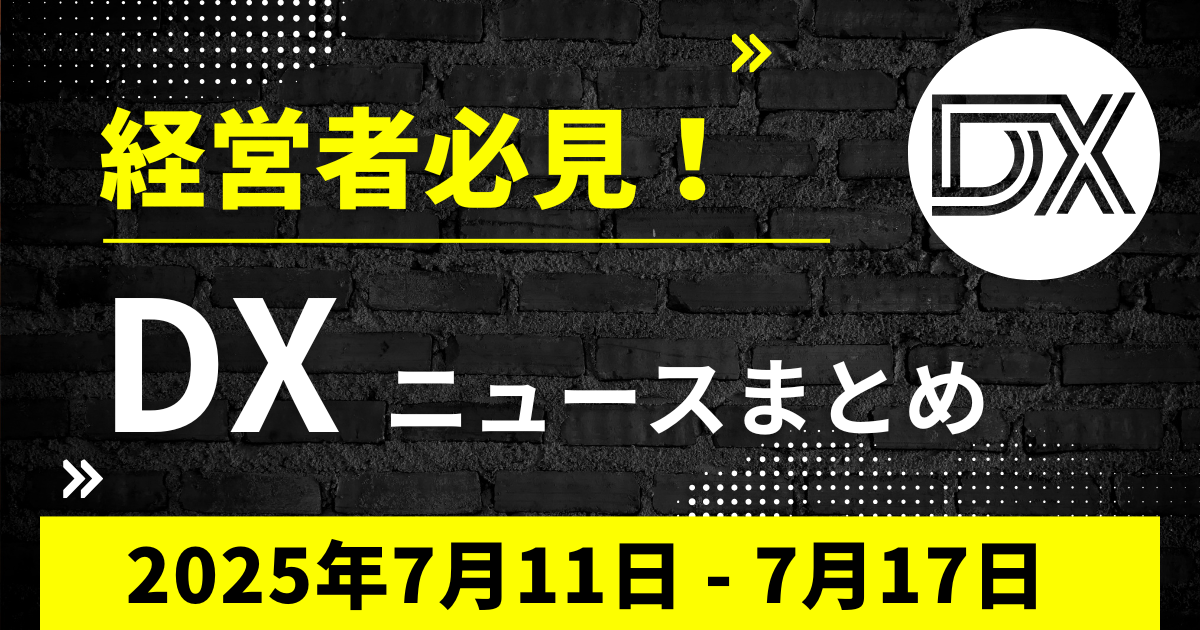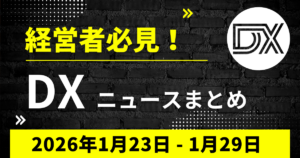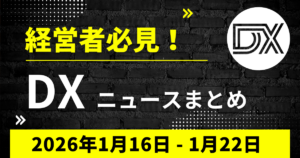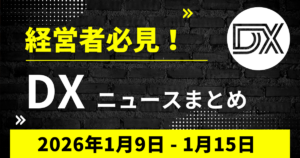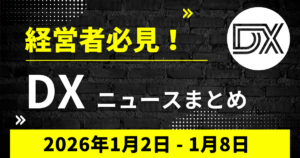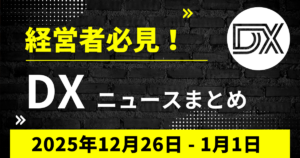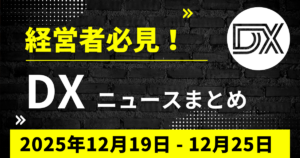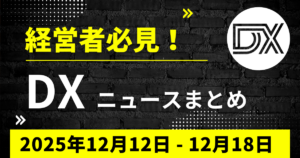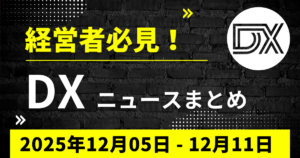DXニュースまとめ(2025年7月11日〜7月17日)
DX(デジタルトランスフォーメーション)分野では、日本国内で重要な動きが次々と報じられました。政府と取引所がDX先進企業の認定を進め、大手企業は生成AI(※文章や画像を自動生成するAI)の活用による大胆なDX戦略を打ち出しています。さらに、地方自治体が産学官連携で中小企業支援策を強化し、流通業界では人手不足を乗り越える店舗DXへの取り組みが具体化しました。また、全国規模のDXコンテストで優れた事例が表彰されるなど、業界横断でDX推進の機運が高まっています。ここでは2025年7月11日から17日にかけて注目された5つのニュースを取り上げ、その概要と中小企業への示唆をわかりやすく解説します。
1. 三菱電機、「Serendie」で生成AI活用&DX人材2万人育成へ
概要
三菱電機が独自のデジタル基盤「Serendie(セレンディ)」を軸にDX(デジタル変革)戦略を加速しています。2030年度までにDX人材を2万人規模に増強する計画を掲げ、今年4月には社員向けの「DXイノベーションアカデミー」を設立しました。社内外のデータを活用したサービス開発を推進するため、横浜と米ボストンに共創拠点「Serendie Street」を開設し、スタートアップ企業や大学とも連携を強化しています。また、空調設備や鉄道システムなど同社製品の運用データをAIで分析し、新たなソリューションを生み出す取り組みも開始。生成AIを含む最新のIT技術を活用することで、ハードとデータサービスを融合した新ビジネスモデルの創出を目指しています。
中小企業への影響
大手メーカーが社内人材の大規模育成と先端技術の積極活用に乗り出したことは、中小企業にも示唆に富みます。例えば「自社の強み×データ活用」で新サービスを生み出す発想や、社員全員のITリテラシー向上に継続投資する姿勢は、小規模企業でも参考になるでしょう。自社に専門人材が少なくても、外部の研修プログラムや自治体のDX支援制度を活用して、人材育成とデジタル活用を進めることが可能です。また、三菱電機のように顧客との協働でサービス改善を図るアプローチは、中小企業が取引先・顧客との関係を深めつつDXを進めるヒントになります。大企業発の新技術ソリューション(例えば設備の予知保全サービスなど)が今後中小企業にも提供される可能性も高く、最新動向にアンテナを張っておくことが重要です。
経営者の視点
経営者として注目すべきポイントは、経営戦略にDXを位置付けて人材と技術に投資する決断力です。三菱電機はトップ自ら「デジタルによる革新的な企業へ変わる」と宣言し、社内のDX推進組織を統合してリソースを集中しています。中小企業でも、経営者が自社のDX推進役を担い、将来を見据えたIT投資や社員教育に踏み切ることが求められます。「うちの規模では無理」と尻込みせず、例えば無料・低コストで使えるクラウドサービスやAIツールを試し、小さく始めて成果を検証しましょう。また、異業種や大学との交流会・勉強会に参加して新しい発想を取り入れるのも有効です。DXは技術導入が目的ではなく、組織風土とビジネスの変革であることを念頭に、経営トップ自ら旗を振って変革を進めましょう。
参考リンク
クラウドWatch:三菱電機、デジタル基盤「Serendie」を軸とした成長戦略を描く姿勢を強調
2. 東京ガス、経産省の「DX銘柄2025」で注目企業に選定
概要
東京ガスは、経済産業省と東京証券取引所が選定する「DX銘柄2025」において「DX注目企業2025」の一社に選ばれました。この取り組みは上場企業の中からデジタル技術で経営革新を遂げている企業を選出するもので、東京ガスは2020年・2023年に続き再度の選定となります。同社が評価されたポイントは、エネルギー事業の枠を超えた新規サービス創出と社内DXの徹底推進です。具体的には、新設のソリューション事業ブランド「IGNITURE(イグニチャー)」による脱炭素やエネルギーマネジメント分野での新サービス展開、そして独自開発した生成AI搭載の社内アプリ「AIGNIS」を活用した顧客対応力強化などが高く評価されました。また、DXを経営戦略の中核に位置付け全社横断組織で推進している点や、社員のレベル別研修など体系立てた人材育成によってDX人材を拡大している体制も注目されています。
中小企業への影響
DX銘柄に選ばれる企業の事例から、中小企業もデジタル化の方向性を学ぶことができます。東京ガスの例では、新ブランドの立ち上げによる事業モデル転換や、社内業務へのAI活用による顧客体験の向上がキーワードです。これは中小企業にも「自社の強みをデジタルで伸ばすには?」と考えるヒントになります。例えば老舗企業であれば蓄積したノウハウをデータベース化してサービス化する、顧客対応にチャットボットを導入して迅速化する、といった工夫が考えられるでしょう。また、同社が全社的にDX推進を図っているように、小規模でも部署横断のプロジェクトチームを作り、経営層直下でデジタル導入を検討する仕組みを作ればスピーディーに実行できます。国主導のDX銘柄は優れた成功事例の宝庫です。公式レポートや事例集が公開されているので、業種が違っても自社に応用できそうなアイデアを探してみる価値があります。
経営者の視点
経営者としては、自社が中小企業であってもDXへの取り組みを経営価値向上につなげる視点を持つことが大切です。東京ガスはDXにより顧客サービス強化と業務効率化を両立し、結果的に企業価値を高めている点が評価されています。中小企業でも、「DX=コスト増」ではなく将来的な収益拡大やブランド力向上への投資だと捉えましょう。そのためには、闇雲に最新ツールを導入するのではなく、自社の経営課題(売上拡大、人手不足、顧客満足度向上など)を洗い出し、解決策として最適なデジタル施策を見極めることが重要です。例えば顧客管理が課題ならCRMシステムの導入、人材不足なら在宅勤務制度とオンライン研修の整備、といった具合に目的を明確にします。経営トップ自ら旗振り役となり、社内外に「デジタルで会社を良くする」というメッセージを発信することで、社員の意識改革や取引先からの協力も得やすくなるでしょう。
参考リンク
東京ガス:「DX注目企業2025」に選定!◆ソリューション事業ブランドの立ち上げや独自開発の生成AIアプリなどが評価
3. D-JITとMISUMI floow、日本DX大賞2025で快挙
概要
デジタル改革の優れた事例を表彰するコンテスト「日本DX大賞2025」で、精密機器商社ミスミグループのサービスが高い評価を得ました。7月17日に発表された結果によると、同社のデジタル購買プラットフォーム「D-JIT(ディージット)」が事業変革部門の優秀賞を受賞し、さらに調達業務DXサービス「MISUMI floow(フロー)」がSX(サステナビリティ変革)部門の奨励賞を受賞しました。日本DX大賞には158件もの応募があり、その中から24件が最終候補に選ばれる狭き門でした。同社のサービスはいずれも製造業の調達プロセスをデジタル技術で革新するもので、大量のサプライヤ在庫データや需要データを統合し、AIを駆使して発注・納品を自動最適化する仕組みが評価されました。例えばD-JITは複数企業の在庫や工場生産能力をネットワーク化し、必要数量の即時見積もり・納期提示を実現。MISUMI floowは工場内に消耗品自販機を設置し、センサーで在庫を管理・自動補充することで調達業務の7割削減を達成しています。
中小企業への影響
業務プロセスをデジタルで変革するアイデアは、中小企業にとっても学びになります。今回受賞したサービスは主に大企業向けですが、その根底にある「ムダな時間や在庫をITで省く」という発想はどの企業規模にも通じるものです。例えば、在庫管理を手作業の台帳からクラウドの在庫管理ソフトに切り替えれば、在庫切れや過剰在庫のリスクを減らせます。また、AIを使った需要予測は中小企業でも活用可能で、過去データを分析して発注やスタッフ配置の最適化に役立てることができます。ミスミの事例からもう一つ重要なのは顧客目線のDXです。単に社内効率を上げるだけでなく、顧客企業の「時間価値」を高めるサービスを提供した点が評価されました。中小企業も、自社の顧客や取引先が抱える無駄・不便をITで解消できないか考えてみましょう。それが結果的に自社の強みとなり、他社との差別化にもつながります。
経営者の視点
経営者にとって、今回の受賞はDXへの投資が競争力強化に直結することを改めて示しています。ミスミグループはIT技術を最大限活用することで市場のニーズに応え、顧客企業の生産性向上に貢献しました。中小企業でも、自社単独では難しい場合は業界内外の連携を模索するのがおすすめです。例えば同業の数社で共同でITツールを導入したり、取引先とEDI(電子データ交換)を進めたりすれば、単体では得られない効果が期待できます。また、社内の現場改善アイデアを集めてミニDXプロジェクトを立ち上げるなど、小さな成功体験を積むことも大切です。今回のようなDXの表彰制度や補助金の情報にもアンテナを張り、自社の取り組みを発信してみましょう。「うちはITが苦手だから」と敬遠せず、外部ベンダーや専門家の力も借りつつ、自社らしいDXへの一歩を踏み出すことが、将来の受注拡大や人材確保にもつながるはずです。
参考リンク
PR TIMES:D-JITとMISUMI floowが日本DX大賞2025を受賞
4. 東急ストア、店舗DXで人手不足と顧客サービスを両立
概要
首都圏でスーパーマーケットを展開する東急ストアは、深刻化する人手不足に対応するため積極的に店舗業務のDXに取り組んでいます。同社ではDX戦略部門を中心に全社横断でデジタル施策を推進しており、レジ業務の省力化や発注の自動化など現場改革が進んでいます。例えば一部店舗ではフルセルフレジ(無人レジ)の導入に踏み切り、従業員が商品のスキャンから会計まで行わずに済む仕組みを実装しました。これによりレジ待ち時間の短縮と従業員の負担軽減を両立しています。また、天井カメラとAIを活用したシステムで売場をモニタリングし、品出しや補充が必要な商品を検知する実証実験も行われています。さらに、電子棚札(デジタル価格表示)や店舗バックヤードの在庫管理システムなどを導入し、価格変更・棚卸作業の効率化や発注ミス削減にも効果を上げています。同社DX推進リーダーによれば、「現場の従業員とお客様双方の理解があってこそDXは成功する」とのことで、現場の声を反映しつつテクノロジーを浸透させている点も特徴です。
中小企業への影響
小売業をはじめサービス業の中小企業にとって、人手不足×DXは避けて通れないテーマです。東急ストアの事例は、人手が足りないからこそデジタルで業務を補完・代替する有効性を示しています。中小の小売店でも、例えばセルフレジやモバイル決済の導入は比較的低コストで可能になってきています。また在庫管理も、Excel管理からクラウド在庫システムへの移行や、棚卸をスマホのバーコード読み取りで行うなど、省力化の余地が多く存在します。重要なのは、現場スタッフとお客様の受け入れやすさを考慮することです。DX導入時には従業員への丁寧な教育と、お客様への案内・フォローを行い、不安や戸惑いを取り除く工夫が必要です。中小企業の場合、顔なじみのお客様も多いため、「新しいサービスを試してみてどうですか?」と直接声を聞きながら改善できる強みもあります。労働力不足という逆風を、新技術導入の追い風に変えていく姿勢が求められます。
経営者の視点
経営者にとって、人手不足の解決と顧客満足の維持を両立するには優先度の高い業務からDX化するのがポイントです。東急ストアの場合、レジ対応という労働集約的な業務にメスを入れました。同様に、中小企業でも特に負荷が大きい業務(例:手書き伝票の入力、在庫確認、問い合わせ対応など)を洗い出し、そこを起点にITツール導入を検討すると効果が出やすいでしょう。また、数字で成果を測ることも大切です。DX投資に踏み切ったら、「レジ待ち時間が何分減った」「月間の残業時間が何時間削減できた」といった指標を追いかけてみましょう。成果が見えれば社員のモチベーションも上がり、追加のDX施策にも前向きになります。もう一つ、経営者自ら店舗や現場に足を運び、現場目線で問題点を発見することも欠かせません。最新技術の展示会に行くのも良いですが、自社の現場のリアルな課題を知ることがDX成功の近道です。「現場主導+経営後押し」でのDX推進により、少人数でも回る強い組織づくりを目指しましょう。
参考リンク
Japan Innovation Review(JBpress):人手不足、業務の複雑化で待ったなし…東急ストアが取り組む「現場も顧客も納得できるDX」の進め方
5. 堺市の産官学「DX推進ラボ」、地域ぐるみ支援が評価
概要
大阪府の堺市で進められている産官学連携プロジェクト「堺DX推進ラボ」が、この度日本DX大賞2025の支援部門で奨励賞を受賞しました【支援部門ファイナリスト全8件中の受賞】。堺DX推進ラボは、堺市役所が事務局となり、地元企業・大学・金融機関・商工団体などが参画して市内中小企業のDX促進を図る取り組みです。具体的には独自の「堺DX診断ツール」で企業ごとの課題を見える化し、それに基づいて専門家がデジタル人材育成や新規事業創出を伴走支援します。人材育成には市の補助金を用意し、社員のIT研修受講や社内DX担当者の育成を経済的に後押ししています。また、新規事業の立ち上げ支援プログラムも実施し、優れたアイデアには外部資金や大企業とのマッチング支援が受けられる体制です。これらを支えるため、堺市は地元金融機関(地方銀行・信用金庫等)やNTT西日本、シャープといったIT企業ともネットワークを構築。地域全体で中小企業を「よってたかってDX化」していく有機的な連携モデルが評価され、今回の受賞につながりました。
中小企業への影響
地方自治体が中心となって地域の企業のDXを支援する動きは、他の地域にも広がる可能性があります。堺市の例は、行政・金融・企業・大学が連携することで中小企業単独では難しい課題解決を図っている点が特徴です。中小企業にとって、自社だけでDX人材を育てたり新しいITシステムを導入したりするのはハードルが高い場合があります。しかし、このように自治体がハブとなってくれれば、補助金や専門家チームの派遣など様々なリソースを活用できます。堺市は企業診断から実行支援までワンストップで提供していますが、他の自治体でもDX相談窓口やIT専門家派遣制度が増えています。自社が所在する地域の施策をぜひ調べてみましょう。また、今回の受賞で注目されたことで堺市以外の企業も他地域の支援策に関心を持つはずです。地域を越えて企業ネットワークが生まれ、優良事例が共有されれば、日本全体の中小企業DXが底上げされることにつながります。
経営者の視点
経営者として、地元の支援策をフル活用するアンテナを高く張ることが重要です。「うちの会社にDXは難しい…」と感じている経営者こそ、行政や支援機関の門を叩いてみてください。堺市のような包括的支援策がなくても、多くの自治体でDX推進補助金や専門家による無料相談会などが用意されています。特に地方の中小企業は情報が入ってきにくい面がありますので、商工会議所や地域金融機関から積極的に情報収集しましょう。また、支援を受けるだけでなく地域内での企業交流にも参加するのがおすすめです。同じ地域の経営者同士でDXの取り組みを共有すれば、新たな協業のきっかけや課題解決のヒントが得られます。堺市の取り組みが示すように、DXは一社単独ではなく周囲を巻き込んで進める時代です。自社の変革と併せて、地域経済全体を盛り上げるくらいの気概で取り組むことで、結果的に自社の成長にも大きく貢献するでしょう。
参考リンク
PR TIMES(堺市):堺DX推進ラボの地域ぐるみでの産業DX支援の取組が、日本DX大賞2025支援部門にて奨励賞受賞
まとめ
今回紹介したニュースから、中小企業経営者に共通して言えるのは「チャンスと危機は紙一重」だということです。大企業がDXで先行すれば市場競争は激しくなりますが、その先端事例から学び自社に取り入れるチャンスでもあります。行政や支援団体のサポートも増えており、単独では難しい課題も周囲の力を借りて解決できる環境が整いつつあります。まずは経営者自らがDXの重要性を正しく理解し、社内外に向けて「変革していくんだ」というメッセージを発信しましょう。
幸い、日本全体でDX推進の流れは加速しています。今回のニュースにあった表彰制度や支援策、そして成功事例は、いずれも「変わる企業を応援する」風土の表れです。自社もこの追い風を逃さず、できるところからデジタル化や業務見直しに着手してください。例えば、紙の業務をひとつ電子化する、新しいITサービスのトライアル版を使ってみる、といった小さな一歩でも構いません。そうした積み重ねがやがて大きな成果となり、2025年以降の厳しい経営環境を生き抜く力になります。
デジタルの波は中小企業にも確実に押し寄せています。本記事をヒントに、自社ならではのDX戦略を描き、行動に移してみましょう。経営者の決断と行動が、会社の未来を切り拓く原動力です。今後も最新情報をキャッチアップしながら、ぜひ積極的にDXにチャレンジしていってください。