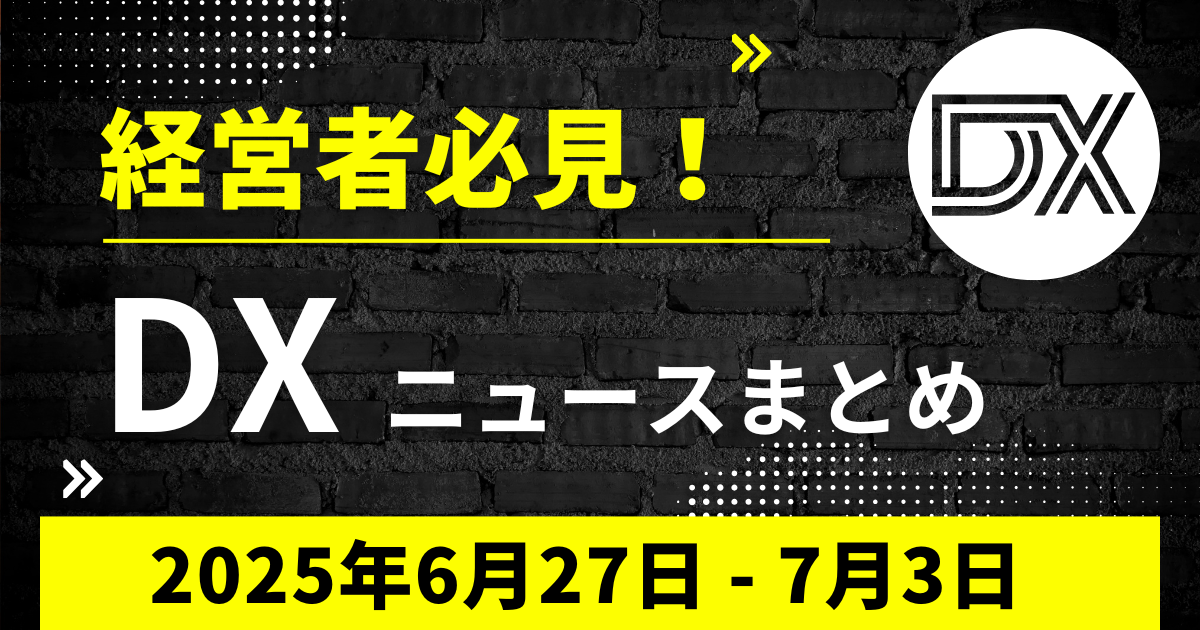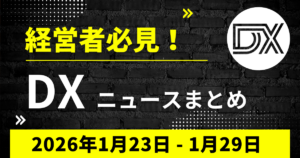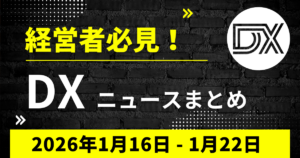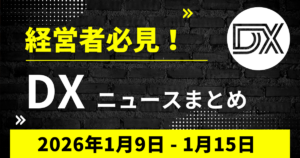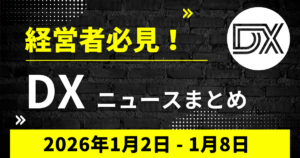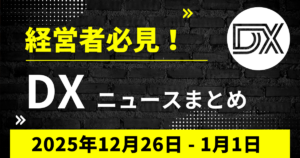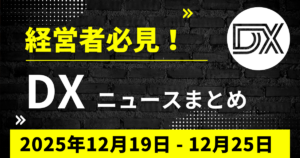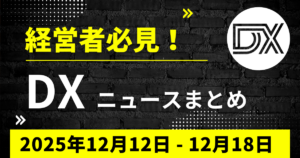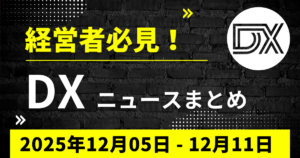DXニュースまとめ(2025年6月27日〜7月3日)
2025年6月下旬から7月上旬にかけて、日本国内でDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する重要な動きが続出しました。 政府は行政分野のデジタル化を加速する包括的なビジョンを打ち出し、大手企業ではDX推進の取り組みが公式に認定されました。また、IT企業や金融機関が中小企業のDX支援に本腰を入れる新サービスや組織を立ち上げ、老朽化したシステム刷新を支援するソリューションも登場しています。中小企業経営者にとってDXは他人事ではなく、自社の競争力強化に直結するテーマです。今回は注目の5つのニュースをピックアップし、その概要とポイントをわかりやすく解説します。デジタル時代に取り残されないために、今どんな動きが起きているのか一緒に見ていきましょう。
1. 国交省、「DXビジョン」で行政データ活用を加速
概要
国土交通省は6月13日、「国土交通省DXビジョン」を策定・公表しました。 行政サービスのデジタル化、政策立案へのデータ活用(EBPM)、オープンイノベーション推進、データ基盤整備の四つの柱を掲げ、同省所管分野でのDX推進の羅針盤と位置付けています。例えば、行政手続きで得られる大量の非構造データをAIで自動構造化しデータベース化する「Project LINKS」を開始し、既に100万件超の紙・PDF資料をオープンデータ化する成果を上げました。行政手続のオンライン化も進み、e-Govで262件の手続を24時間対応にするなど、デジタル技術で業務効率と利便性を飛躍的に向上させています。背景には人口減少やインフラ老朽化、災害頻発といった課題があり、データ活用によって政策対応を迅速化・高度化する狙いがあります。
中小企業への影響
国のDXビジョン策定により、今後行政とのやり取りや各種手続がますますデジタル化される見通しです。これは中小企業にもメリットをもたらします。例えば許認可申請や報告業務のオンライン化によって、これまで紙や対面で時間を取られていた事務負担が軽減されるでしょう。また、オープンデータの拡充により、公共データを活用した新サービス開発や市場調査が容易になる可能性もあります。一方で、行政がDXを推進することで企業にもデジタル対応を求める流れが強まることが予想されます。電子申請への対応やデータ連携への協力など、従来アナログだった分野でもITリテラシーが必要になるでしょう。国全体のデジタル基盤が整備されれば、大企業と取引する際のデジタル要件も高まるかもしれません。中小企業にとっても、公的手続の変化に適応し、自社の業務プロセスをデジタル対応させておくことが重要です。
経営者の視点
経営者として注目すべきは、国のDX推進に自社がどう乗っていくかという点です。まず、自社の行政手続きがオンライン化に対応できているか確認しましょう。まだ紙で行っている手続きがあるなら、早めに電子申請等に切り替えておくことをお勧めします。また、国交省のような官公庁が公開する業界データや統計情報にはビジネスのヒントが詰まっています。日頃から関連データをチェックし、商品開発やマーケティングに活かせないか検討してみましょう。さらに、デジタル技術を活用した規制緩和や補助金制度が今後出てくる可能性があります。最新情報にアンテナを張り、「使えるものは使う」姿勢で国の施策を自社のDXに取り入れることが大切です。行政のDX化は社会全体のDXを底上げするチャンスでもあります。自社もその波に乗り、業務効率化だけでなく新たな事業機会の創出につなげましょう。
参考リンク
観光経済新聞:国交省、「国土交通省DXビジョン」を公表〖29日付〗
2. 住友林業、DXへの取り組みが公式認定を取得
概要
日本企業のDX推進を評価する制度で新たな動きがありました。住友林業株式会社が7月1日付で経済産業省の「DX認定事業者」に認定されました。DX認定制度は「デジタルガバナンス・コード」に沿って優れたDX推進体制を整備した企業を国が認定する仕組みで、有効期間は2年間です。住友林業では2030年ビジョンに基づきIT・DX戦略を策定し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による社内業務効率化や顧客情報の統合基盤構築などを推進してきました。森林資源管理から住宅建築、エネルギー分野までデジタル技術を活用し、全社横断での業務変革と新事業への挑戦を進めている点が評価されたものです。「全員参加のDXによるデジタル化の深化」や「デジタルで生産性向上」といった基本方針を掲げ、グローバル展開も視野に入れたDXを推し進めていることが今回の認定につながりました。
中小企業への影響
大企業のDX認定取得は、中小企業にもいくつかの示唆を与えます。まず、DX推進には明確な経営ビジョンと計画が不可欠だということです。住友林業の例では、経営トップ主導で長期ビジョンにDX戦略を位置付け、具体的な施策(業務の自動化やデータ活用基盤整備など)を講じています。中小企業でも規模は小さくとも、自社なりのDX方針や目標を定めることが重要です。また、大手企業がDXを加速すれば、その取引先である中小企業にもデジタル対応や高度なIT連携が求められる場面が増えるでしょう。例えば受発注や情報共有がよりデジタル化され、紙やFAX主体では取引が難しくなる可能性もあります。さらに、DX認定制度自体は中小企業にも開かれており、優良な取組を行う企業はPRや信用力向上につながります。すぐに認定取得を目指さなくても、認定基準となるガバナンス・コードの項目(経営ビジョン策定、公表、体制整備など)を参考にして社内体制を整えることは有益です。
経営者の視点
経営者としてこのニュースから得られるポイントは、「DXを経営課題として正式に位置付けること」の大切さです。忙しい日々の中でIT化が後回しになりがちですが、住友林業のようにトップ自ら旗を振り全社でDXを推進する姿勢が成果につながります。まず、自社の経営計画にDXの項目を盛り込み、具体的な目標(例:○年までに主要業務の○%をデジタル化など)を設定しましょう。 また、DXは専門部署任せではなく全社員が関与すべき取り組みです。現場の声を聞きながら「全員参加のDX」を進めることで、小さな会社でも大きな効果を生むことができます。必要に応じて外部のDX支援制度や専門家の力も借りましょう。経済産業省のDX認定企業の事例集は公開されており、そこから他社の成功パターンを学ぶことも可能です。DXは自社の存続と成長に直結するテーマです。大企業の成功事例に学びつつ、自社に合ったデジタル改革を計画的に進めていきましょう。
参考リンク
共同通信PRワイヤー:住友林業、DX認定事業者に選定〖2日付〗
3. LINEヤフー、飲食・サロン業向けDX支援の新会社を設立
概要
中小規模の店舗ビジネスを支援するため、LINEヤフー株式会社が新会社「LINEヤフービジネスパートナーズ」を設立しました(7月1日付)。 飲食店や理美容院など地域の店舗に特化し、DXによる顧客対応力強化や業務効率化を支援するのが目的です。同社によれば、国内のDX関連投資は年々拡大し2030年度には約9.26兆円に達すると見込まれる一方、飲食・美容業界では人手不足やコスト面からDX導入が遅れ、競争力低下が課題となっています。例えば予約管理や顧客管理が未だアナログで行われ、リピーターづくりや業務効率に支障を来すケースが多いと指摘されています。新会社では、月間利用者9800万人を抱える「LINE」プラットフォームを活用し、店舗運営のデジタル化を支援します。LINE公式アカウントによる集客・顧客コミュニケーションや、予約システムの導入支援、コンサルティングを通じて、小規模店舗でも無理なくDXを実現できるようサポートするとのことです。「2025年の崖」(古い基幹システム放置による経済損失リスク)が指摘される中、地域の事業者にも迅速な対応が必要として、LINEヤフーはDX推進を専門に担う子会社設立に踏み切りました。
中小企業への影響
このニュースは、地域で店舗営業を行う中小企業にとって朗報と言えます。IT人材や資金が乏しくても大手プラットフォームを活用した手軽なDX手段が提供されるからです。例えば、個人経営の飲食店でもLINE公式アカウントを活用すれば、予約の自動受付やクーポン配布、顧客との1対1トークによるリピーター育成が可能になります。これまでは専門システムの導入に二の足を踏んでいた店舗も、身近なLINEを使ったソリューションなら導入ハードルが低いでしょう。また、新会社によるコンサルティング支援で各店舗の状況に合わせたオーダーメイドのDXプランを提案してもらえることも期待できます。人手不足で日々の運営に追われる小規模事業者にとって、外部パートナーの手厚いサポートはDX推進の強力な後押しです。一方で、DXが進むにつれ競合他社との差も生まれます。デジタル活用が進んだ店舗は予約の埋まり方や顧客満足度で優位に立てるため、同業他社も追随してDXに取り組まざるを得なくなるでしょう。遅れると顧客離れにつながる可能性があるため、各店舗はこの流れを他人事とせず注視する必要があります。
経営者の視点
店舗ビジネスの経営者にとって、今回の取り組みから得られる教訓は「身近なITツールからDXを始める」ことです。難しい専門システムをいきなり導入しなくても、LINEのように多くの人が使っているプラットフォームを活用すれば十分な効果が得られる場合があります。例えば、電話予約中心だったお店がLINE予約を導入すれば、24時間受付で予約漏れも減り、顧客は手軽に予約できます。ポイントカードやクーポンもLINEで発行すれば紙の管理が不要になり分析も可能です。経営者は「ITが苦手だから…」と敬遠せず、小さな一歩でもデジタル化に踏み出すことが大切です。LINEヤフーの新会社のように大企業が支援に乗り出している今こそチャンスと言えます。地域の商工会や業界団体経由で情報収集し、利用できる支援策には積極的に手を挙げましょう。また、自社でDXに取り組む際は、「何のためにデジタル化するのか」を明確にすることも重要です。ただ闇雲にITツールを導入しても定着しません。目的(売上アップ、業務効率化、顧客満足度向上など)を定め、現場の声を取り入れながら少しずつ改善を積み重ねていきましょう。身近なDX成功が次の成長につながるはずです。
参考リンク
日本ネット経済新聞:LINEヤフー、飲食・理美容業界の店舗DX支援会社を設立〖2日付〗
4. 地方銀行とNTTが連携、地域企業向けDXコミュニティを開始
概要
千葉県の地方銀行である千葉興業銀行と、NTTグループのDX支援企業がタッグを組み、地域企業のDX推進を支援するコミュニティプラットフォーム「ちばCoラボ」の構築に乗り出しました。 6月30日に両社が発表したもので、7月1日から本格的な取り組みを開始しています。この「ちばCoラボ」は、中小企業同士が業種や規模を超えてオンライン/オフラインで学び合い、実践知を共有できる場を提供するものです。具体的には、参加企業がDXの最新トレンドや成功事例を学べる記事コンテンツ、企業間交流のためのオンラインコミュニティ、DX成熟度を診断できるツール、さらにはリアルの勉強会・交流イベント等を用意し、地域の中小企業が自律的にデジタル変革に取り組める環境を整備します。背景には、総務省の調査で「中小企業の約70%がデジタル化に未着手」という現状があり、単独ではDXが進まない企業に対し銀行がハブとなって支援しようという狙いがあります。NTT側は今年3月に金融機関向けDX支援ソリューション「DXSTAR for Bank」を開始しており、その第一号事例として千葉興業銀行と連携する形です。正式サービスインは2025年10月を予定し、それまでに機能拡充や参加企業の意見反映を重ねるとしています。
中小企業への影響
地方発のこの取り組みは、地域の中小企業にとって心強い後方支援となるでしょう。これまでDX推進といっても何から始めればよいか分からなかった企業でも、銀行主導のコミュニティに参加すればヒントを得られるからです。例えば近隣の他社がどんなITツールを導入し効果を上げたか、生の事例を共有してもらえる場は貴重です。身近な企業の成功事例は自社にも応用しやすく、説得力があります。 また、銀行という信用のおける機関が窓口になることで、専門ベンダーに直接相談するハードルが下がり、安心してDX支援サービスを利用できる利点もあります。診断ツールで自社のデジタル成熟度を測れば、自分たちの課題が客観的に見えてくるでしょう。加えて、このようなコミュニティには行政やIT企業から最新情報が提供されたり、補助金の紹介がなされたりと、副次的なメリットも期待できます。注意点としては、せっかく支援の場があっても受け身の姿勢では十分に活かせないということです。コミュニティに参加した中小企業同士で切磋琢磨し、自社の課題解決に積極的に取り組むことで初めてDXが前進します。地域全体でデジタル化の底上げを図る本プロジェクトが軌道に乗れば、参加企業の競争力強化や新ビジネス創出といった波及効果も生まれるでしょう。
経営者の視点
中小企業経営者として、このニュースから得るべきは「仲間とともにDXに取り組む」姿勢です。社内にIT担当者がいなくても、外部のコミュニティで専門知識や他社事例を共有してもらえれば道筋が見えてきます。ぜひ近隣地域や取引先で同様の取り組みがあれば参加を検討しましょう。銀行や信用金庫は企業支援の一環でDXセミナーや相談会を開くケースが増えています。そうした機会に顔を出し、「うちも何か始めないと」と危機意識を持つ経営者同士で情報交換することは大きな刺激になります。また、自社が属する業界以外の事例にも耳を傾けてみてください。他業種の革新的なDX事例が自社にも新風を吹き込むことがあります。重要なのは、「DX=難しいIT導入」ではなく「経営課題を解決する新しいやり方」だと捉えることです。今回の千葉興業銀行のように、金融機関は企業の課題をよく知っています。そうしたパートナーの知見を借りつつ、自社ならではのDXロードマップを描いていくと良いでしょう。仲間と共に学び、実践することで、単独では乗り越えられなかった壁も突破できるかもしれません。
参考リンク
船橋経済新聞:NTTと連携し「ちばCoラボ」構築を開始〖30日付〗
5. キヤノンITS、老朽システム刷新を丸ごと支援する新サービス
概要
キヤノンITソリューションズ株式会社(キヤノンITS)は6月30日、レガシーシステム(旧式基幹系)のマイグレーション支援サービス「PREMIDIX(プレミディックス)」の提供開始を発表しました。 同社は従来からメインフレーム(汎用機)で動く古い業務システムをオープン環境へ移行するサービスを展開してきましたが、新サービスでは移行前の現状評価(アセスメント)から移行実行、移行後の保守運用代行までを一括サポートする点が特徴です。具体的には、長年使われてきたCOBOL等で書かれたシステム資産を調査・分析し、最適な移行計画を立案します。その後、プログラムを極力修正せずに最新のサーバ環境へリホスト(載せ替え)方式で移行し、移行後も新環境で安定稼働するよう運用監視や保守作業を請け負います。これにより、「2025年の崖」問題の根源である古いシステムからの脱却をワンストップで支援し、中堅・中小企業でも限られたリソースで安全にシステム刷新が行えるようになります。サービス名「PREMIDIX」は「Precious assets Migration for DX」の造語で、「大切なシステム資産を活かしながらDXに繋げる」という意思を込めているとのことです。価格は個別見積もりで案件ごとに対応し、企業ごとの事情に合わせ柔軟に支援するとしています。
中小企業への影響
このサービスは特にレガシーシステムを抱える中小企業にとって有用でしょう。例えば長年使っている基幹業務システムが古くなり、不安を感じつつも「停止させられない」「更新費用が読めない」ため放置しているケースがあります。PREMIDIXのような専門サービスを利用すれば、計画立案から実行までプロの手で進めてもらえるため、自社内のIT人材不足を補えます。移行後の保守まで任せられるのも安心材料です。自社システムを新規開発し直す場合と比べ、既存資産をリホストする手法はコストや移行期間を抑えられるメリットがあります。これにより、IT予算の限られる中小企業でも現実的な範囲でDXに踏み切る選択肢が増えたと言えます。一方で、こうした外部サービスを活用する際には自社の業務要件をきちんと整理しておくことが求められます。ブラックボックス化した古いシステムの場合、何が動いているか社内で把握できていないことも多いですが、移行プロジェクトを成功させるには現行業務フローの棚卸しや課題の洗い出しが欠かせません。サービス提供側と社内担当者が二人三脚でプロジェクトを進める体制づくりも重要です。総じて、PREMIDIXの登場は「レガシーだから手が付けられない」と諦めていた企業にとってDXへの現実的な道筋が示されたと言えるでしょう。
経営者の視点
経営者にとってレガシーシステム刷新は避けて通れない課題です。しかし「現状維持で当面しのぎたい」という気持ちから先送りしがちでもあります。このニュースが示すのは、専門家の力を借りれば意外にスムーズに移行できる可能性があるということです。まず経営者自ら自社システムのリスクを直視しましょう。メーカーの保守期限切れやエンジニア高齢化で、旧システム運用には思わぬコスト増や障害リスクが潜んでいます。「何とかなるだろう」は危険で、最悪の場合システム停止が事業継続に致命傷を与えかねません。 次に、信頼できるパートナーを探すことです。今回のキヤノンITSのように、大手ITベンダーや専門SI企業が各種移行サービスを提供しています。複数社から提案を聞いて比較検討し、自社に合った進め方を選びましょう。その際、単に技術要件だけでなく、ビジネスを止めずに移行する計画(段階移行や並行稼働期間の確保など)を重視することがポイントです。最後に、移行はゴールではなくDXへのスタートだと捉えましょう。新システムに移った後も、継続的に機能改善やデータ活用を図り、業務効率化や新サービス創出につなげていく視野が必要です。レガシー刷新は投資でもあります。その投資を最大限に活かし、攻めのDXにつなげる戦略を描くのが経営者の腕の見せ所と言えるでしょう。
参考リンク
IT Leaders:キヤノンITS、レガシー移行サービス「PREMIDIX」提供開始〖1日付〗
まとめ
今回取り上げたニュースから、日本におけるDX推進が官民あらゆるレベルで加速していることが分かります。政府は省庁横断でデータ活用を進め、企業のDXを後押しする施策を打ち出しています。一方、大企業は自社のDXを深化させつつ、その知見を活かして中小企業支援に乗り出す動きを強めています。新しいサービスやコミュニティの登場は、リソースに限りがある中小企業でもDXに取り組みやすい環境が整いつつあることを示しています。また、技術面ではレガシーシステムの問題に具体的なソリューションが提示され、「2025年の崖」を乗り越えるための道具立てが揃い始めました。
共通して言えるのは、DXは待ったなしの経営課題だということです。国の政策から業界トレンドまで、デジタル化の波は確実に押し寄せています。中小企業の経営者はこれらの動きを他山の石とせず、自社に取り入れられるポイントを見出すことが重要です。例えば、行政のオンライン化に備えて自社の手続きを電子対応に改める、他社の成功事例を参考に自社のDX計画をブラッシュアップする、専門サービスの力を借りて古いシステムを更新する――できることから着手しましょう。DXは一社だけで完結するものではなく、取引先や顧客、地域社会と連携して進めるものでもあります。今回のニュースにあったコミュニティやパートナーシップのように、周囲と協力しながらデジタル時代のビジネス変革に挑む姿勢が求められます。
幸い、政府のビジョンや先行企業の取り組み事例、支援サービスなど、道しるべとなる情報は豊富に出始めています。ぜひアンテナを高く張り、自社の未来を見据えたDX戦略を描いてください。 小さな一歩の積み重ねがやがて大きな飛躍につながります。デジタルの力を味方につけ、次の時代を勝ち抜く経営を目指しましょう。自社の強みとデジタルを掛け合わせることで生まれる新たな価値に期待しつつ、今後も最新動向を追いながら敏捷に対応していきましょう。