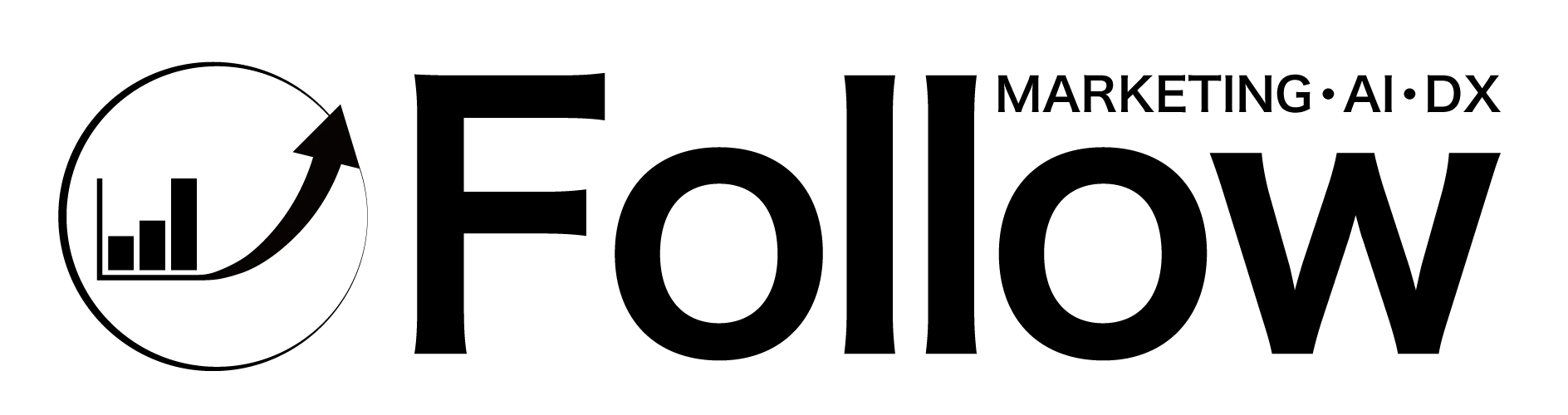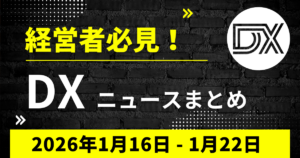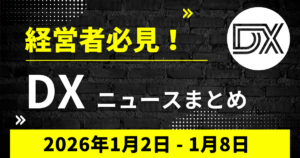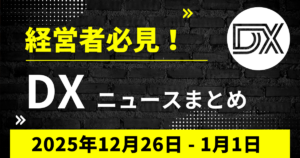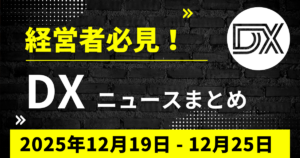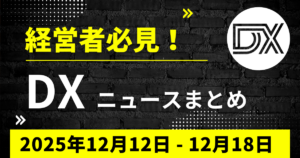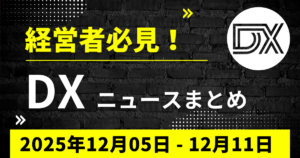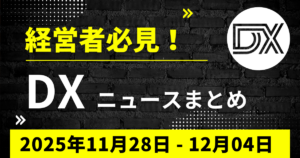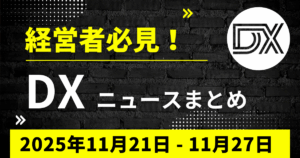DXニュースまとめ(2026年1月9日〜1月15日)
生成の現場でDXが進むとき、成果が出る会社には共通点があります。現場が使える形で“情報とデータ”を整えることです。2026年1月9日〜1月15日に公開されたDX関連ニュースを見ると、紙の規程類の電子化、現場を3D化して遠隔共有する取り組み、自治体DXのノウハウ共有、経費精算のAI自動化、そして脱炭素の「見える化」を支えるサービスなど、どれも“データを経営に活かす”方向に揃っています。
中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、①現場文書の電子化、②3Dデジタルツイン、③行政DXの標準化、④バックオフィスのAI化、⑤GXを支えるデータ基盤です。自社に置き換えながら読むと、次の打ち手が見えてきます。
1. 名鉄が「紙の規程」を電子化 現場が動くDXは“情報共有”から始まる
概要
名古屋鉄道(名鉄)は、乗務員向けの規程類や業務資料をデジタル化し、タブレットで一元管理できる仕組みを整えました。700ページを超える規程類を紙で配布していたため、改訂のたびに差し替え作業が発生し、紙の廃棄や携行の負担が課題になっていたそうです。そこで、オフラインでも閲覧でき、役職や担当に応じて閲覧権限を細かく設定できる文書共有基盤を採用。社用メールアドレスを持たない人にも配布しやすい点も含めて、現場で“使える”条件を優先しました。紙の削減だけでなく、必要な情報を検索してすぐ見つけられる状態を作ったのがポイントです。
中小企業への影響
中小企業のDXは、大きな基幹システムよりも「現場の情報がすぐ届く・すぐ探せる」状態を作るだけで、体感できる効果が出ます。例えば、作業手順書・品質基準・営業資料・社内ルールが紙や共有フォルダに散らばっていると、探す時間が増え、ミスや属人化が起きやすくなります。スマホやタブレットで見られ、更新が自動で反映される仕組みがあれば、教育の手間や問い合わせが減り、現場の判断が速くなります。特に、パート・アルバイト・現場作業者など「PCやメールが前提ではない」人が多い会社ほど、情報共有の差が業績に直結します。一方で、権限設計が甘いと情報漏えいリスクが増えるため、最初に「誰が何を見られるか」を決めることが重要です。
経営者の視点
経営者としては、DXを「業務アプリを増やすこと」と考えないほうがうまくいきます。まずは、社内の“紙・Excel・口頭”で回っている情報を棚卸しし、更新頻度が高いものからデジタル化するのがおすすめです。次に、現場の代表メンバーを巻き込み、使い方のルール(更新担当、版管理、緊急連絡の動線)を一緒に作ります。名鉄のように現場主導の改善プロジェクトが動くと、導入後の定着が一気に進みます。最初のゴールは「検索すれば必ず最新が出る」。この状態ができると、教育、理解度テスト、アンケートなど、周辺業務の改善へ自然に広げられます。
参考リンク
クラウド Watch:名鉄、紙の規程類・業務資料の電子化とDX推進にアステリアの「Handbook X」を活用
2. 点群・3Dモデルを“軽く”共有 デジタルツインが中小企業の現場改善を加速
概要
建設や製造などの現場を3Dデータ化するために、デバイスワークスが点群データ計測や3Dモデル作成のサービスを始めました。LiDAR(レーザーで距離を測る機器)で現場をスキャンして点群データを作るほか、写真や動画から「写真のように見える3Dモデル」を作る技術も使います。特徴は、Webブラウザーやスマホでも確認しやすい“軽量”データにできる点です。設計と現況のズレ確認、設備変更時の干渉チェック、遠隔教育、ロボットやAGVの走行シミュレーションなど、デジタルツイン(現場をデジタル上に再現したもの)の土台として使えるとしています。
中小企業への影響
現場型ビジネスでは「現地に行かないと分からない」がコストの塊です。3D化が進むと、社内の意思決定が速くなり、移動時間や手戻りが減ります。例えば、設備レイアウト変更の検討、保守点検の事前打ち合わせ、協力会社との工程調整などで、写真だけでは伝わらない“距離感”が共有できるのは大きな強みです。さらに、教育にも効きます。ベテランが現場で口頭説明していた内容を3Dで示せれば、理解が早く、引き継ぎの品質が上がります。一方で、3Dデータは資産であると同時に機密にもなり得ます。クラウド共有の範囲、持ち出し、取引先との取り扱いルールは必ず整備が必要です。
経営者の視点
経営者が考えるべきポイントは「3D化そのもの」より、どの工程の無駄を減らすかです。おすすめは、①現地確認の回数が多い業務、②手戻りが起きやすい業務、③教育に時間がかかる業務、のどれかに絞って試すこと。小さく始めて、移動回数や見積り精度、工期のズレ、教育時間など“お金に換算できる指標”で効果を見ます。効果が見えたら、図面管理や保全記録、IoTデータとつないでデジタルツインへ育てていく。導入時は「誰がスキャンするか」「データを誰が更新するか」まで決めておくと、形だけのツール導入で終わりにくくなります。
参考リンク
DIGITAL X:建設や製造などの現場の点群データや3Dモデルの作成サービス、デバイスワークスが開始
3. GovTech東京が自治体向け視察会 「行政DXの標準化」がビジネス環境を変える
概要
GovTech東京は、自治体職員向けに「視察オープンデー」を開催し、区市町村DXの取り組みや共同調達、デジタル人材育成、東京アプリ開発、生成AI活用などの事例やノウハウを共有するとしています。会場での説明に加え、オフィスツアーも行う予定で、自治体が単独で悩みがちな“進め方”を、横展開しやすい形にしていく動きです。行政のデジタル化は住民サービスだけでなく、調達や業務標準にも直結するため、民間側にとっても影響が大きいニュースです。
中小企業への影響
自治体のDXが進むと、企業側の手続きや取引の前提が変わります。例えば、補助金や許認可、入札関連の申請がオンライン化すると、紙提出や窓口対応にかけていた時間が減り、スピードが上がります。また、共同調達が広がると、自治体ごとに仕様がバラバラだったシステムやサービスが揃いやすくなり、「一度対応すれば他でも展開できる」世界に近づきます。中小企業にとっては、行政が求めるセキュリティ要件やデータ形式に早めに慣れておくことが、取引機会の拡大につながります。逆に、紙中心の業務のままだと、提出物のデータ化だけが“追加作業”になり負担が増えます。
経営者の視点
経営者としては、「行政のDXは自社と関係ない」と切り捨てないほうが得です。理由は2つあります。1つ目は、自社が自治体と取引しない場合でも、取引先が自治体案件を持つと、サプライチェーン全体に同じ要件が降りてくる可能性があること。2つ目は、行政手続きがデジタル化するほど、会社側も“提出できるデータ”を整えていないと手間が残ることです。まずは、社内の書類(見積書・請求書・契約書・各種証憑)をデータで出せる体制にし、保管ルールと権限管理を整える。さらに、担当者が変わっても回るように、申請フローを1枚にまとめておくと、外部環境の変化に強い会社になります。
参考リンク
INTERNET Watch:GovTech東京、自治体向け「視察オープンデー」を1月23日・3月6日に開催
4. 経費精算の“その先”へ AIで不正検知・自律運用が進むバックオフィスDX
概要
コンカーの橋本社長は、2025年に「経費精算をなくす」という目標が機能面で達成できたと振り返り、AIによる自動不正検知サービス「Verify」を含めて、入力レス・キャッシュレス・ペーパーレス・承認レス・運用レスという“5つのレス”が揃ったと説明しています。その上で2026年は、AIチャットによる問い合わせ対応や設定改善支援、分析支援などで導入・運用の負担を最小化する「自律運用」を進め、最終的には「データの民主化(誰でも必要な数字にアクセスできる状態)」へ向かう方針を示しました。経費データを起点に、出張旅費分析や業務ボトルネック分析、サステナビリティ関連のスコアリングまで広げる考えも語られています。
中小企業への影響
バックオフィスは、売上を直接生まない一方で、ミスが起きると損失が出やすい領域です。経費精算のDXが進むと、①入力や確認の手間が減る、②不正やミスを早期に見つけられる、③データが溜まり意思決定に使える、という3つの効果が出ます。中小企業では「人が足りないから後回し」になりがちですが、実は少人数ほど効果が大きい分野です。注意点は、ルールが曖昧なままツールを入れると混乱すること。例えば、立替の範囲、承認基準、領収書の扱いが揃っていないと、入力レスどころか問い合わせが増えてしまいます。
経営者の視点
経営者がやるべきは、まず“経費精算を経営の数字にする”ことです。月次で、交通費・交際費・サブスクなどの内訳を見て、ムダや偏りを把握できるだけでも利益率が変わります。その上で、運用を軽くするコツは「例外を減らす」こと。承認ルートをシンプルにし、よくある支出はテンプレ化する。AIの不正検知や自動分類を活かすには、入力項目や勘定科目の設計が土台になります。最初から完璧を狙わず、1〜2部門で試し、現場の声を拾ってルールと仕組みを一緒に整える。この進め方が、バックオフィスDXを“定着する成果”に変えます。
参考リンク
クラウド Watch:「築いてきた信頼と伴に、AI時代の翼になる」コンカー橋本社長に聞く、2025年の到達点と2026年の次の一手
5. CO2見える化支援サービス開始 GXも“データ化”が前提になる時代へ
概要
京葉銀行、伊藤忠丸紅鉄鋼、NTTドコモビジネスの3社は、中堅・中小企業向けにCO2排出量の測定から削減、成果活用までを支援する「αBANK GX ソリューション」を開始しました。CO2の可視化(見える)、算定や法規制・ESG戦略の相談(教えて)、エネルギー消費に伴う排出量削減の支援(減らせる)、取り組み成果を資金調達や採用、営業、PRに活かす(活かす)という4つのメニューで構成されます。中小企業は専門知識や人手が不足し取り組みが進みにくい、という課題認識も示されています。
中小企業への影響
GX(脱炭素)というと製造業だけの話に見えますが、実際は業種を問わず「取引の条件」になりやすいテーマです。大企業がサプライヤーに排出量の情報提供を求める動きが強まると、データを出せない会社は商談で不利になります。逆に、数字を出せるだけで信頼が上がり、融資や採用でも説明材料になります。ここで重要なのがDXです。電気・ガス・燃料・物流などのデータを集め、同じルールで記録し、社内で回せる仕組みにして初めて、CO2算定が“作業”から“経営管理”になります。さらに、支援サービス側もDXの知見を持つ事業者と連携しているため、単なる算定ツールではなく業務の回し方まで含めて見直すきっかけになります。今のうちに備えたいところです。
経営者の視点
経営者としては、脱炭素を「追加の義務」と捉えるより、「原価の見える化」と捉えると動きやすくなります。まずは、エネルギーコストの大きい拠点・工程を特定し、月次で数字を揃える。次に、改善策(設備更新、運用見直し、物流の効率化など)を少数に絞って試し、削減効果を数字で確認します。ここまでできれば、金融機関や取引先に“根拠ある説明”ができます。GX支援サービスを使う場合も、丸投げではなく、社内に「データの入口(入力)と出口(報告)」の担当を置くことが成功のカギです。
参考リンク
SmartGridフォーラム:中小企業のCO2算定から成果活用まで支援、京葉銀行・伊藤忠丸紅鉄鋼・NTTドコモビジネスが協業
まとめ
今回取り上げた5つのニュースは、業界は違っても「DXはツールではなく、運用とデータの整備で決まる」ことをはっきり示しています。紙を減らす、現場を3Dで共有する、手続きをデータで出せるようにする、経費を数字で管理する、CO2を見える化する――どれも“最初の一歩”は小さいのに、積み上げると競争力になります。
明日からできる行動としては、次の3つがおすすめです。
- 社内で探す時間が多い資料を1つ選び、最新版が必ず出る場所を決める
- 移動や手戻りが多い現場業務を1つ選び、写真・図面・3Dなど「共有の型」を作る
- 経費やエネルギーなどの数字を月次で揃え、改善の打ち手を“数字で”検討する
DXは、始めるのが早い会社ほど学習が進みます。まずは「情報が迷子にならない状態」から整えていきましょう。