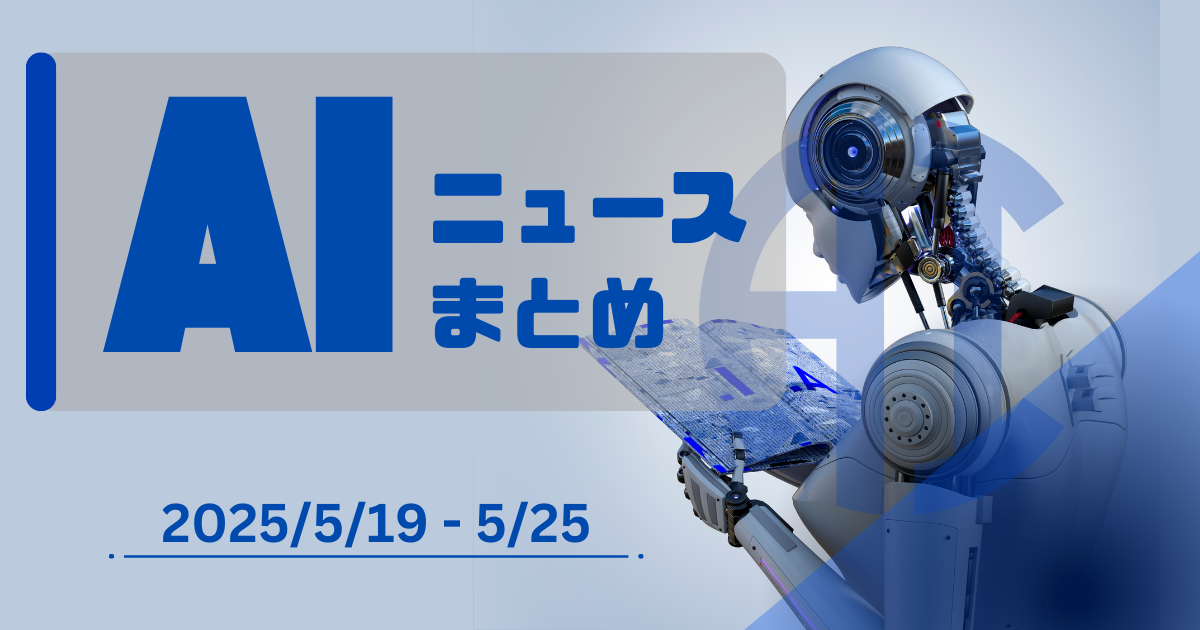生成AIニュースまとめ(2025年5月19日〜5月25日)
2025年5月19日から5月25日にかけて、日本国内では生成AI(Generative AI)に関する様々なニュースが報道されました。グローバル企業の発表から国内での具体的な活用事例まで、生成AIの進化と影響を感じさせる話題が目白押しです。中小企業の経営者にとっても無関係ではありません。生成AI技術の最新動向や活用事例を知ることで、自社の業務効率化やビジネス戦略に役立つヒントが得られるかもしれません。
そこで、本記事では上記期間に報じられた生成AI関連の注目ニュース5件をピックアップしました。それぞれのニュースについて、概要と中小企業への影響、経営者の視点を分かりやすくまとめています。ぜひ今後の経営のヒントとしてお役立てください。
1. Google、生成AIモデル「Gemini 2.5 Pro」に深く考える新機能「Deep Think」を発表
概要
米Google社は開発者会議「Google I/O 2025」にて、自社の生成AIモデル「Gemini 2.5 Pro」に関する新機能を発表しました。中でも注目されたのが、AIが回答する前に複数の仮説を検討する新モード「Deep Think」です。これにより、AIがより深く推論し、複雑な問題にも高精度で答えられるようになるといいます。また、AI音声応答の話し方やトーンをプロンプトで指定できる機能も導入され、ユーザーはAIの話し方(アクセントやスタイル)を自由に調整可能になりました。さらに、短い動画を音声付きで自動生成する新モデル「Veo 3」も発表されており、テキストからナレーション付きの動画コンテンツを作るといった応用も視野に入っています。
中小企業への影響
Googleの最新AI機能は一見最先端過ぎて中小企業には直接関係ないように思えるかもしれません。しかし、こうした技術進化は今後、中小企業が日常的に使うツールやサービスにも組み込まれていく可能性があります。例えば、より高度な推論ができるAIは、これまで専門家に依頼していたような分析業務を自動化・効率化するツールにつながるかもしれません。また、生成AIによる動画コンテンツ生成は、少ないリソースでプロモーション動画や教育コンテンツを作成する助けになる可能性があります。AIの話し方調整機能も、将来的に顧客対応の自動音声アシスタントなどに応用されれば、自社のブランディングに合った話し方で自動応答させることができるかもしれません。総じて、大企業発のAI技術革新は、中小企業にも新たなツールや機会をもたらす可能性があると言えるでしょう。
経営者の視点
経営者として注目したいのは、検索エンジンへの生成AI統合です。Googleは検索結果に生成AIを活用する実験も進めており、将来的にユーザーが検索した際にAIが質問に直接答えるようになるかもしれません。これはSEOにも影響を及ぼす可能性があります。自社サイトへの集客戦略も、AIによる要約や直接回答が一般化すれば、従来のキーワード対策だけでは不十分になる可能性があります。今後の検索動向を注視しつつ、ユーザーにとってより価値の高いコンテンツを提供することが一層重要になりそうです。また、最先端の生成AI技術といっても、時間が経てばクラウドサービスや手頃なソフトウェアとして利用できるようになるかもしれません。小規模企業でも使えるAIツールが出てきた際に備え、今から情報収集し試してみる姿勢が、将来の競争力につながるでしょう。
参考リンク
- Impress Watch(PC Watch):「Google、Gemini 2.5 Proが複数の仮説を検討可能に。AI音声の話し方も指定可能に」
- マイナビニュース:Google I/O 2025 注目の発表まとめ(音声付き動画生成モデル「Veo 3」など)
2. マイクロソフト、Build 2025でAIエージェントの新機能を多数発表
概要
米マイクロソフト社は5月19日〜22日に開催した年次開発者会議「Microsoft Build 2025」において、生成AIを活用した多数の新機能を発表しました。今回のBuildは「AIエージェントの時代」がテーマとされ、発表内容も終始AI関連で占められました。特に注目すべきポイントは以下のとおりです。
- マルチエージェントの協働: 複数のAIエージェントがタスクを分担・連携できる新機能「Multi-agent orchestration(マルチエージェントオーケストレーション)」が発表されました。例えば社内の新人研修手続きを、総務・経理・法務など複数部門のエージェントが協力して自動処理する、といった複合的な業務フローをAIでまとめて実行できるイメージです。
- 企業独自データでのAIチューニング: 「Microsoft 365 Copilot」において、企業が自社のデータや用語を使って生成AIを調整(ファインチューニング)できる新機能「Copilot Tuning」が公開されました。これにより、AIが自社の業界用語やスタイルに沿った回答を返すことが可能になります(まずは大企業向けの早期アクセス提供)。
- 高度なAIモデルの活用強化: マイクロソフトのクラウドAIプラットフォーム「Azure AI Foundry」に、さらに高度な外部AIモデルが組み込まれることも発表されました。例えば、OpenAIの動画生成モデル「Sora」をはじめとする最新モデルがクラウド経由で利用可能になり、セキュリティ強化や開発者向けツールの充実も図られています。
中小企業への影響
マイクロソフトが発表したこれらの機能は、一見すると大企業や開発者向けの高度なものに感じられるでしょう。しかし、中小企業にも将来的に影響を与え得る重要なトレンドです。マルチエージェントの協働は、今後ソフトウェアやクラウドサービスとして提供されれば、複数の業務プロセスをまとめて自動化することが可能になるかもしれません。例えば、見積作成から請求書発行、在庫引当まで、異なる部署の処理をAIエージェント同士が連携して進めるような未来も想像できます。また、企業独自データでAIをチューニングできるようになると、これまで大企業しか扱えなかったようなオーダーメイドAIが、中小企業でも利用できる日が来る可能性があります。自社の蓄積データ(顧客データや業務マニュアルなど)を活かしてAIがお客様対応や資料作成をしてくれるようになれば、少人数でも高度なサービス提供が可能になるでしょう。
経営者の視点
経営者として注目すべきは、「自社に適したAIを作れる時代」が近づいているという点です。今回マイクロソフトが示した方向性から、標準化されたAIツールをそのまま使うだけでなく、自社の業務にフィットするようAIを調整・活用する流れが見えてきます。中小企業にとって、自社専用にAIを開発するのはハードルが高いように思えますが、クラウド経由で容易にチューニングできる仕組みが普及すれば、身の丈に合ったカスタマイズAIが手に入るかもしれません。経営者の視点では、「AI活用=大企業だけのもの」と決めつけず、発表された新機能の動向をウォッチしておくことが大切です。特にマイクロソフトの製品(Office365やTeamsなど)を利用している企業は、今後数年でこれらのAI機能が統合される可能性があります。自社でも使えるときが来たらどう活かすか、今から社内でアイデアを出し合ったり試験的に触れてみたりすることで、先行者利益を得られる準備をしておくと良いでしょう。
参考リンク
3. アンソロピック、最新生成AIモデル「Claude 4」を発表 – 長時間の自律動作が可能に
概要
米国の新興AI企業Anthropic(アンソロピック)は5月22日、対話型生成AI「Claude(クロード)」シリーズの最新モデル「Claude 4」ファミリーを発表しました【注: 日本国内メディアによる報道】。今回発表されたのは大規模モデル「Claude Opus 4」と、小型でコスト効率に優れた「Claude Sonnet 4」という2種類です。最大の特徴は、AIが非常に長時間にわたり自律的にタスクを実行できる点です。従来モデルに比べ、コード(プログラム)を書き続けられる持続時間が飛躍的に伸びており、なんと数時間にわたって自律的にコーディングが可能だといいます。実際、日本企業の楽天が「Claude Opus 4」に約7時間もの連続コーディングを実行させる実験を行い、その持続的な作業能力を示しました。また、ゲームのポケットモンスターを24時間ノンストップでプレイさせるデモも披露され、前世代モデル(約45分間の持続動作)から格段の進歩を示しています。新モデルは質問に対し即答もじっくり推論もでき、インターネット検索を行いながら回答を作ることも可能です。併せて、今年2月に開発者向けに提供を開始したコード支援ツール「Claude Code」が一般利用可能になったことも発表されました。総じて、Anthropicは生成AIの自律性と持続性を大きく向上させた形です。
中小企業への影響
Anthropicは日本ではOpenAI(ChatGPTの開発元)ほど知名度は高くないかもしれませんが、世界的には有力なAI企業であり、大手テック企業からの出資も受けています。今回の発表は、生成AI同士の競争が激しく進んでいることを示しています。中小企業にとって、この競争の直接的な恩恵はAIサービスの高機能化と多様化として現れてくるでしょう。例えば、今回のClaude 4のように長時間自律動作できるAIがクラウドサービスとして提供されれば、夜間にAIが自動でデータ分析やコード修正を続け、朝には結果が出ている…といった使い方も夢ではなくなります。また、小型モデルのSonnet 4はコスト効率に優れるとされており、予算が限られる企業でも手の届く高度AIが今後登場する可能性があります。重要なのは、生成AIの能力が日進月歩で向上している点です。数年前には難しかった長時間のタスクも今や可能になりつつあり、これによりこれまで自動化できなかった業務領域にもAIが活用できる余地が広がっています。
経営者の視点
経営者としては、生成AI業界の動向を戦略的に捉えることが大切です。Anthropicを含む各社がしのぎを削ることで、AIの性能はさらに向上し、サービス利用料も競争原理で適正化されていくでしょう。これは、中小企業がより強力なAIツールをより安く使えるチャンスが増えることを意味します。一方で、AIの高度化は業務の自動化・効率化の可能性を飛躍的に高める反面、従来の仕事のあり方にも影響を与えます。例えば「数時間自律的にコーディングできるAI」が実現すれば、システム開発やデータ処理のスピードが格段に上がる一方で、人間の担当範囲が変わる可能性もあります。経営者は、自社の事業分野でAIがどのように活用できそうかを常に考え、社員のスキルアップや業務設計の見直しを進める必要があるでしょう。今回楽天が先行して新型AIをテストしているように、日本企業も含め各社が最新AIを試しています。自社でも試験的に新しいAIサービスを触ってみるなど、小さな一歩から始めてみるのも良いかもしれません。未来の変化に備え、柔軟にテクノロジーを取り入れる姿勢が求められています。
参考リンク
4. 姫路市、生成AI活用で議会答弁作成を10分の1の時間に短縮
概要
兵庫県姫路市において、生成AIを活用した業務効率化が大きな成果を上げています。クラウドサービス企業のFIXERは5月21日、姫路市職員を対象に行った生成AI利用に関するアンケート結果を発表しました。同市では2024年7月より、FIXER社のエンタープライズ向け生成AIサービス「GaiXer(ガイザー)」を導入し、職員の事務作業効率化に取り組んできました。その結果、調査対象となった職員の約68%が週1回以上生成AIを業務で活用しており、文章作成や要約、議事録作成、情報検索など幅広い用途で利用が進んでいることがわかりました。特筆すべきは、85%もの職員が「時間短縮効果を実感した」と回答している点です。実際、具体的な業務で以下のような大幅な時間短縮が報告されました。
- 議会答弁原稿の作成: 草案や答弁要旨の準備にかかる時間が、従来の約10分の1に短縮
- 文書要約・議事録作成: 2時間かかっていた作業が15分で完了
- Excelマクロ(VBA)コードの作成: 約1時間要していた作業が30分に短縮
- 教育委員会のアンケート結果分類: 約237時間かかっていた集計・分類作業が約50時間で完了(※大半は個人情報マスキングの作業時間)
アンケートの自由回答では、「繰り返しの単純作業から解放される」「業務効率が上がり本来業務に集中できる」など前向きな声が多く、職員たちは生成AIによる効果を実感しています。姫路市ではこの結果を受け、職員間での活用事例共有や研修の充実など、さらなる利用促進策を講じる予定とのことです。
中小企業への影響
姫路市の事例は、公共団体における生成AI活用の成功例ですが、そのインパクトは中小企業にも当てはまるものです。議会答弁の原稿作成という行政特有の業務に限らず、文章作成、要約、議事録、プログラミングなど、どの組織にも存在する事務作業で生成AIが大きな効果を上げたことが示されました。中小企業でも、例えば社内会議の議事録作成や提案書の下書き、メール対応、簡易なプログラミング作業(Excelのマクロ作成など)に、多くの時間を割いているケースは少なくないでしょう。生成AIを上手に活用すれば、これらの反復的な作業を劇的に効率化できる可能性があります。実際に姫路市では業務時間が何十分の一にも短縮されていますから、中小企業でも人手不足の解消やサービスの迅速化に繋げるチャンスです。また、この事例は職員の多数がAIを使いこなしている点も重要です。中小企業においても、一部のIT担当者だけでなく幅広い社員がAIツールを使えるよう支援すれば、組織全体の生産性向上が期待できます。
経営者の視点
このニュースから得られる教訓は、「まず試してみることの重要性」です。姫路市では昨年から生成AIツールを導入し、効果測定まで行っています。中小企業の経営者も、「うちの会社でも使えるのか?」と悩むより、小さく試行導入してみることで得られるものが大きいでしょう。幸い、最近ではChatGPTや各種生成AIサービスが手軽に利用できます。まずは社内で数人のチームを作り、議事録作成や社内文章の要約に試験的に使ってみる、といったことから始めてはいかがでしょうか。重要なのは、姫路市が今後計画しているように、社内で活用ノウハウを共有し合うことです。経営者が率先して「こんな風に使ったら時間が浮いたよ」と情報共有する場を設ければ、従業員も安心してAIを活用できるようになります。ただし、業務でAIを使う際は情報セキュリティや誤答のリスクにも注意が必要です。姫路市が採用したような企業向けの安全なサービスを使う、あるいは機密情報は入力しないルールを決めるなど、適切な配慮も忘れずに。総じて、経営者自らが生成AI活用の旗振り役となり、効率化の文化を作っていくことが、これからの時代に求められる姿勢と言えるでしょう。
参考リンク
5. 日本木材、生成AI活用で在庫確認や営業先提案を効率化
概要
社内のデータ分析に生成AIを活用し、中小企業ならではの課題解決に取り組んでいる企業があります。東南アジア産木材を扱う専門商社「日本木材」(大阪府堺市)では、2代目代表取締役の長谷部愛さんが生成AIツールを業務に積極導入して営業効率化を図っています。長谷部さんは元ITエンジニアという経歴もあり、GeminiやClaudeといった最新の生成AIを試行的に取り入れてきました。中でも効果を実感しているのが、自社の蓄積データをAIに分析させて営業のヒントを得るという使い方です。具体的には、過去の販売データや顧客情報をAIが分析し、「次にどのタイミングでどの取引先に営業をかけるべきか」を提案してくれる機能や、倉庫に眠っている滞留在庫を洗い出すといった使い方です。「感覚的に気づいていたことを、AIが数値で明示してくれるので感動した」と長谷部さんは語っており、属人的な勘に頼っていた営業判断がデータドリブンに変わりつつあるようです。また、チャット形式でAIに質問すると、社内資料から必要な情報を探し出して回答してくれるため、社員が調査や報告書作成に費やす時間も削減できているといいます。日本木材のように中小企業が自社データと生成AIを組み合わせて活用する先進事例は、今後増えていくことが期待されます。
中小企業への影響
この日本木材のケースは、中小企業でも生成AIを活用して成果を上げられることを示す好例です。ポイントは、自社の業務データという「宝の山」をAIに分析させている点です。中小企業でも日々の営業記録や在庫データ、お客様からの問い合わせ内容など、蓄積されたデータがあります。それらを人手で分析するのは大変ですが、生成AIであれば短時間でパターンや異常値を洗い出し、ビジネスチャンスや改善点を提案してくれる可能性があります。特に営業面では、「どの顧客に何を提案すべきか」「アプローチすべき適切なタイミングはいつか」といった判断にAIの知見を加えることで、経験の浅い担当者でも効果的な営業活動ができるよう支援してくれるでしょう。また、在庫管理でも、売れ残りがちな商品や季節変動の分析などにAIを用いれば、在庫回転率の改善や無駄な仕入れの削減につながる可能性があります。中小企業は大企業に比べリソースが限られますが、だからこそ安価または無料で使える生成AIツールを賢く使うことで、大企業並みの分析力を手に入れられるかもしれません。この事例は「ITの専門知識がなくても工夫次第でAIを使いこなせる」ヒントにもなります。
経営者の視点
経営者として学ぶべきは、トップ自らが新技術に興味を持ち試してみる姿勢です。日本木材の長谷部社長はエンジニア出身とはいえ、中小企業の経営者が自ら生成AIを色々と試し、具体的な業務改革に結びつけている点は注目に値します。必ずしも経営者自身が技術に詳しくなる必要はありませんが、社内に詳しい人材がいるなら任せてみる、外部の専門家に相談するなどして、新しいITツールを取り入れる柔軟性を持つことが大切です。生成AIは使い方によっては経営者の意思決定をサポートする「参謀」にもなり得ます。例えば売上データの傾向をAIに尋ねれば、客観的な視点での分析結果が得られ、今後の戦略立案に役立つでしょう。また、この事例では「繰り返しの作業から社員を解放したい」という思いも導入の背景にあります。経営者にとって人材は貴重な資源ですから、AIに任せられる作業は任せて、社員には創造的な業務や顧客対応に集中してもらうという発想は、生産性向上と従業員満足の双方にプラスです。まずは小さく試し、良いところはどんどん取り入れる。そんな前向きな姿勢が、中小企業がこれからの技術変化についていく上で重要だと言えるでしょう。
参考リンク
- 朝日新聞デジタル(ツギノジダイ):「生成AIがデータから在庫確認・営業先を提案 日本木材2代目の活用法」
- ITmedia ビジネスオンライン(参考記事):「生成AIの普及で『デジタル人材』に求められるスキルはどう変わるのか」
まとめ
以上、2025年5月19日〜5月25日に報じられた生成AIに関する注目ニュース5件をお届けしました。大手テクノロジー企業の発表から地方自治体・中小企業での活用例まで、生成AIは様々な分野で急速に進化し普及しつつあることが分かります。特に、小規模な組織でも創意工夫次第でAIの恩恵を受けられるという点は、中小企業の経営者にとって希望が持てるポイントではないでしょうか。
もちろん、新技術には課題やリスクも伴います。情報漏えいや誤った出力への対応など、慎重さも必要です。しかし、現状に留まっていては競争に遅れをとる可能性があります。大切なのは最新情報にアンテナを張りつつ、自社で実践できる範囲から取り入れてみることです。例えば今回ご紹介したニュースをきっかけに、社内で「うちではどれが活用できそうか?」と話し合ってみるのも良いでしょう。小さな一歩でも踏み出すことで、やがて大きな差となって現れるかもしれません。
生成AIは今後もビジネスの在り方を変えていくと予想されます。中小企業にとっても他人事ではなく、自社の成長や効率化の強力なツールになり得る存在です。ぜひ最新動向をチェックしながら、前向きにチャレンジしてみてください。あなたの会社ならではのAI活用アイデアが、次の成功ストーリーを生むことを期待しています。