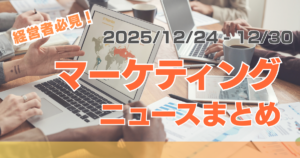マーケティングニュースまとめ(2025年8月13日〜8月19日)
マーケティング領域では、実務に直結する更新が相次ぎました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは「韓国向け広告の取り扱い開始による越境プロモーション強化」「インフルエンサー素材のサブスク提供」「LINEと連動した“軽ギフト”サービスの登場」「物価高に伴う節約志向の鮮明化」「複数SNS併用の常態化」です。どれも集客コストの最適化や顧客体験の再設計に直結します。本記事では、要点と実務での使い方を“経営者視点”で解説します。
1. 韓国広告の本格取り扱いで“訪日需要”を先回り──サイバーエージェントが越境プロモーションを強化
概要
サイバーエージェントは8月19日、韓国の主要広告媒体の取り扱いを開始し、日本企業のインバウンドマーケティング支援を強化すると発表しました。現地の配信面や運用ノウハウを国内から一括で提供することで、韓国の生活者に対して訪日前(計画・予約)/訪日中(地図・検索)/帰国後(ロイヤル化)をつなぐ一気通貫のコミュニケーションが可能になります。観光・小売・EC・エンタメなど、訪日回復が進む分野で、指名検索の創出や店頭送客、EC越境の後押しが期待されます。韓国は日本との距離が近く短期旅行も多いため、意思決定から来店までの“移動時間”が短いのが特徴です。スピード重視の訴求が有効になります。
中小企業への影響
これまで海外広告は言語・決済・配信設計の壁から大手中心でしたが、国内代理店経由で契約・課金・レポートが完結できると参入障壁が下がります。地方の宿泊・体験事業者は「事前予約クーポン×地図広告」、物販は「越境EC×レビュー訴求」で、現地での露出から来店・購入までを短い動線で結べます。注意点は、文化・法規に配慮した表現(医薬品・美容表現の規制差、飲酒年齢など)、即時翻訳に頼りきらないコピー制作、オフライン計測(レシート連携・Wi-Fi来店計測)を組み合わせた効果把握です。価格表示は通貨・税込の明確化、返品・免税の条件提示も信頼につながります。
経営者の視点
最初の一歩は“小さく素早く検証”です。①韓国語LPを用意(決済・配送・利用条件を明記)②店舗側は韓国語POP/決済QR/レビュー誘導の整備③キャンペーンは2週間単位で仮説検証(地域・年齢・興味で配信分割、駅名・観光地名キーワード活用)④KPIは“来店・購買・再訪”の3指標で追跡――という順で回すと無駄が出にくくなります。四半期ごとに学びをまとめ、クリエイティブ・入店導線・スタッフ対応の“三位一体”で改善しましょう。
SNSでの発見(旅行記・グルメ動画)→地図アプリでの比較→予約・決済という行動連鎖を前提に、同一ビジュアルと言語で“追いかける”設計が鍵です。特にモバイルは回線事情で離脱が起きやすいため、画像軽量化・決済手順の短縮・チャット対応の即応を徹底しましょう。 また、現地口コミサイトや地図評価への返信体制を整え、“来日前の不安解消”に寄り添う姿勢を示すと成果が伸びやすくなります。
参考リンク
MarkeZine:サイバーエージェント、韓国の広告媒体の取り扱いを開始 インバウンドマーケティング支援を強化
2. クリエイター素材を“定額”で──Wunderbarが「Skettt Influencer」を提供開始
概要
8月19日、Wunderbarはインフルエンサーの宣伝素材を月額で利用できる「Skettt Influencer」を発表しました。広告・SNS運用担当者は、インフルエンサーの投稿や動画の二次利用、販促バナーやEC商品ページなどに展開できるクリエイティブを契約範囲内で効率よく活用できます。素材の配布・更新を管理する仕組みにより、制作スピードの平準化とクリエイティブの一貫性向上を狙うサービスです。企業側は“素材を選ぶ→編集→配信→測定”の流れを短縮でき、反応が良い表現を素早く横展開できます。
中小企業への影響
撮影や編集をスポット発注するより、サブスクで“必要な時に必要なだけ”使えるのは人手が限られる現場に相性がよいです。トンマナが合う素材を選び、CTAや価格表記だけ差し替える運用にすると、A/Bテストの回転が速くなります。ただし、同一素材の過度な使い回しは効果減衰につながります。新商品・季節要素・ユーザーレビューを絡めた差分を定期投入し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)と混ぜて“他人事ではない”実感を作ることが欠かせません。自社のブランド資産(ロゴ・色・言い回し)を簡単に差し替えられるテンプレート運用にすると、属人化を防げます。
経営者の視点
契約・利用範囲(媒体、地域、期間、二次利用の可否)と、肖像・著作・商標の権利処理を必ず確認しましょう。CVRだけでなく、保存率・プロフィール遷移・検索リフトといった中間指標もダッシュボード化し、素材ごとの“役割”を見極めます。たとえば「認知用:3秒視聴率」「比較用:保存率」「購入直前:サイト遷移率」のように目的別KPIを設定し、週次で入れ替える体制にすると少人数でも成果が積み上がります。 また、インフルエンサーの素材は“文脈”が命です。薬機法・景表法に抵触しない文言チェック、誇大表現の禁止、レビューと広告の区別の明示(タイアップ表記)は必須です。ブランドセーフティの観点から、炎上時の差し替え基準と運用責任者を事前に決め、緊急時の停止・入替までをワークフロー化しておくと被害を最小化できます。 最後に、素材の“寿命”を見える化し、効果が落ち始めたら新作に入れ替える更新規律を持つことで、費用対効果を安定させられます。 素材は“売れ筋×季節×用途”の3軸で棚卸しし、常に入替候補を用意しておくと運用が止まりません。
参考リンク
MarkeZine:Wunderbar、「Skettt Influencer」提供 インフルエンサーの宣伝素材を月額利用
3. スタンプとお酒を贈る“軽ギフト”──サントリーがLINE発の新サービス「ノンデネ」を開始
概要
8月19日、サントリーはLINEスタンプと連動したソーシャルギフト「ノンデネ」を開始しました。日常の「ありがとう」「ごめんね」など小さな気持ちを、メッセージ性のあるスタンプと一緒にドリンクチケットとして贈れる仕組みで、購入から受け取りまでがLINE上で完結します。ギフトのカジュアル化を追い風に、ブランドの想起機会を増やし、体験を通じたファン化を狙う動きです。ギフト単価が低くてもタッチポイントが増えるため、ボトル購入や店舗来訪につながる“入口”として機能します。
中小企業への影響
“高価な贈り物”だけでなく、“ちょっとしたお礼”の需要をすくい上げる設計は、飲食・小売・サービスの来店導線に応用できます。例えば、回数券・試飲チケット・体験クーポンなどをデジタルギフト化すれば、客単価が大きくなくても接触回数を積み増せます。注意点は未成年・飲酒運転への配慮、利用期限や対象店舗の明確化、受け取りフローのわかりやすさです。受け取り場所が限定される場合は、地図リンクと混雑回避の案内を合わせて提示すると離脱を防げます。
経営者の視点
ギフト経由の“初回接触”をLTVに変える仕掛けを重ねましょう。受け取り後のアンケートで好みを把握→次回来店クーポンや限定メニューの提案→SNSでの共有導線、のように体験を連鎖させます。顧客データは“贈る人・贈られる人”の2軸で分析し、紹介プログラムの種として活用するのが有効です。販促カレンダーに合わせ、季節イベント(例:送別・合格・父の日)用のテンプレートを用意しておけば、少人数でも継続運用しやすくなります。 加えて、POSや予約システムと連携し、来店時に自動でチケット消込ができるようにすると現場の手間が減ります。不正利用の防止には、スクリーンショット対策やワンタイムコード、譲渡可否の明示が有効です。法人利用では、取引先への“ちょいギフト”として使えるメッセージテンプレートを用意し、社内稟議なしで使える金額帯に設定すると活用が進みます。ギフトは広告と異なり“感情に紐づく体験”です。顧客の喜びの声を収集し、次の企画・商品開発に反映することで、継続的なファン創出につながります。 店舗周辺での回遊を促すため、受け取り画面に“近隣おすすめ”を掲出するなど、地域連携の仕掛けも効果的です。
参考リンク
MarkeZine:LINEスタンプとお酒で気持ちを届ける サントリーの新ソーシャルギフトサービス、「ノンデネ」開始
4. 物価高で“節約モード”鮮明──デロイトの消費動向調査が示す支出シフト
概要
デロイト トーマツ グループは8月19日、食料品の消費金額が増えた理由として67.4%が「物価高」と回答した調査結果を公表しました。節約志向の高まりで外食や旅行への支出に減速感がみられ、家計は“必要消費”へ重心を移しています。物価上昇や実質賃金の伸び悩みを背景に、生活者は「価格に見合う価値」をより厳しく見極めています。価格だけでなく、量・栄養・保存性・時短性といった“総合価値”の評価が進んでいるのがポイントです。
中小企業への影響
値引き一辺倒は利益を毀損します。鍵は“価値の再定義”です。同じ価格でも、耐久性・詰替え・メンテの容易さ・健康・安心・購入体験など、どこに価値を置くかで選ばれ方が変わります。小売はまとめ買いセットや定期便で手間を削減、外食はハーフサイズやセットの最適化、ECはレビュー強化と返品の容易さで“失敗コスト”を下げると選ばれやすくなります。広告では“節約の言語”――長持ち、無駄が出ない、時間短縮――を明確に打ち出しましょう。
経営者の視点
短期は「既存顧客の維持」と「離脱防止」に注力を。RFMで優良層を抽出し、リピート特典やメンテ無料など“現金価値以外の価値”を設計します。中期は商品ラインの再編成です。同一カテゴリ内で“良い・ほどほど・お試し”の三階建てを用意し、顧客が無理なく上げ下げできる価格の階段を作りましょう。原価高が続く前提で、仕入れ・製造の最適化やロス削減も並行して進めると、利益率がぶれにくくなります。 さらに、比較サイトやSNSでの“買う理由の納得感”が購入を左右します。値上げ時は理由と還元策(容量・品質・保証・アフター)を正直に説明し、FAQや店頭POPで疑問を潰すのが得策です。外食は“ごはんを減らせる”“子どもとシェアしやすい”などの具体表現が効きます。コミュニティ作りも有効です。レシピ・使い切り術・長持ちのコツを顧客と共有すれば、価格以外の接点が生まれます。データでは、客単価だけでなく“頻度×継続月数”を重視して日次でモニタリングし、小さな悪化兆候(来店間隔の伸び)に早めに手を打ちましょう。 最後に、プロモーションは“短期の値引き”より“長期の使い勝手”を伝えるコンテンツに軸足を置き、指名検索の増加と解約率の低下で効果を測るのが現実的です。
参考リンク
MarkeZine:デロイト調査、食料品の消費金額増加に67.4%が「物価高」と回答 節約志向が高まり外食・旅行に減速感
5. 複数SNSの“使い分け”が常態化──フラー調査、X/TikTok利用者の約8割がInstagramも併用
概要
マーケティング支援を手がけるフラーの調査によると、XやTikTokのユーザーの約8割がInstagramも併用していることがわかりました(8月19日公表)。生活者は目的に応じてプラットフォームを切り替え、発見は短尺動画、比較は検索・保存、購入前はレビュー視聴というように行動が分散しています。単一チャネル依存は届かないリスクが高まり、プランニングの前提が「マルチタッチ」に移ったと言えます。注目すべきは、同じコンテンツでも媒体によって“勝ち筋”が異なる点です。
中小企業への影響
“全部やる”のではなく、主軸(例:Instagram)+発見(TikTok)+検索(Google/YouTube)の三層構成が現実的です。各層に役割を割り当て、指名検索と比較導線に一貫したメッセージを配置することで、少額でもコンバージョン率を底上げできます。計測は“最後の接点”だけでなく、保存率・プロフィール遷移率・検索リフトといった中間指標も追いましょう。競合の“保存される投稿”を観察し、構図・テロップ・尺・音の要素を分解して真似するところから始めれば、短期で改善が進みます。
経営者の視点
編集負荷を抑えるなら“1素材×3展開”です。縦動画を核に、Instagramは商品理解、TikTokは体験の楽しさ、YouTubeは比較・レビューという“役割編集”で露出を最適化。コメント返信やDMの初動を自動化し、問い合わせから予約・購入までの導線を切らさない体制を作ると成果が積み上がります。アルゴリズム変更に備え、メールやLINE公式など“自社オウンド”にも必ず流し、プラットフォーム依存度を下げることが持続的な成長につながります。 投稿運用は“カレンダー×ライブラリ化”が効率的です。よく聞かれる質問、使い方、ビフォーアフター、お客様の声をテンプレ化し、週ごとに順番に回すだけでも成果は出ます。制作はスマホ中心で十分。撮影→文字入れ→字幕→書き出しの手順を標準化し、同じ素材から静止画・ショート・ロングの3種を作れば、更新頻度と質を両立できます。 有料配信は“主軸2・発見1・検索1”の比率から始め、頻度上げすぎによる広告疲れを避けるため、クリエイティブを週次でローテーションすると安定します。 フォーマットごとに“何をもって成功か”を言語化し、週次で小さく改善する体制が成果の再現性を高めます。
参考リンク
MarkeZine:SNS併用が当たり前に、X・TikTokユーザーの約8割がInstagram利用〖フラー調査〗
まとめ
今回のポイントは、①越境プロモーションの“実装可能性”が高まったこと、②制作と配信のスピードを上げる仕組みが整いつつあること、③生活者の節約志向とマルチタッチ前提でコミュニケーション設計を見直す必要があること、の3点です。まずは小さくテストし、効果の出た打ち手に予算を集中させましょう。
経営者としては、チャネル設計(主軸・発見・検索)を明確化し、KPIを“来店・購買・再訪”の3本柱で管理することが近道です。さらに、ギフトやUGCなどの“体験を伴う接点”を増やし、短期の販促だけでなく中長期のLTV最大化を狙ってください。
次回も、意思決定に役立つマーケティングニュースをわかりやすく解説します。更新のペースを保つため、社内でも気になる動向をメモし、学びを蓄積していきましょう。