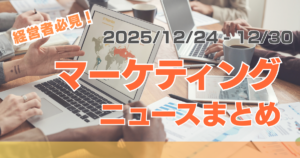マーケティングニュースまとめ(2025年7月2日〜7月8日)
中小企業経営者が押さえておくべき重要なマーケティング関連ニュースは、大手広告会社によるAI活用の本格化、新たな中小企業向けデジタル支援サービスの開始、そして消費者のAIに対する意識変化です。例えば、広告業界最大手の電通は約1000名規模のAI専門組織を立ち上げ、業界全体のAI活用を加速させようとしています。また、LINEヤフーは飲食・美容業界の小規模店舗を支援する新会社を設立し、身近なツールであるLINEを活用した店舗DXを推進します。さらに、電通の調査では対話型AIが「親友や母親と同じくらい頼れる存在」と感じる人が若年層を中心に増えていることが明らかになりました。それぞれのニュースが中小企業にもたらす意味合いを解説していきます。
1. 電通、1000名規模の「AIセンター」発足で広告業界をAI時代へシフト
概要
国内広告大手の電通グループは7月7日、グループ横断の「dentsu Japan AIセンター」を発足しました。この組織には電通や電通デジタルなどグループ5社から約1000名のAI専門人材が結集し、広告業務へのAI活用を推進します。マーケティングやクリエイティブの高度化、AIエージェントの開発、データインフラ強化など目的別に6つのユニットを編成し、社内業務の効率化から顧客企業へのAI導入支援まで包括的に取り組む計画です。電通グループ全体を「AIネイティブ企業」へと進化させる戦略の一環で、顧客企業のバリューチェーン全体でのAI活用も視野に入れています。
中小企業への影響
広告業界のリーダー企業による本格的なAI活用は、市場全体のデジタル化を加速させるでしょう。将来的に広告制作やマーケティング分析にAIを用いたサービスが増え、比較的低コストで高度なマーケティングソリューションが利用できるようになる可能性があります。例えば、これまで大企業向けだったAIマーケティングツールや分析サービスが、中小企業にも手の届く形で提供される展開が期待できます。一方で、大手各社がAIで効率化を図ることで広告・マーケティング業務の水準が全体的に引き上がり、従来型の手法に頼っている企業との競争格差が広がるリスクもあります。自社の宣伝や集客手法についても、AIを活用した効率化や高度化の波に遅れないよう注視する必要があるでしょう。
経営者の視点
経営者としては、大手発の最新テクノロジー動向にアンテナを張りつつ、自社で取り入れられる部分を見極めることが重要です。例えば、広告代理店やマーケティング支援会社からAIを活用した新サービスの提案を受けた場合には前向きに検討し、少ない予算でも試験導入できる施策にはチャレンジしてみる姿勢が求められます。自社単独で高度なAIシステムを構築するのは難しくても、外部の専門サービスを活用すれば営業効率化や顧客分析の自動化が可能になるかもしれません。また、社員のITリテラシー向上やデータ活用スキル育成にも努め、AI時代に適応できる組織づくりを進めましょう。大手企業の動きをヒントに、自社のマーケティング手法をアップデートしていく柔軟性が今後ますます重要になります。
参考リンク
電通グループをAIネイティブ化 「dentsu Japan AIセンター」発足
2. 博報堂DY×SOテクノロジーズ、中小広告代理店を支援する「S-ONEプロジェクト」始動
概要
博報堂DYグループのデジタル企業Hakuhodo DY ONEと、地方企業向けマーケ支援を手掛けるSO Technologies社が連携し、中堅・中小の広告代理店の事業成長を支援する「S-ONEプロジェクト」を開始しました。本プロジェクトでは両社のサービス・ツールを統合し、地方も含めた多数の小規模広告会社に対して最新テクノロジー活用による業務効率化と競争力強化を支援します。具体的には、“3つの革新” (Speedy・Smart・Strategic) を柱にサービスを展開。例えば、AI搭載ツールでメディアプランニングを自動化したり、進行管理を一元化するプラットフォーム(パートナーダッシュボード)を提供し、クリエイティブ素材の自動生成機能も備えています。さらに、テレビ×デジタル統合プランニングツールなど博報堂系の高度なソリューションも組み合わせ、地方や小規模の代理店でも大手と遜色ないマーケティング提案ができるようにすることが狙いです。
中小企業への影響
この取り組みにより、地方や規模の小さい広告代理店でも最先端のデジタル広告運用ノウハウを活用しやすくなります。中小企業の多くは、自社のマーケティングを地域の広告代理店やコンサルに依頼していますが、そうしたパートナー企業のサービス品質が向上すれば、結果的に中小企業が得られるマーケティング効果も高まるでしょう。例えば、最新AIを駆使した広告配信最適化や、テレビCMとウェブ広告を組み合わせた統合キャンペーンといった施策も、小規模代理店経由で手頃な価格帯で利用できる可能性があります。一方で、市場全体で広告運用が洗練され競争が激しくなる中、自社の広告戦略にも一層の工夫が必要になります。代理店任せにせず、自社でもKPI設定や成果確認を丁寧に行い、パートナーの提案を最大限活かせるよう準備しておくことが重要です。
経営者の視点
経営者は、自社のマーケティングを委託している広告会社や支援会社の動向にも注意を払いましょう。「S-ONEプロジェクト」のような動きによって、自社を担当する代理店がより高度なサービスを提供できるなら、それを積極的に活用する価値があります。定期的に代理店と打ち合わせを行い、新しいツールやデータ活用方法について情報交換すると良いでしょう。「うちの代理店は規模が小さいから最新の提案は難しい」と決めつけず、博報堂DYなど大手と連携したサービス提供が可能になっているかもしれません。また、もし自社内でマーケティングを完結している場合でも、これらのプロジェクトから生まれるSaaSツール(広告運用管理や効果測定ツールなど)が中小企業向けに提供される可能性があります。コストに見合うようであれば導入を検討し、自社マーケティングの効率アップや成果向上につなげましょう。
参考リンク
Hakuhodo DY ONEとSO Technologies、中小広告会社を支援するプログラム開始
3. SEO対策もAI時代へ:ミエルカSEOが検索結果のAI概要表示を可視化する新機能
概要
SEO支援ツール「ミエルカSEO」に、Google検索におけるAI生成の概要表示(AI Overviews)の出現率を計測できる新機能「AIOレポート」が追加されました。開発元のFaber Companyによれば、この機能により登録キーワードに対し検索結果にAIによる回答が表示される頻度をモニタリングでき、AI概要表示が自社サイトや競合サイトのアクセスに与える影響を可視化できるとしています。2024年8月以降、日本のGoogle検索でもユーザーの質問にAIが直接回答を提示するケースが増えており、従来の検索上位表示ページへのクリック率が変動する可能性があります。本機能では、特定キーワードで何%の確率でAI概要が表示されているかをグラフで一目で確認でき、さらにAI概要によるトラフィック減少の予測なども立てられるようサポートします。SEO業界ではこれを「GEO(Generative AI Optimization)」とも呼び、同社は今後AI概要内で自社サイトが引用されているかを把握する機能なども提供予定です。
中小企業への影響
検索エンジン経由で集客している企業にとって、Googleの検索結果表示の変化は見過ごせません。特に、AIがユーザーの質問に直接答えを示す「AIオーバービュー」が増えると、ユーザーが検索結果をクリックせずに満足してしまう「ゼロクリック検索」が起こりやすくなります。中小企業のウェブサイトも、せっかく上位表示されてもアクセスが減る可能性があり、これまでのSEO戦略の前提が揺らぎかねません。一方で、自社の情報がAI回答に引用リンク付きで取り上げられれば、新たな流入経路になるチャンスもあります。このミエルカSEOの新機能は、自社サイトがそうしたAI回答の影響をどれほど受けているか定量的に把握する助けになります。専門の担当者がいない小規模事業者でも、ツールを使えば「自社の狙うキーワードでは○割のユーザーにAI回答が出ている」といった状況を把握でき、対策立案に役立てられるでしょう。
経営者の視点
SEOやWeb集客を外部に任せている経営者も、この検索トレンドの変化について基本的な理解を持っておくべきです。まず、自社のサービス分野の検索結果にAI回答が出現し始めているか、試しにいくつかキーワード検索して確認してみましょう。もしAIによる回答が目立つようであれば、ウェブ担当者や支援会社に相談し、コンテンツの見直しや対策を検討します。例えば、AIに引用されやすい公式情報(FAQの充実やスキーママークアップの活用)を整備することや、AIでは伝えきれない専門性の高いコンテンツを充実させることが考えられます。また、ミエルカSEOのようなツール導入について提案を受けた際は、費用対効果を精査しつつも前向きに検討しましょう。検索エンジンの進化は早いため、小さな改善でも機敏に実行し、データをもとにPDCAを回す姿勢が大切です。「AI時代のSEO」に対応することで、安定したウェブ集客経路を将来にわたり確保する意識を持ちましょう。
参考リンク
ミエルカSEO、Google AI Overviewsの出現率を可視化する新機能を追加
4. LINEヤフー、小規模店舗のDX支援に本腰 – 飲食・サロン業界向け新会社を設立
概要
LINEヤフー株式会社は7月1日付で、飲食店や理美容サロンなどの小規模事業者を対象に店舗DX(デジタルトランスフォーメーション)支援を行う新会社「LINEヤフービジネスパートナーズ」を設立しました。月間利用者9800万人を抱えるコミュニケーションアプリLINEの基盤を活用し、専任スタッフが各店舗の課題解決をサポートします。具体的な支援内容としては、LINE公式アカウントを使った顧客管理・販促、ミニアプリや「LINEで予約」機能の導入支援などが挙げられます。従来、人手不足やIT知識の不足からデジタル化が進みにくかった飲食・美容業界に対し、低コストかつ簡便に導入できるLINEの仕組みを提供することで、予約受付や顧客とのやりとりを効率化し、紙・電話中心だった業務をオンライン化する狙いです。
中小企業への影響
身近なSNSアプリであるLINEを使ったDX支援は、小規模ビジネスにとってハードルの低いデジタル化のチャンスと言えます。新会社のサービスによって、これまで予約管理や集客を手作業で行っていた個人経営の店でも、スマホで予約受付やクーポン配信ができるようになるでしょう。例えば、飲食店ならLINEで空席状況確認から予約まで完結し、リマインド通知やレビュー収集も自動化できます。美容院・サロンでも、施術メニューの事前相談をチャットで受け付けたり、来店サイクルに合わせたお知らせを一斉送信するといったきめ細かな顧客フォローが可能になります。こうした取り組みはリピーター獲得や顧客満足度向上につながり、大手チェーンと競う上でも強みとなるでしょう。一方で、デジタル化に乗り出す店舗が増えれば、従来通りのアナログ対応のみでは顧客から選ばれにくくなる可能性もあります。業界全体で顧客体験の底上げが進む中、自社も遅れずについていくことが大切です。
経営者の視点
「ウチのような小さな店にはITなんて無縁」と思っていた経営者にも、今回のニュースはDXへの第一歩を踏み出す好機となりえます。LINEは多くの顧客が日常的に使っているツールであり、導入のハードルが低い点が魅力です。経営者はぜひ新会社が提供する支援メニューをチェックし、自社にフィットしそうなサービスがあれば積極的に活用を検討しましょう。例えば、予約システムの導入に踏み切れば無断キャンセルの減少や顧客データの蓄積といった効果も期待できます。また、デジタル導入後はスタッフへの周知徹底や、得られたデータを活かしたマーケティングも重要です。LINE公式アカウントで顧客属性や来店頻度が把握できるようになったら、常連向けキャンペーンや休眠客フォローなど次の施策につなげましょう。小規模だからこそ、小回りを利かせてデジタル施策を柔軟に試し、「アナログの良さ」と「デジタルの便利さ」を両取りする経営を目指すことが今後の成長に繋がります。
参考リンク
「LINEで予約」で飲食・理美容DX LINEヤフー新子会社
5. 対話型AIが「第3の仲間」に? 若年層で進むAIチャットへの信頼【電通調査】
概要
電通が7月3日に公表した調査によると、週1回以上AIチャットを利用する人の64.9%が「対話型AIに感情を共有できる」と感じており、その割合は「親友」(64.6%)や「母親」(62.7%)とほぼ同じ水準に達しました。特に10代・20代では7割以上がAIに気持ちを打ち明けられると答えており、電通は対話AIが若者にとって「第3の仲間」のような存在になりつつあると分析しています。また「AIチャットを信頼している」という人も全体の86%にのぼり、10代・20代では過半数が「非常に信頼している」と回答しています。さらに、対話AIに愛着を感じる人も全体の67.6%おり、中にはAIに自分で名前を付けているケース(全体26%、20代では約40%)もあるとのことです。「否定しないで寄り添ってくれる」「カウンセラーのようだ」など、AIが人には言いにくい悩み相談役になっている様子もうかがえます。
中小企業への影響
消費者、とりわけ若い世代のAIテクノロジーに対する心理的ハードルが下がっていることは、中小企業のサービス提供にも影響を与えそうです。例えば、これまで有人対応が当たり前だったカスタマーサポートや問い合わせ対応に、AIチャットボットを導入することへの抵抗感が利用者側で減っていると考えられます。むしろ「AIのほうが気軽に本音を話せる」という層もいるため、商品選びの相談やクレーム対応にAIを活用すれば、従来より率直な顧客の声を引き出せる可能性があります。店舗ビジネスでも、深夜の問い合わせや予約変更対応をAIが受け付けることで顧客満足度を維持しつつ省力化できるかもしれません。また、マーケティング面では対話型AIが新たな情報収集源となっている点にも注目です。消費者がAIに商品アドバイスを求める時代が来れば、企業は自社商品がAIに正しく推薦・言及されるよう、情報発信の仕方を工夫する必要があります(※この点は前述のAI検索最適化とも関連します)。
経営者の視点
経営者は、顧客コミュニケーション手段の選択肢としてAIチャットの活用を前向きに検討してよいでしょう。もちろん全てをAI任せにするのではなく、まずは簡易な問い合わせへの自動応答や、ウェブサイト上での案内役としてAIチャットボットを試験導入してみる価値があります。意外な質問や相談が寄せられることで、新たな顧客ニーズの発見につながるかもしれません。導入にあたっては、AIが誤った応答をしないよう定期的なメンテナンスと、必要に応じた人間オペレーターへのエスカレーション体制を整えておくことが重要です。またマーケティング面では、AIが参照する公式情報(商品データやQ&A)の整備や、AIに企業情報を提供するプラットフォームへの対応などが今後求められる可能性があります。いずれにせよ、若い顧客層の価値観変化として「AIに話を聞いてもらいたい」という傾向が出てきている点を押さえ、自社の顧客接点戦略に織り込んでいきましょう。新技術への適応が、顧客満足度の向上と業務効率化の両立につながるはずです。
参考リンク
まとめ
以上のニュースから、この期間はマーケティング分野でAI活用が一段と進展し、中小企業を取り巻くデジタル環境にも変化が及んでいることが分かります。電通をはじめ大手広告会社がAI専門組織を立ち上げた動きは、業界全体のデジタルシフトを象徴しています。最新技術の恩恵が大企業だけでなく中小にも波及する一方、競争環境の高度化も進むため、各企業が自社に適した形でAIやITを取り入れ、効率化と付加価値向上を図ることが不可欠です。また、プラットフォーム企業による中小支援策(LINEによる店舗DX支援など)は、自社の弱点を補完するチャンスです。外部サービスもうまく活用し、従来リソースが不足していた部分にテコ入れすることで、業務改善や集客力アップにつなげましょう。
一方、消費者側のトレンドとして、AIに対する心理的受容度が上がってきた点も見逃せません。「顧客の声をAIが聞く時代」が近づいており、マーケティングやカスタマーサービスの在り方もそれに合わせて進化させる必要があります。中小企業経営者は引き続きアンテナを高く持ち、テクノロジーと消費者動向の双方を注視してください。自社に今すぐ活かせるものから取り入れて、小さく試しながら改善を積み重ねていくことが、生き残りと成長の鍵となるでしょう。今回のニュースをヒントに、自社のマーケティング戦略をぜひアップデートしてみてください。