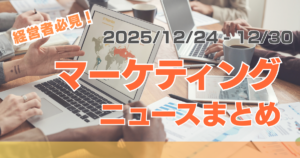マーケティングニュースまとめ(2025年6月25日〜7月1日)
今回の中小企業経営者が押さえておくべき重要なマーケティング関連ニュースは、AI技術の活用による営業・検索の革新、主要プラットフォームの新機能導入、そして消費者動向の変化です。例えば、マーケティング展示会では営業支援にAIを取り入れたツールが注目を集め、TikTokの新しいEC機能が日本で正式に始まりました。また、Google検索では大規模なアルゴリズム更新が行われ、企業のウェブ集客に影響を与える可能性があります。さらに、物価高騰やコロナ後の消費回復によって売れる商品にも変化が見られています。それぞれのニュースと中小企業への意味合いを解説していきます。
1. AI営業ツールが展示会で大盛況、150名以上が体験
概要
東京ビッグサイトで開催されたマーケティングWeek -夏 2025- 営業支援EXPOにおいて、AIを活用した営業支援ツールが来場者の関心を集めました。FlashIntel社が出展した営業効率化ツール「FlashRev」と対話型AIエージェント「FlashAI」には3日間で150名以上が訪れ、その機能に驚きの声が上がりました。特に「1時間で最大100件の電話架電が可能」など、従来の手法では考えられない効率的なアウトリーチや、人間さながらに自然な会話ができるAIのデモンストレーションに多くの注目が集まりました。
中小企業への影響
AI営業ツールの登場により、中小企業でも少ない人員で効率よく営業活動を行える可能性が高まっています。例えば、これまで人手に頼っていた新規顧客への電話アプローチや問い合わせ対応をAIがサポートすることで、営業プロセスの自動化・効率化が期待できます。一方で、競合他社が先にこれらの最新ツールを導入すれば営業力に差がつく恐れもあります。市場全体で営業DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、自社もAI活用による業務効率アップを検討しなければ、機会損失につながる可能性があります。
経営者の視点
経営者としては、まずこうした最新ツールの情報にアンテナを張り、自社の営業活動に適用できるかを検討することが重要です。デモやトライアルの機会があれば積極的に体験し、自社の課題(顧客対応の速度や提案件数の拡大など)の解決に役立つか評価してみましょう。また、導入に踏み切る際は現場の営業担当者への教育や運用体制の整備も必要です。導入コストとの見合いになりますが、業績アップや顧客満足度向上につながるならば投資する価値は大いにあるでしょう。自社に合った範囲で段階的にAIを活用し、競争力強化に役立てたいところです。
参考リンク
東京新聞:FlashIntel、マーケティングWeek 2025夏で大盛況 ─ 150名以上の来場者がAI営業ツールを体験【PR TIMES】
2. Google検索のコアアップデート開始、SEOに変動の可能性
概要
Googleは6月30日深夜(日本時間)に検索アルゴリズムのコアアップデートを開始しました。 約3か月ぶりとなる大規模更新で、完了まで最大2〜3週間かかる見込みです。コアアップデートとは検索結果のランキングを決める基準の大幅な見直しのことであり、今回も公式には具体的な変更点は公表されていません。このため、通常のアップデート同様にウェブサイトの順位変動が徐々に生じると予想されています。実際、アップデート開始直後には大きな順位変動は確認されなかったものの、今後数日のうちに検索結果の上下が発生し始める可能性があります。最終的なロールアウト完了までに複数回の変動があり得るため、サイト管理者は注意深いモニタリングが必要です。
中小企業への影響
検索順位の変動は、中小企業のウェブ集客に直接影響します。今回のGoogleコアアップデートによって、自社サイトの検索順位が上昇すれば問い合わせや注文の増加が期待できますが、逆に順位が下がればウェブからの集客減少につながりかねません。特に店舗ビジネスやECサイトを運営する中小企業にとって、検索エンジン経由のアクセスは貴重な集客チャネルです。大手企業と比べ広告予算が限られる分、検索結果で上位表示されることが売上に直結するケースも多いため、今回のアップデートの影響は見逃せません。また、最近のアップデートではAIによる要約コンテンツ表示など検索結果の画面変化も指摘されており、単に順位だけでなく自社情報の見え方にも変化が出る可能性があります。
経営者の視点
経営者としては、まず自社サイトのアクセス解析を注視し、アップデート以降に検索流入や問い合わせ数に急激な変化がないか確認しましょう。もしアクセス減少が顕著な場合は、慌てずに専門家に相談したり、公式発表やSEO情報を収集して原因を分析することが重要です。SEO対策の基本である質の高いコンテンツ作りやユーザーに有益な情報提供ができているか改めて見直す機会と捉えましょう。急にテクニック的な修正を加えるよりも、まずはアップデート完了まで推移を見守りつつ、必要に応じて信頼できるSEO専門業者の意見を聞くのも有効です。日頃から検索アルゴリズムの変更に備えてサイトの改善を続ける姿勢が、長期的には安定した集客につながるでしょう。
参考リンク
SEO HACKS:〖速報〗2025/6/30 Google検索アルゴリズム コアアップデートが開始【ナイル株式会社】
3. TikTokがアプリ内EC「TikTok Shop」を日本で提供開始
概要
若年層を中心に人気の短尺動画プラットフォームTikTokが、ついにアプリ内で完結する本格的なEC機能「TikTok Shop」を日本で正式提供開始しました。6月30日にByteDance社から発表があり、ショート動画やライブ配信を視聴しながらその場で商品を購入できるいわゆる「ディスカバリーコマース(発見型EC)」が実現します。具体的には、動画内の商品タグや「ショップ」タブから直接商品を注文でき、決済までアプリ内で完結するシームレスな購買体験をユーザーに提供します。米国や東南アジアで急成長しているこの機能が日本上陸したことで、月間数千万規模の国内TikTokユーザーにリーチして商品を販売できる新たな販路が開かれました。既にコスメや食品、アパレルなど多くの国内外ブランドがTikTok Shopに参加しており、今後大きな市場形成が期待されています。
中小企業への影響
TikTok Shopの開始は、中小企業にとってSNSを活用した新しい販売チャネルの登場を意味します。特に広告予算や知名度で大企業に劣る小規模事業者でも、TikTok上でバズれば大きな販売機会を得られる点が魅力です。これまで自社ECサイトや既存モールでの集客が主だった企業も、TikTok内で商品を直接売れることで若い世代の消費者層にリーチしやすくなります。一方、SNS特有の速いトレンド変化や口コミ拡散の影響を受けるため、商品が話題になれば一気に注文が殺到する反面、埋もれてしまう可能性もあります。また、TikTok Shop内での評価やコメントがそのまま販売に影響するため、商品クオリティや顧客対応に対するこれまで以上の注意が必要です。中小企業でも柔軟な発想でTikTok向けコンテンツを工夫できれば、大手に負けないプロモーション効果を得るチャンスと言えるでしょう。
経営者の視点
まずはTikTokの動向をウォッチし、自社の商品・サービスがTikTokユーザーに響くかを見極めましょう。例えばファッション・美容・食品など映える商品を扱っているなら、クリエイターとタイアップして商品を紹介してもらう戦略が考えられます。経営者自身がTikTokに馴染みなくても、若いスタッフや専門の代理店の力を借りて企画を立てるのも一案です。重要なのは「ただ商品を売り込む」のではなく、TikTokらしい楽しさやストーリー性を持ったコンテンツでユーザーの共感を得ることです。また、始める際は在庫管理や発送体制も整えておき、もし動画がバズって注文が急増しても対応できる準備をしておきましょう。小さくテストしながらノウハウを蓄積し、SNS時代の新たな売り上げチャネルを自社の成長に取り入れていく姿勢が求められます。
参考リンク
Web担当者Forum:TikTokのアプリ内EC機能「TikTok Shop」を日本で展開、動画やLIVEの視聴から購入へ
4. 博報堂など広告大手、AI検索でのブランド情報最適化に実証実験
概要
生成AIを使ったAI検索エンジン(チャットボット型検索)の普及に対応し、広告大手の博報堂とHakuhodo DY ONE(博報堂DYグループ)およびスタートアップのAI Hackが共同でブランド情報の最適表示に関する実証実験を開始しました。例えばユーザーがAIチャットに質問した際、企業や商品の情報が正しく提示されるかどうかを検証し、AIに最適な情報発信手法を探る目的です。現在、AIによる検索回答は必ずしも情報の正確性・網羅性が担保されておらず、企業に関する誤情報や意図しない表現が生成されるケースもあります。そこで3社は、自社ブランドがAI検索結果でどう認識・表示されているかを可視化し、回答内容の正確さやブランドイメージ適合度を評価、さらにAI向け情報発信戦略の策定・検証までを行う包括的な取り組みを進めます。この実証実験を通じて、AI時代における新たな検索エンジン最適化(AEOやGEOとも呼ばれる分野)のソリューション開発を目指すとのことです。
中小企業への影響
AIチャット検索が普及すると、ユーザーは従来の検索結果ページではなくAIが生成した回答から情報を得る割合が高まる可能性があります。そうなれば、自社の商品・サービスに関する正確な情報や魅力がAIの回答に反映されるかが新たなマーケティング課題となります。今回のニュースは大企業の取り組みですが、中小企業にとっても無縁ではありません。仮にAIが誤った情報(例:「定休日は月曜です」と誤回答する等)をユーザーに示した場合、機会損失や誤解を生む恐れがあります。AI検索最適化の重要性は今後あらゆる企業に及ぶ可能性があり、自社も公式サイトやプレスリリースで正確で最新の情報発信を心がけておく必要があります。また、業界団体や支援機関がこの分野のガイドラインや支援策を打ち出す可能性もあります。中小企業でも、自社の基本情報(住所・営業時間・商品スペック等)が構造化データで整理されているかなど、できる範囲で備えておくと良いでしょう。
経営者の視点
現時点で中小企業が専用のAI検索対策ツールを導入するのは現実的ではないかもしれませんが、経営者として押さえておきたいポイントがあります。まず、自社についてAI(例えばChatGPTやBingのチャット検索)に尋ねてみて、どのような回答が返ってくるか確認してみましょう。もし古い情報や不正確な記述が見られた場合は、自社サイトやSNSを通じて正しい情報発信を強化することが大切です。今回の博報堂らの実証実験の動向にも注目し、将来的にAI検索最適化(AIO)のサービスやノウハウが共有されるようになれば積極的に学びましょう。AI時代においても、結局は自社の商品やサービスの価値を高め、分かりやすく伝える努力が本質です。技術トレンドに振り回されるのではなく、基本を押さえつつ新しい手法にも柔軟に対応できるよう社内体制を整えておくことが望まれます。
参考リンク
エキサイトニュース:Hakuhodo DY ONE、博報堂、AI HackとともにAI検索におけるブランド情報最適化に向けた実証実験を開始【PR TIMES】
5. 上半期ヒット商品ランキング、1位「米」184%増で食品が好調
概要
市場調査会社インテージの発表によると、2025年上半期(1〜5月累計)に前年同期比で販売額が大きく伸びた日用品カテゴリの第1位は米(コメ)で、売上は前年の1.84倍に達しました。昨年来のコメ価格高騰と品薄「米騒動」の影響で家庭や飲食店による買いだめ需要が伸びたことが要因です。トップ15位までを見ると食品・飲料カテゴリーが半数以上を占めており、物価上昇下でも生活必需品や嗜好品への支出が増えていることが伺えます。一方、2位から4位には化粧品(おしろい、美容液、パック)がランクインしました。UVケア用のフェイスパウダーや高価格帯の美容液が好調で、コロナ禍で低迷していた化粧品需要が回復基調にあります。特にフェイスパックは昨年も上半期1位になるなど日常的なセルフケア習慣が定着し、引き続き売上を伸ばしています。また「売上減少(販売苦戦)ランキング」では、1位オートミール、2位検査薬といったようにコロナ禍で一時的に需要が跳ね上がった商品が軒並み順位を下げています。
中小企業への影響
このランキングから、消費者のニーズ変化やトレンドを読み取ることができます。食品業界では値上げや不足といった外部要因で需要が急増するケースがあるため、関連商品を扱う企業は在庫確保や仕入先との連携が重要です。たとえば米や食用油など生活必需品が急に動く際、機動的に対応できればチャンスを掴めます。化粧品の回復は、アフターコロナで外出機会が増えたことによる需要回復を示しており、美容・アパレル系の中小企業にとって追い風と言えます。こうした商品ではSNSマーケティングやインフルエンサー起用を強化し、波に乗ってブランド認知を伸ばす好機です。一方、オートミールや簡易検査薬の失速からは、ブームに頼った商品構成のリスクも見て取れます。流行に乗って売上が伸びた商品はブーム終了後に反動減が起こりやすいため、事業計画の際には一過性の需要と継続的な需要を見極めておく必要があります。
経営者の視点
自社の商品やサービスがこのような消費トレンドの中でどの位置にあるのか、経営者は常に意識する必要があります。売上構成比を分析し、「流行に左右される商品」と「安定した定番商品」のバランスをチェックしましょう。ブームに乗った商品で短期的に利益を上げつつも、その利益を新商品の開発や既存主力商品の強化に投資するなど、一時的なトレンドを持続的な成長につなげる戦略が求められます。また、市場データや消費者アンケートなどを積極的に参考にし、消費者のニーズ変化をプロダクト開発や販促計画に反映させましょう。中小企業だからこそ市場の隙間を突いた素早い商品展開が可能です。大手が手掛けないニッチな需要や新しいライフスタイルに着目し、自社の強みと組み合わせた商品・サービスを打ち出せれば、次の「ヒット商品」を生み出すことも夢ではありません。
参考リンク
インテージ:令和の米騒動が直撃「2025年上半期、売れたものランキング」
まとめ
以上のニュースから、マーケティングを取り巻く環境がテクノロジーの進化と社会の変化によって大きく動いていることが分かります。生成AIの活用が営業や検索といった分野で現実的なソリューションとなりつつあり、政府や大企業のみならず中小企業もその波に乗ることで効率化や新たなビジネスチャンスを得られるでしょう。また、プラットフォームの新展開(TikTokのEC化など)は消費者との接点を増やすチャンスであり、従来のやり方にとらわれない柔軟なマーケティング戦略が求められます。さらに、消費者ニーズの変化を敏感に捉えることも重要です。物価高対応やアフターコロナの動きに合わせて商品戦略を調整し、ヒットの芽を逃さないようにしましょう。
中小企業経営者は、これらの動向にアンテナを張りつつ自社に活かせるものは何かを見極める姿勢が大切です。例えば、AIツールの導入検討、SNS上でのプロモーション強化、あるいは市場データに基づく商品仕入れや開発など、できることから少しずつ実践してみることをおすすめします。環境変化のスピードは速いですが、小回りの利く中小企業ならではの俊敏さで対応すれば十分にチャンスを掴めます。引き続き最新情報を追いながら、自社のマーケティング活動に創意工夫を凝らし、顧客との信頼関係を深める取り組みを継続していきましょう。そうすることで、変化の時代においても着実に自社サービスへの共感と支持を広げ、成長につなげていくことができるはずです。