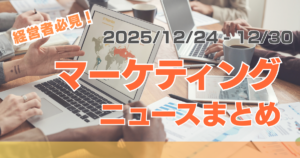マーケティングニュースまとめ(2025年6月18日〜6月24日)
マーケティング分野では2025年6月18日から24日にかけて、大型資本提携や公的支援策の拡充、AIを活用したクリエイティブ制作手法の進化など、注目すべき動きが相次ぎました。海外ゲーム企業による日本広告会社への巨額出資は、業界の垣根が急速に溶け、ファンコミュニティを核とした新しいマーケティングエコシステムが拡大していることを示しています。さらに、助成金をフル活用してマーケティング人材を育成するプログラムの登場や、AIエージェントによる業務支援サービスのリリースにより、従来は大企業の専売特許だった高度なマーケ施策が中小企業にも手の届く段階に入りました。広告制作のリードタイムを半日に短縮するソリューションや、地方メーカーのリブランディング成功事例も現れ、スピード・顧客体験・ブランドストーリーがより一体化した競争環境が到来しつつあります。本記事では、この期間に報道された5つのキートピックを、中小企業経営者の皆さまにとって実践的な視点で解説します。
1. 助成金活用で中小企業のマーケ人材育成支援を開始
概要
6月19日、マーケティング支援企業のシナジーマーケティングと補助金コンサルのHelpTechが提携し、助成金を活用した中小企業向けデジタルマーケティング人材育成プログラムを開始しました。国の「人材開発支援助成金」を活用して研修費用を最大▽割相当削減できるのが特徴で、導入研修・応用研修・オンラインeラーニング・個別メンタリングの4段階がセットになっています。カリキュラムはSEO、SNS運用、Web広告運用、データ解析、コンテンツ企画、ブランド設計など幅広く、実務で使えるテンプレートやチェックリストも提供。申請書作成や報告書提出の代行をHelpTechが行うことで、助成金特有の煩雑な手続きをワンストップで完結させています。昨年度に実施したパイロット版では、参加21社中19社が目標KPIを達成し、平均で広告CPAが28%改善したとの報告も公表されました。
中小企業への影響
専門のマーケターを雇用・育成する余裕がなかった中小企業にとって、低コストで社員を本格的にマーケティング教育できる画期的な仕組みです。特に「広告は外注」「SNS更新は担当者の空き時間」という属人的運用になりがちな企業では、研修を受けた社員が自社の価値を深く理解したうえで施策を実行できるため、外注よりも訴求の精度が高まりやすい点が大きなメリットです。さらに、助成金を利用することで経費計上の負担も抑えられ、学んだノウハウが社内資産として蓄積されます。今後、人材流動性が高まるなかで「育成プログラムの有無」は採用競争力にも影響するため、マーケティング組織を内製化していく企業は増えるでしょう。
経営者の視点
経営者としては、(1)自社の中期経営計画でどの領域のマーケスキルが不足しているかを棚卸し、(2)助成金を使って優先順位の高い研修から着手し、(3)学びを定着させる仕組み(週次共有会・小規模ABテスト・ペアワーク省察)を整える、という三段階アプローチを推奨します。研修後は“やりっぱなし”で終わらせず、学んだ社員が実案件を通じて試行錯誤できる環境を提供することが成功の分岐点です。また、経営者自らが助成金の仕組みを理解し、財務・人事部門と連携してPDCAを回すことで、組織全体が「マーケティングは投資」という文化に変わっていきます。
参考リンク
PR TIMES:シナジーマーケティングとHelpTechが提携、助成金を活用した中小企業のデジタルマーケティング人材育成支援を開始
2. 中小メーカーのリブランディング、マーケティング大賞で表彰
概要
公益社団法人日本マーケティング協会が主催する「第17回日本マーケティング大賞」にて、新潟県燕市の家電メーカー・ツインバードが奨励賞を受賞しました。同社は創業70周年を機にブランドプロミス「心にささるものだけを。」を掲げ、ロゴを刷新。さらに「匠プレミアム」「感動シンプル」という2つのブランドラインを立案し、高価格帯と日用価格帯それぞれで顧客体験を設計しています。リブランディング施策の要となったのが、社内外に向けたストーリーテリングの徹底です。具体的には、職人のインタビュー動画や工場見学VRコンテンツを制作し、顧客が“ものづくりへのこだわり”を擬似体験できる施策を展開。オンライン限定のシリアルナンバー刻印サービスや、購入者コミュニティサイト「TWINBIRD CIRCLE」など、顧客参加型の企画も導入しています。これにより、Z世代を中心とした若年層の新規顧客が前年比160%増を記録し、オウンドメディア経由の売上比率が28%→47%に伸長したと報告されています。
中小企業への影響
この事例は「パーパス経営」と「ブランド体験の一貫性」が評価された好例であり、規模を問わず再現性があります。(1)自社の強み・弱みを棚卸し、(2)顧客が共感できるメッセージを設計し、(3)体験接点ごとに言語・ビジュアル・ストーリーを統一する、という王道フレームを愚直に実行した点が高く評価されています。特に地方企業の場合、地域文化や歴史的背景をブランドの物語に組み込むことで他社と差別化できるメリットがあり、ECプラットフォームで“見て選ばれる”時代において強い武器となります。
経営者の視点
経営者がまず行うべきは、「自社ブランドの約束」を15秒で語れるかをチェックすることです。言語化が曖昧な場合、ワークショップで経営陣と現場リーダーが協働し、パーパス・バリュー・ビジョンを再設計しましょう。その後、ロゴ刷新やサイト改修よりも前に、“ブランド体験の主要接点”を洗い出し、接客マニュアルやアフターサポートまで一貫させることが重要です。オンラインコンテンツ制作が難しい場合でも、社史や職人紹介をブログで連載する、地元メディアとコラボして地域の祭りに出店するなど、小さく始めて成果を可視化することで社内の合意形成が進みます。
参考リンク
にいがた経済新聞:ツインバード、日本マーケティング大賞で「奨励賞」受賞 リブランディングが評価
3. ゲーム大手が日本広告会社に750億円投資、アニメ×ゲームで協業拡大
概要
韓国のゲーム開発大手KRAFTONは6月24日、国内広告大手ADKホールディングスに約750億円を出資し、ファンド経由で株式の過半を取得する方針を発表しました。ADKは1月に米Stagwellと資本業務提携を発表したばかりで、今回のKRAFTON出資によりグローバル×エンターテインメント領域のハイブリッド広告ネットワークを形成する狙いです。両社は、(1)アニメIPとゲームIPのクロスメディア開発、(2)没入型広告・メタバース内イベントの共同企画、(3)eスポーツ大会とコンテンツ配信の統合プラットフォーム化、など複数のプロジェクトを想定。KRAFTONの「PUBG」や「Dark and Darker」などのゲームIPに、ADKが保有する人気アニメIPを掛け合わせることで、新たなファンエンゲージメントモデルを構築するとしています。
中小企業への影響
一見スケールの大きい話ですが、示唆に富んでいます。消費者がエンタメ性の高い体験を求めるなか、広告も“感情移入”や“共創”をキーワードに進化しています。中小企業でも、ミニゲームキャンペーンやコラボグッズ販売、ユーザー投稿型コンテストといった低コスト施策でファンコミュニティを醸成する余地があります。特にBtoC商材を扱う場合、アニメキャラクターやインフルエンサーと組むだけでなく、顧客自身がストーリーの一部になる仕掛け(例:購入者限定ライブ配信や商品開発投票)を設計すると、広告費をかけずにリーチを広げられます。
経営者の視点
経営者が注目すべきは今回の投資が「コミュニティ価値の貨幣化」を目的としている点です。自社もプロダクトの機能訴求だけではなく、ユーザー同士が交流し、UGCが自然発生する仕組みを検討しましょう。まず、SNSグループやオンラインサロンを立ち上げ、熱心な顧客をシードメンバーとして招待し、定期的にフィードバックをもらう仕組みを作るのが第一歩です。そのうえで、商品ストーリーと顧客ストーリーを結びつけるコンテンツを用意し、“買って終わり”を“参加して続く”体験へと転換することで、限られた広告費でも高いLTV(顧客生涯価値)を実現できます。
参考リンク
MarkeZine:KRAFTON、ADKグループを750億円で傘下に アニメとゲームの協業拡大へ
4. AIで縦型動画制作を半日に短縮、電通デジタルとMetaが提携
概要
電通デジタルはMetaと提携し、Instagram向けの縦型動画広告を最短半日で制作できるワークショップ「IG AI Creative Studio」を提供開始しました。AIプラットフォーム「∞AI(ムゲンAI)」が、消費者インサイト解析→クリエイティブ生成→効果予測→ABテスト⼊稿の一連フローを自動化。Metaの大規模言語モデル「Llama」が広告ライブラリを解析し、ターゲット属性に最適な表現パターンを提案します。従来は3〜4週間かかっていた動画制作が劇的に短縮され、クリエイターは戦略設計やストーリー強化に集中できるようになるのが特徴です。既にファッション、食品、SaaSなど複数業界でPoCを完了し、平均CVRは従来比1.8倍、制作コストは65%削減とのレポートも公表されています。
中小企業への影響
動画広告がブームとはいえ、実際には「費用も時間もかかる」ため消極的な企業が多いのが現状です。しかし、このようなAIツールの普及により、制作ハードルが一気に下がるのは確実です。具体的には、(1)テンプレート生成AIを使って冒頭3秒のフックを複数案自動生成、(2)在庫画像をアップロードして商品訴求映像を自動合成、(3)メディアごとの最適フォーマットを書き出し、という流れがワンストップで可能になります。これにより、タイムセールや季節限定キャンペーンを当日中にPRできるようになり、既存のSNSフォロワーに素早くアプローチできます。
経営者の視点
経営者がまず行うべきは、自社で動画を使う目的の明確化です。「認知拡大」「顧客教育」「EC購買促進」など目的別にKPIを設定し、そのうえでAIツール導入を検討しましょう。また、短時間で量産できるようになるほど“質”の管理が課題になります。社内にブランドガイドライン(色/書体/トーン&マナー/禁止表現)を用意し、AI出力のクリエイティブが基準を満たしているかをチェックするフローを整備してください。制作スピードとブランド統制を両立できれば、AI活用は大きな武器になります。
参考リンク
Web担当者Forum:電通デジタルとMetaがAIで提携、Instagram縦型動画制作を半日に短縮するサービス開始
5. オプトとRidge-i、AIエージェント活用のマーケ業務支援サービスを提供開始
概要
インターネット広告大手オプトとAI開発企業Ridge-iは、AIエージェントを活用したマーケティング業務支援サービスをリリースしました。トレンド分析、競合サイトのデータ収集、自社ナレッジDBのQA検索、広告クリエイティブ自動生成、レポーティングまでをカバーし、マーケ担当者の作業時間を最大50%削減する設計です。AIはOpenAI系言語モデルと自社独自モデルを組み合わせ、過去施策の効果データを継続学習することで提案精度を高めます。β版導入企業10社では、媒体出稿までの平均リードタイムが21日→9日へ短縮し、担当者1人あたり月20時間のリソースが創出されたといいます。
中小企業への影響
マーケティング専門部署がない企業でも、AIエージェントの活用によって“データに基づく意思決定”と“クリエイティブ量産”を同時に実現できる環境が整いつつあります。たとえば、(1)自社Web解析データを接続して週次で改善提案レポートを自動受信、(2)新商品ローンチに合わせてAIが競合動向・適切な広告予算配分を提示、(3)複数の広告クリエイティブ案を自動生成してクリック率予測と併せて提示、といった運用が可能です。少人数でも“回る”マーケ組織をつくれる点は、中小企業の人的リソース不足を補完する強力な手段になります。
経営者の視点
まずはマーケティング業務をタスク分解し、AIが代替可能な領域(データ整理、簡易文案生成、定型レポート作成など)を洗い出しましょう。そのうえで、既存のSaaSツールにAIアドオンを追加する、もしくは外部サービスに部分委託しながら段階的に自社データと統合する、というハイブリッド戦略が現実的です。導入時のポイントは、(1)学習用データの整備と権限管理、(2)AI出力の検証フロー(人間がレビュー&承認)、(3)長期的ROIのモニタリング、の3点です。経営トップが“数値を見ながら小さく試し、大きく伸ばす”姿勢を示すことで、社内にAI活用の文化が根づきます。
参考リンク
MarkeZine:オプト、Ridge-iと共創でAIエージェント活用のマーケティング業務支援サービスを提供
まとめ
2025年6月18日〜24日に報道された5つのニュースは、マーケティングの主戦場が「スピード」と「顧客体験の深化」に移行していることを示しています。助成金を活用した人材育成やAIによる制作効率化は、コストと時間の壁を取り払い、中小企業でもトップレベルの施策を実装できる時代が到来したことを物語ります。同時に、ブランドの“芯”を再定義し、ファンコミュニティを育てるストーリー設計が欠かせません。経営者は以下の3点を意識すると良いでしょう。
- 学びへの投資をコストでなく“資産形成”と捉える
公的助成や外部プログラムを活用し、社内にマーケティングの“型”を蓄積する。 - 顧客参加型の体験設計でファンを巻き込む
コミュニティスペースやUGC施策で、顧客を“買い手”から“語り手”へ昇華させる。 - AIと人の役割分担を再編成し、PDCAの速度を最大化する
AIを情報収集・分析・生成に活用し、人は意思決定と創造に集中。小さく試して高速に回転させるカルチャーを築く。
変化の激しい時代こそ、武器になるのは“俊敏な実行力”と“ぶれないブランド軸”です。本記事を参考に、テクノロジーとストーリーテリングの両輪で自社のマーケティングをアップデートし、持続的な成長につなげていただければ幸いです。