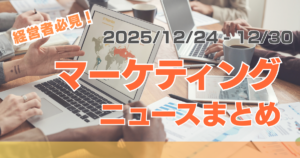マーケティングニュースまとめ(2025年5月7日〜5月13日)
中小企業経営者の皆さま、2025年5月7日〜13日にかけて、日本国内でマーケティングに関する注目ニュースが多数報じられました。例えば、Googleの新しいAI広告システムが発表され、オンライン広告の効果向上が期待されています。国内では大手広告会社の電通がAIを活用したマーケティング支援を開始し、マーケティングツール企業からも生成AIを組み込んだ新サービスが登場しました。また、自治体と連携して中小企業の情報発信を支援する取り組みや、若者の「推し活」(ファン活動)に着目したマーケティング調査など、多岐にわたる話題が登場しています。本記事では忙しい経営者の方に向けて厳選した5つのニュースを解説し、それぞれが中小企業にもたらす影響と、経営者として取るべき対応策をまとめました。ぜひ最後までお読みいただき、明日からの経営にお役立てください。
1. Google、AI活用の新広告システム「AI Max」で検索広告を強化
概要:
検索エンジン大手のGoogleは、新たな広告配信システム「AI Max for Search campaigns」を発表しました。これは生成AIの技術を活用し、ユーザーの検索キーワードの文脈まで理解して関連性の高い広告を表示できる仕組みです。従来はキーワードの一致が中心でしたが、AI Maxではより柔軟に関連語句にも広告を出せるようになり、その結果、Googleの調査では広告のコンバージョン(成果)数が平均14%向上したと報告されています。このシステムは5月下旬にベータ版提供予定で、広告主はGoogle広告の管理画面で新機能を有効化するだけで利用できます。
中小企業への影響:
小規模企業にとっても、少ない広告予算で効率よく集客できるチャンスとなり得ます。AIが検索ユーザーの意図を読み取ってくれるため、これまでキーワード設定では拾えなかった見込み客にもリーチできる可能性があります。例えば、これまで「カフェ 横浜」で広告設定していた場合に、AI Maxなら「横浜 落ち着く喫茶店」など関連表現で検索した人にも広告が表示されやすくなります。結果として同じ費用でより多くの問い合わせや購買につながる可能性が期待できます。一方で、AIに任せる範囲が広がる分、広告が想定外の検索語にも表示される可能性があります。中小企業でも広告配信後のレポートを確認し、無関係な表示がないかチェックするなど、運用状況のモニタリングは引き続き重要です。
経営者の視点:
経営者としては、この新機能を積極的に試してみる価値があります。まずは少額の予算でAI Maxを有効化し、広告成果の変化を検証してみましょう。効果が向上すれば、本格導入によって限られた広告費で最大の効果を狙えます。また、AIに任せるとはいえ、広告の元となるキャッチコピーやランディングページの内容が魅力的であることが前提です。自社の商品・サービスの強みがユーザーの目に留まるよう、広告文やサイト内容も見直しておきましょう。さらに、競合他社も同様の機能を活用してくると考えられるため、自社だけでなく業界全体の広告動向にもアンテナを張り、効果的なマーケティング手法を常にアップデートする姿勢が大切です。
参考リンク:
GIGAZINE:GoogleがAIを使った広告システム「AI Max for Search campaigns」を発表
2. 電通、生成AIでマーケティング戦略立案を高速化する新ソリューション開始
概要:
日本最大手の広告会社である電通が5月8日、マーケティングプロセスをAIで高度化するソリューション「People IMC Prototyping」の提供開始を発表しました。マーケティングの「ターゲット設定・戦略設計・戦術設計・効果検証」の4ステップそれぞれに、電通の保有する大量の行動データや市場リサーチ、専門人材の知見を学習した生成AIを活用し、短期間で質の高いマーケティングプランを作成・検証できるのが特徴です。従来は企画に数カ月かかっていた作業を大幅に圧縮でき、新商品プロモーションのプランニングやキャンペーン施策のアイデア出しを迅速化します。例えば、小売業界向けには店内ディスプレイ施策をAIで多数考案し即テストすることで、PDCAサイクルを飛躍的に短縮するといった応用も可能とのことです。
中小企業への影響:
大企業の動きではありますが、「マーケティングのスピードと精度を上げる」という潮流は中小企業にも無関係ではありません。電通のようなリソース豊富な企業がマーケティング計画の効率化に乗り出すことで、市場全体の施策実行サイクルが速まる可能性があります。中小企業も従来のように時間をかけて試行錯誤していると、俊敏な競合に先手を打たれてしまうかもしれません。一方で、AI活用による効率化は中小企業にとってもヒントになります。自社のマーケティングでも、例えば簡易なAIツールで顧客データを分析したり、オンライン上でトレンド調査を素早く行ったりといった工夫で、企画立案のスピードを上げることが可能です。大企業ほどデータがなくても、無料・安価なAIサービスを使えば手軽に市場リサーチやアイデア創出ができる時代になりつつあります。
経営者の視点:
経営者としては、「計画→実行→検証」のサイクルを如何に早く回せるかが競争力に直結することを認識しましょう。電通のニュースは、自社でも意思決定の迅速化に取り組むべきサインです。具体的には、社内のマーケティング会議でAIツールを使って消費者の声やトレンドを即座に調べ、その場で戦略に反映するといった手法も試してみてください。また、マーケティング専門部署がない小規模企業でも、外部のマーケティング支援サービスやコンサルタントと連携し、最新の手法を取り入れる柔軟性が重要です。ポイントは、大企業の真似をそのままする必要はありませんが、「データに基づき、素早く仮説検証する」姿勢を持つことです。限られたリソースでも小回りの良さを発揮し、変化する市場に敏捷に対応できる組織作りを目指しましょう。
参考リンク:
共同通信PRワイヤー:電通、生成AIでマーケティングプロセスを高度化する「People IMC Prototyping」の本格提供を開始
3. イルグルム、日本初のAI搭載「マーケティングキャンペーン管理」ツール発表
概要:
マーケティング支援ツールを手掛けるイルグルム社は5月7日、日本初のマーケティング・キャンペーン・マネジメント・プラットフォーム「AD EBiS Campaign Manager」を正式リリースすると発表しました。このサービスはオンライン広告の効果測定で知られる「アドエビス」のデータと、外部情報を組み合わせた生成AI(RAG技術)による分析機能を統合し、企業のマーケティング施策の企画から実行、振り返り(効果検証)までを一貫して支援するものです。例えば、過去の広告キャンペーン結果が社内に蓄積されておらずノウハウが属人化する問題に対し、本ツール上で施策内容と成果を記録・共有し、AIが次回の施策アイデアを提案してくれるため、チーム全体で知見を蓄積し再現性のあるマーケ戦略を構築できるとしています。正式提供開始は5月下旬で、月額利用料は25,000円~と中小企業でも導入可能な価格帯に設定されています。
中小企業への影響:
少人数でマーケティングを担当する企業にとって、施策の管理と改善提案を自動でサポートしてくれるツールは心強い存在です。広告やキャンペーンのたびに都度手探りでPDCAを回しているような状況でも、本サービスを使えば過去の成功・失敗パターンを資産として蓄積しやすくなります。例えば「昨年の夏に実施したSNS広告はどの層に響いたか」といった振り返りをAIが分析しレポートしてくれれば、担当者が替わっても知見が残り、次の夏キャンペーンに活かせます。また、生成AIによる自動レポート作成や改善案の提案は、専門知識の乏しい中小企業でも最新のマーケティング知見にアクセスできることを意味します。一方で、ツールに頼るだけではなく、そこで得た示唆を自社の実情に合わせて判断する人間の目も必要です。データに基づく提案はあくまで支援ツールなので、経営者や担当者が最終的な方向性を決める指針として使うようにしましょう。
経営者の視点:
経営者として注目すべきは、「マーケティング施策自体を会社の財産にする」という発想です。中小企業では、マーケティングが個人の勘や経験に頼りがちですが、このサービスのように結果を記録しAIが分析する仕組みを取り入れれば、経験値を社内ナレッジとして蓄積できます。まずは無料トライアルやデモ版があれば試してみて、自社のマーケティング活動の見える化を進めてみましょう。難しければ、エクセルや簡易なツールでも良いので施策の記録と結果分析を習慣化することが大切です。その上で、可能ならAI解析ツールを導入し、レポート作成の自動化や改善点の洗い出しに活用してください。コストに見合う効果が得られるなら業務効率が上がり、人手不足の解消にもつながります。マーケティングはやりっぱなしにせず、結果を資産として次につなげる――その意識改革が、中小企業の持続的な成長に寄与するでしょう。
参考リンク:
PR TIMES:イルグルム、日本初の“マーケティング・キャンペーン・マネジメント・プラットフォーム”を正式リリース
4. 地方自治体とPR TIMESが連携、中小企業のプレスリリース発信を支援
概要:
5月7日、岡山市と国内最大のプレスリリース配信サービス「PR TIMES」が情報発信支援に関する連携協定を締結しました。この協定により、岡山市が支援する地元のスタートアップ企業や中小企業・団体は、一定の条件下でPR TIMESを最大6カ月間無償利用できるプログラムの提供を受けられます。具体的には、自社の新商品やサービスの情報をプレスリリースとして作成し、PR TIMESを通じて全国の報道機関や読者に配信できるよう支援するものです。また、市内企業向けに効果的な広報・PR手法についてのセミナーも開催される予定で、企業の広報力向上を後押しします。岡山市によると、自治体がPR TIMESと組むのは中国・四国地方では初めてで、全国でも熊本市に続き8例目とのことです。自治体側も自らの施策発信に同サービスを活用することで、市の魅力発信や企業誘致にもつなげたい考えです。
中小企業への影響:
この取り組みは、地域の中小企業にとって絶好のPR機会となります。普段は広報専門の人材や予算がなく、新聞やテレビに取り上げてもらうハードルが高い小規模事業者でも、プレスリリース配信を通じて自社のニュースを広く知ってもらえる可能性が高まります。実際、PR TIMESで配信された情報は多くのウェブニュースサイトや記者の目に留まるため、新製品発表やイベント開催といったニュースがあれば全国区で紹介されるチャンスがあります。結果として、販路拡大や認知度向上につながり、地域にとどまらないビジネス展開のきっかけになるかもしれません。また、今回の岡山市の例を皮切りに、他の自治体でも同様の支援策が広がる可能性があります。自社が所在する自治体で似たプログラムがないか調べてみる価値があるでしょう。仮になくても、この動き自体が「中小企業でも戦略的な情報発信が必要」と示唆していると言えます。
経営者の視点:
経営者は、広報・PRも経営戦略の一部であると認識しましょう。今回のニュースを機に、「自社の強みや成果をきちんと外部に伝える」ことに改めて目を向けてください。もし岡山市のような支援を受けられるなら積極的に活用し、プレスリリースの作成に挑戦してみましょう。ポイントは、専門的な文章でなくても構わないので、自社の商品・サービスがどのようにユニークで社会の役に立つかをシンプルにまとめることです。写真やデータを盛り込み、読み手の興味を引く工夫も大切です。また、自治体の支援がなくても、無料で情報発信できる手段は他にもあります。例えば自社サイトのニュース欄やSNS、地域の商工会議所の会報などです。重要なのは「知らせなければ存在しないのと同じ」という意識で、自ら情報発信に動くことです。経営者自らがメディアや顧客に向けて自社の物語を語れるようになれば、ビジネスチャンスは今より広がっていくでしょう。
参考リンク:
岡山経済新聞:岡山市とPR TIMESが連携協定。地元事業者の発信力強化で協力
5. 若者の「推し活」がマーケティング鍵に、新サービスで“熱狂ポイント”を可視化
概要:
Z世代を中心に広がる「推し活」(アイドルやキャラクターなどお気に入りの対象を熱心に応援する活動)がマーケティングの注目テーマとなっています。SNSで推しへの愛を語ったり関連グッズに惜しみなくお金を使ったりするこの現象に着目し、株式会社Oshicocoは5月、「推し活」層の心理データを分析できるマーケティング調査サービス『推しペディア』の提供を開始しました。同社の発表によれば、Z世代の約3人に1人が何らかの推し活をしており、2025年1月時点で推し活人口は約1,400万人、市場規模は推定3兆円にも達するとのことです。『推しペディア』では自社が運営する推し活コミュニティ(総フォロワー数約11万人)のデータやアンケート結果を基に、「どんな要素があると商品やサービスが若者に支持され拡散されるか」を見極めることができます。例えば、「価格以上に推しへの貢献になるかを重視する」「共感できるストーリーがあるとSNSで共有したくなる」など、若年層の購買行動の裏にある“熱狂ポイント”を定量化し、企業の商品の企画開発やプロモーション戦略に役立てられるといいます。
中小企業への影響:
若者をターゲットにする商品・サービスを扱う中小企業にとって、推し活文化を理解することは非常に重要です。ただ安いだけ、便利なだけでは動かない層が、「心を動かす何か」に対して大きな購買力を発揮する傾向があるためです。例えば地方の小さなカフェでも、ある人気アニメとコラボして「聖地巡礼スポット」的な位置づけになると、遠方からファンが訪れてグッズやメニューを購入してくれるケースがあります。推し活市場の調査によれば、若年層は共感や一体感を感じられる商品に高い価値を見出すとのこと。これは裏を返せば、中小企業でもSNS発信などで物語性やコミュニティ性を持たせれば、大手に負けない熱狂的ファンを生むチャンスがあるということです。一方で、流行りに乗ろうとするあまり無理に若者文化に迎合すると、かえって「わかっていない」感じを与えて逆効果になることもあります。大切なのは、自社ブランドの個性を生かしつつ、その中にファンと一緒に作り上げる要素や参加型の仕掛けを取り入れることです。
経営者の視点:
経営者は、自社の商品やサービスに「お客様が熱中できるポイント」があるかを考えてみましょう。ただ機能や価格をアピールするだけでなく、「この商品にはこんなストーリーやこだわりがある」「みんなで○○を応援しよう」といったメッセージが打ち出せないか検討してください。例えば、地元の伝統を守りながら作った商品なら、その伝統自体を推してもらえるようなキャンペーンを企画するのも一手です。また、SNS上でハッシュタグキャンペーンを行い、ユーザーが自発的に宣伝したくなる場を提供することも効果的です。「推し」は何も有名アイドルに限りません。御社の商品を気に入ってくれているお客様を立派な“推し活”の担い手に育てることもできます。そのためには日頃からファンとのコミュニケーションを大切にし、意見を取り入れたり、特別感のある体験(限定グッズやイベント招待など)を提供したりすることが重要です。若年層の心の動きを敏感に捉え、価格以上の価値や体験を提供するマーケティングを意識することで、新たな顧客層の獲得や熱狂的なリピーターの育成につながるでしょう。
参考リンク:
PR TIMES:600万人の推し活データから“売れる理由”を発見!若年層マーケティング調査サービス『推しペディア』提供開始
まとめ
今回取り上げた5つのニュースから見えてくるキーワードは「マーケティングの新時代への適応」です。テクノロジーの進化や消費者行動の変化に合わせて、企業のマーケティング手法も大きく変わろうとしています。Googleや電通の動きに象徴されるように、AIの活用による効率化がマーケティング業界全体で加速しており、限られたリソースで最大の効果を上げることがこれまで以上に可能になっています。一方で、PR TIMESと自治体の連携や「推し活」の分析に見られるように、情報発信の重要性やファンとのつながりといった、人の心に訴える部分も依然としてマーケティングの核と言えるでしょう。中小企業の経営者にとって、これらは決して無縁の話ではありません。それぞれのニュースが示すポイントを押さえ、自社に取り入れられるものは何かを考えてみてください。
具体的には、まず最新のデジタルツールやAIサービスにアンテナを張り、使えるものは積極的に使ってみる姿勢が求められます。小さなトライアルから始めて、自社なりのデータ活用・AI活用の方法を探っていきましょう。また、行政やプラットフォームから提供される中小企業支援策(広報支援や補助金情報など)にも目を向け、遠慮せず活用することが大切です。そして何より、自社のファンを大切に育てるマーケティングを意識してください。お客様とのコミュニケーションを密にし、共感や愛着を醸成できれば、予算が潤沢でなくても熱心な支持者がビジネスを支えてくれます。今後もマーケティングの潮流は高速で変化していくでしょう。チャンスとリスクを見極めながら、新しい手法に対しては俊敏かつ柔軟に対応しつつ、自社の強みやお客様との絆という普遍的な価値も忘れずに、明日からの経営に活かしていただければと思います。