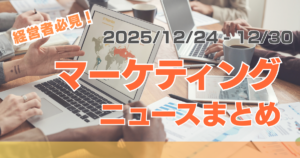マーケティングニュースまとめ(2025年5月14日〜5月20日)
マーケティングの分野でも重要な動きが相次ぎました。革新的なプロジェクトがマーケティング大賞を受賞し、新しい広告キャンペーンが若者の心をつかむ工夫を見せています。また、大手企業はAIを活用した戦略を加速させ、将来を見据えた新サービスも登場しました。さらに、SNSマーケティングに関する調査から効果的な運用のヒントも明らかになっています。中小企業経営者にとって見逃せない、注目の5つのニュースとそのポイントを解説します。
1. 「未来のレモンサワー」が日本マーケティング大賞グランプリ受賞
概要:
2025年の「第17回 日本マーケティング大賞」で、アサヒビールの缶チューハイ製品『未来のレモンサワー』が最高賞のグランプリを受賞しました。この賞は市場へのインパクトや独自性、ブランド定着性などで顕著な成果を上げたプロジェクトに贈られます。『未来のレモンサワー』は2024年6月の発売以来、世界初の本物レモンスライス入りチューハイというユニークな商品コンセプトで注目を集めました。缶を開けると中のレモンスライスが浮かび上がり、香りや食感まで楽しめる仕掛けで、調達・製造から飲用体験に至るまで一貫したマーケティング戦略が高く評価されています。
中小企業への影響:
大企業の事例ではありますが、商品のユニークな体験価値づくりは中小企業にも示唆を与えます。限られたリソースでも創意工夫次第で顧客の五感に訴えるような体験を提供できれば、話題性を生みブランド認知を高めることができます。例えば、商品開発からプロモーションまで一貫したテーマやストーリーを持たせることで、消費者に強い印象を残すことが可能です。今回の受賞は、単なる機能や価格競争ではなく、体験やストーリーを重視したマーケティングが評価される時代であることを物語っています。
経営者の視点:
中小企業の経営者は、自社の商品やサービスにどんな独自価値を持たせられるかを改めて考えてみましょう。他社には真似できないアイデアや地域資源の活用など、小規模だからこそ実現できる差別化ポイントがあるはずです。例えば、商品パッケージに工夫を凝らして開封時に驚きを与えたり、サービス提供時に顧客体験を演出したりといった工夫です。また、自社の取り組みを各種アワードに応募してみるのも良い刺激となります。他の受賞事例から学びつつ、自社ならではのマーケティング施策を磨いていくことが大切です。
参考リンク:
PR TIMES:『未来のレモンサワー』日本マーケティング大賞グランプリ受賞
2. Z世代の声を活かしたTOEIC広告キャンペーン開始
概要:
Z世代(若者)のリアルな声をそのまま広告コピーに反映したTOEICの新キャンペーンが、5月14日から首都圏の電車内吊り広告や大学の学食トレイ広告で展開されています。この施策は、Z世代向けのマーケティング会社「僕と私と株式会社」が企画・制作を担当し、「私がTOEIC®を受けた理由。」と題したコピーで就職活動中の学生の心情に寄り添う内容になっています。実際の学生から集めた声を基に、「他の学生が優秀に見えて焦る」「このままで大丈夫か不安」といった就活の悩みに共感しつつ、「英語力を可視化するTOEICを受験したことで自信が持てた」など前向きな一歩を後押しするメッセージを発信しています。広告デザインも黒板風のビジュアルに手書き風文字を用いるなど、学生の日常感覚に合わせた工夫が凝らされています。
中小企業への影響:
このキャンペーンは、大企業の資格試験PRですが、中小企業のマーケティングにも通じるポイントがあります。それはターゲットの生の声に耳を傾け、共感を得るメッセージを発信するという点です。自社の商品・サービスの宣伝でも、お客様(特に若年層)が抱える不安や課題に寄り添った表現をすることで心に響きやすくなります。例えば、「お客様の体験談」や「生の声」を紹介する形で広告やSNS投稿を行えば、押し付けがましさを避けつつ信頼感を醸成できます。また、この事例のようにターゲットが日常的に目にする場所(電車内や学校など)を選んで情報発信することも重要です。中小企業でも地域密着型ビジネスであれば、地域の掲示板やコミュニティ紙、SNSグループなど身近な媒体を活用することで効果的にメッセージを届けられるでしょう。
経営者の視点:
経営者として、自社のマーケティングメッセージがお客様目線になっているかをチェックしてみましょう。「売りたいこと」ばかりを前面に出すのではなく、顧客が感じているであろう悩みやニーズにフォーカスし、それを解決・サポートする姿勢を示すことが大切です。また、自社の商品やサービスに関して既存顧客からフィードバックを集め、それをマーケティングに活かす仕組みを作るのも有効です。例えばアンケートやレビューを集め、その声を引用した広告やSNS投稿を行うことで、よりリアルで共感度の高い訴求が可能になります。顧客の生の声をマーケティング資源として活用する視点を持ちましょう。
参考リンク:
マイナビニュース:Z世代のリアルな声を反映した「TOEIC Program」の広告を掲出
3. 電通が独自AI戦略「AI For Growth 2.0」を発表
概要:
広告業界大手の電通グループは5月19日、マーケティング業務のAIネイティブ化を目指す独自のAI戦略「AI For Growth 2.0」を発表しました。これは、マーケティングのあらゆる工程をAIエージェントが支援し、業務効率の向上と新たな価値創出の両立を図る取り組みです。具体的には、電通が保有する大規模な消費者データや社内の専門知見をAI技術と融合させ、1億人規模の仮想ペルソナを再現する「People Model」を開発しました。また、社内のクリエイターやプランナーの発想法を学習した「Creative Thinking Model」も機能拡充され、AIがビジュアルアイデアを生成することも可能になっています。さらに、社内でのAI活用人材の育成や、外部AIツールとの連携強化にも取り組んでおり、顧客企業への支援体制を強化しています。
中小企業への影響:
マーケティング領域におけるAI活用が加速する流れは、中小企業にも無関係ではありません。電通のような大企業が開発する高度なAIモデルは、すぐに同じものを中小企業が導入できるわけではないですが、今後マーケティング支援ツールや広告プラットフォームにAI機能が組み込まれていくことが予想されます。例えば、顧客データ分析やウェブ広告の自動最適化、クリエイティブ(広告文や画像)の自動生成など、従来は専門家や多大な手間が必要だった作業がAIによって簡易化・高度化されていくでしょう。中小企業でも、手頃な価格で利用できるAI搭載のマーケティングツールが登場すれば、顧客ターゲティングや宣伝効果の分析をより効率的に行えるようになります。
経営者の視点:
経営者としては、AI時代のマーケティングに前向きに備える姿勢が求められます。具体的には、現在利用しているマーケティングツールや顧客管理システムが将来的にAIと連携できるか注視したり、新しいAIサービスの情報をキャッチアップすることが大切です。自社で蓄積している顧客データ(購買履歴や問い合わせ内容など)があれば、その活用方法について社内外の専門家に相談するのも良いでしょう。また、小規模企業でも試しやすいAI活用として、文章作成AIや画像生成AIをSNS発信やブログ記事作成の補助に使ってみるといった一歩から始めても良いかもしれません。重要なのは人間の強みとAIの強みを組み合わせて活用することであり、AIに任せつつ人間ならではの創意で付加価値を付けるという意識です。時代の変化にアンテナを張り、使えるAIは積極的に使いながら、自社のマーケティング力を底上げしていきましょう。
参考リンク:
DIGIDAY:電通グループ、「AI For Growth 2.0」始動 1億人規模のペルソナ生成とビジュアルアイデア創出が可能に
4. ECサイトの「AI時代のSEO」サービス登場
概要:
ダイレクトマーケティング支援を手がける売れるネット広告社は5月20日、AI時代に備えた新サービス「売れるAI最適化 for ChatGPTショッピング」の提供を開始しました。これは、将来AIエージェントが商品選定・購入を代行する時代を見据え、ECサイトがAIに「選んでもらいやすく」なるよう最適化するコンサルティングサービスです。具体的には、商品データをAIが理解しやすい構造で提供したり、サイトをAIのクローラー(巡回プログラム)が読み取りやすいよう技術対応することなどを支援します。いわば検索エンジン向けのSEOならぬ、AI向けのSEO(AEO:AI Engine Optimization)を行うサービスで、将来的に音声アシスタントやチャットボットがユーザーの代わりに商品を探すケースに対応する狙いがあります。同社では2024年に専門部署を立ち上げ、AIを活用した「買うAI」「売るAI」など複数のサービス開発を進めており、今回の提供開始もその一環です。
中小企業への影響:
EC(ネット通販)を営む企業にとって、検索エンジン経由の集客対策(SEO)はこれまで重要でしたが、今後はAI経由で自社商品が推薦されるかどうかという視点も出てくる可能性があります。例えば、消費者がチャットボットに「おすすめの○○を教えて」と尋ね、そのAIがいくつか商品候補を提示するような未来です。このとき、自社の商品情報がAIに正しく認識され、候補に挙がるようにすることが、新たなマーケティング課題となります。今回のサービスは先進的な取り組みですが、中小企業でも自社サイトの構造化データ(商品名・価格・在庫情報などのマシンが読み取りやすいデータ形式)を整備したり、主要なショッピングプラットフォームのAPIに対応しておくなど、将来のAIショッピングに備えた情報発信の土台作りを意識しておくことが重要になるでしょう。
経営者の視点:
まずは現状でできる範囲で、商品やサービス情報をネット上にわかりやすく整理して提供しているか確認しましょう。検索エンジン向けの対策(適切なキーワード配置やメタデータの設定など)は引き続き有効ですが、それに加えて、商品データを構造化マークアップ(リッチリザルト対応のschema.orgタグなど)することも検討してみてください。これは将来AIが情報を収集する際にも役立つ可能性があります。また、Amazonや楽天市場など大手ECプラットフォームを利用している場合は、プラットフォーム側が提供する商品データの充実(画像・説明・カテゴリ設定など)にも注力しましょう。新技術の波に乗るには基礎を固めることが肝心です。余裕があれば今回のような最新サービスの相談会やセミナーに参加し、情報収集するのも良いでしょう。
参考リンク:
MarkeZine:売れるネット広告社、「売れるAI最適化 for ChatGPTショッピング」提供 AEO最適化を支援
5. SNS運用調査:成功の鍵は「フォロワーとの対話」
概要:
マーケティングリサーチ会社のネオマーケティングが発表した「自社SNSに関する調査」によると、SNSマーケティングの成果(KPI達成度)が高い企業担当者ほど、フォロワーへの“いいね”や返信などのアクションを積極的に行っていることが分かりました。実際、KPIを達成している担当者は、未達成の担当者に比べて約2〜3倍も頻繁にフォロワーとコミュニケーションしていたというデータがあります。また同調査では、企業のSNS活用トレンドとして動画系SNSへの注力が高まっている点も注目されています。特にTikTokでは、月間予算100万円以上を投じている企業が28.4%にも達し、300万円以上投入するケースも8.6%と、主要SNSの中で突出していました。YouTubeを含め、動画プラットフォームに高い予算をかける企業が増えており、SNSマーケティングの主戦場が文字や画像中心から動画へシフトしつつある傾向がうかがえます。
中小企業への影響:
予算規模の点では中小企業と大企業とで大きな差がありますが、SNS活用のヒントとして「フォロワーとの積極的な対話」が重要であることは企業規模に関係なく当てはまります。SNSは一方的な宣伝媒体ではなく、顧客とのエンゲージメント(関係性)を育む場です。中小企業でも、たとえフォロワーが少数であっても、一人ひとりのコメントに返信したり「いいね」することで身近で親しみやすい印象を与え、ロイヤルティ向上につながります。予算を大量に投下できなくても、手間をかけたコミュニケーションで補える部分は大いにあるでしょう。また、TikTokやYouTubeなど動画SNSが存在感を増している点も見逃せません。リソースが限られる中小企業にとって動画コンテンツの制作はハードルが高いかもしれませんが、短いスマートフォン動画やライブ配信など工夫次第で低コストでも取り組める方法があります。まずは自社のターゲット層が利用している主要SNSが何か把握し、適切なチャネルに注力することが大切です。
経営者の視点:
SNSマーケティングは「やりっぱなしにしない」ことがポイントです。経営者はSNS運用担当者(兼任の場合も含め)に、フォロワーとの対話を戦略に位置づけるよう促しましょう。例えば、週に◯回はコメント返しをする、問い合わせには◯時間以内に返信する、といったガイドラインを設けるのも有効です。SNS上での顧客の声は製品改善や新サービスのヒントにもなりますので、経営者自らエゴサーチ(自社名や商品名の検索)を定期的に行い、生の声を経営判断に取り入れる姿勢も重要です。一方で、動画SNSへの対応については無理のない範囲で構いません。もし自社の商品・サービスが動画で魅力を伝えやすいものであれば、簡単な紹介動画を作ってみる、あるいは既存顧客によるレビュー動画を共有してもらうなどから始めてみましょう。SNSマーケティングは継続と工夫が鍵です。小さな積み重ねでも、続けることで確実にファンとの絆が強まり、結果的に売上や集客力アップにつながっていきます。
参考リンク:
PR TIMES:TikTokに月100万円以上の予算をかける企業が28.4%に|自社SNSに関する調査
まとめ
今回のマーケティング関連ニュースでは、創造性とテクノロジー活用の両面で大きな潮流が見えてきます。マーケティング大賞を受賞した事例に見るように、顧客体験を重視した独自のアイデアが成果を生み出しています。一方で、AIやSNSといったテクノロジーの進化に対応した戦略やサービスも次々と登場し、マーケティング手法のアップデートが加速しています。中小企業の経営者は、これら両面の動きを押さえつつ、自社に取り入れられることは何かを考えてみましょう。
重要なのは基本とトレンドのバランスです。顧客目線に立った地道なコミュニケーションや体験づくりという「基本」を疎かにせず、同時にAI活用や新しいプラットフォーム対応といった「トレンド」にも柔軟にチャレンジすることが求められます。幸い、現在は情報もツールも以前より入手しやすい環境です。今回のニュースをヒントに、ぜひ自社のマーケティング戦略を一歩前進させてみてください。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果につながるはずです。今後も最新情報をウォッチしながら、時代の変化に適応したマーケティングに取り組んでいきましょう。