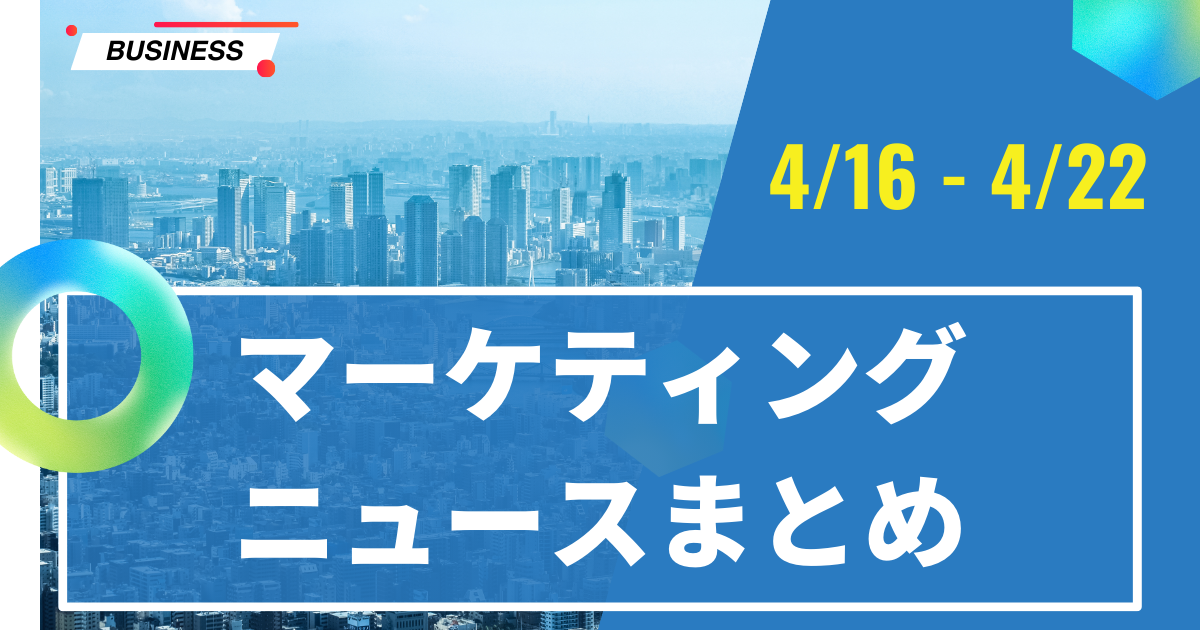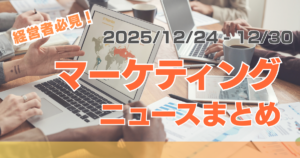マーケティングニュースまとめ(2025年4月16日〜4月22日)
今回も、中小企業の経営者が注目すべきマーケティング関連ニュースが目白押しです。Instagramの新機能によるSNS活用の変化、実店舗向け集客支援サービスの登場、消費者調査から見えるデジタル施策の重要性、生成AI活用への顧客期待、そしてゴールデンウィーク商戦の最新トレンドが報じられました。それでは、それぞれのニュースを詳しく解説していきます。
1. Instagram、新機能「ブレンド」で友達限定フィードを提供開始
概要:
写真SNS大手のInstagramは、友人同士でおすすめのリール動画を共有できる新機能「ブレンド(Blend)」を4月17日付で発表しました。
ダイレクトメッセージ(DM)上の1対1またはグループチャット内で招待制の専用フィードを作成でき、参加メンバー各自にレコメンドされたリール動画がひとつのフィードにまとめて表示されます。
視聴中にリアクションやコメントを送ると、そのままDMで会話ができる仕組みになっており、いつでも退出も可能です。
友達同士で日々更新される動画コンテンツを共有し合い、コミュニケーションを深められるのが特徴です。
中小企業への影響:
SNSの新機能追加はユーザーの利用スタイルに変化をもたらします。
特に「ブレンド」によって、ユーザーが友人間でコンテンツを共有しやすくなるため、口コミ的な拡散効果が期待できます。
中小企業の商品やサービスに関連する短い動画コンテンツ(リール)がユーザーの間でシェアされれば、新たな潜在顧客へのリーチにつながる可能性があります。
また、この機能はより親しい間柄での情報共有を促すため、企業公式アカウントの投稿が直接ブレンドに載るわけではありませんが、ファンを介した自然な紹介が起きやすくなると考えられます。
経営者の視点:
経営者としては、まずInstagramのこの動きを知り、自社のSNS戦略を点検する良い機会です。
具体的には「ファンに思わず友達にシェアしたくなるコンテンツとは何か?」を考えてみましょう。
商品紹介でも、役立つ豆知識やユーモアのある動画など、ユーザーが共有したくなるリール動画の制作にチャレンジしてみる価値があります。
加えて、SNS担当者や若手スタッフから実際の使い勝手や反応をヒアリングし、今後のInstagramマーケティングに活かすと良いでしょう。
参考リンク:
@Impress Watch:インスタ、友達とリールを共有する「ブレンド」機能
2. 実店舗向けオンライン集客パッケージ『まるごと店舗集客』登場
概要:
PR事業大手ベクトルの子会社であるトライハッチ社は4月17日、実店舗ビジネスのオンライン集客をまとめて支援する新サービス『まるごと店舗集客』をリリースしました 。
このパッケージでは、Googleマップでの店舗検索対策(MEO)、スマートフォンで見やすいスワイプ型ホームページ制作、ネット広告運用、さらにオンライン予約システムまで、店舗集客に必要な施策が一括提供されます。
特徴的なのは、AIを活用したクチコミ自動返信機能や競合分析機能を備えた高度なMEO対策や、縦横にスワイプできる直感的操作のホームページ作成など、新しい技術を取り入れている点です。
料金も成果報酬型(予約1件ごとの課金)を採用し、中小の店舗でも固定費リスクを抑えて導入しやすくなっています。
中小企業への影響:
小規模な店舗経営者にとって、ネット集客は「何から手を付ければいいか分からない」「専門知識がない」という悩みの種です。
このサービスは必要な集客施策をワンストップで提供するため、そうした悩みを解消するソリューションとなり得ます。
例えば、自社でゼロからホームページを作り、Googleビジネスプロフィールを更新し、SNSや広告を運用して…と個別に対応する負担が大きい場合でも、パッケージを利用すれば専門チームのノウハウに任せられる安心感があります。
また成果報酬型なので、「集客効果が出てから費用を払う」というモデルは限られた予算の中小企業にもありがたい仕組みです。
経営者の視点:
経営者としては、自社のデジタル集客状況を棚卸しし、足りない部分を外部サービスで補うことも検討しましょう。
特に地域のお店(飲食、美容室、クリニック等)では、Googleマップでの評価や予約のしやすさが集客に直結します。
「まるごと店舗集客」を試験的に導入し、予約数や問い合わせ数の増減を測定してみるのも一案です。
もちろん導入にあたっては費用対効果を見極め、サービス内容が自社の業種・規模に合っているか確認が必要です。
一度に全てを任せるのが不安なら、MEO対策だけ部分利用するといった柔軟な活用も検討すると良いでしょう。
重要なのは、オンラインでの顧客接点強化を後回しにせず、専門サービスも活用しながら早めに手を打つことです。
参考リンク:
PR TIMES:トライハッチ「まるごと店舗集客」の提供開始
3. 調査:デジタルメディア経由の購買意向、全世代で上昇
概要:
マーケティング調査会社VOSTOK NINEが発表した「主要オンラインマスメディア調査2025」によると、デジタルメディアを通じて商品を「買いたくなる」人の割合が全世代で増加したことがわかりました。
特に30代・40代の伸びが顕著で、この1年でデジタル経由の購買意向が約10%増加しています。
シニア層(50代以上)でも昨年より「ネットで欲しくなった」経験が増えており、デジタルの影響力が年代問わず拡大中です。
また、媒体別に見ると動画サイトやSNSで商品の購買意欲が刺激される人が増えており、「YouTube」や「Instagram」「X(旧Twitter)」「TikTok」といったプラットフォームでその傾向が強いことが報告されています。
例えばInstagramでは、20代ユーザーの7割以上が「SNSで見て欲しくなった経験がある」と回答するなど、若年層ほど顕著です。
中小企業への影響:
この調査結果は、中小企業にとってデジタルマーケティングの重要性が一段と増していることを裏付けるものです。
従来はリアル店舗や紙媒体を主な販促チャネルとしていた企業でも、今や年代を問わず顧客がネット上の情報で購買意欲を高めています。
つまり、デジタル上に情報発信をしていなければ機会損失に繋がるリスクが高まっています。
特に30~40代のボリュームゾーンがオンライン経由で動き始めているため、ホームページやSNSでの商品情報の充実、動画コンテンツの活用などは小規模企業でも避けて通れないでしょう。
一方で、シニア世代向けの商品を扱う企業にとっても、「年配のお客様はインターネットを見ないだろう」という前提は崩れつつあります。
経営者の視点:
経営トップとしてまず取り組みたいのは、自社のデジタル施策の点検です。
自社の商品・サービスはウェブ上で十分に情報発信できているか、ターゲット世代がよく使う媒体に露出しているか確認しましょう。
もしリソースが限られている場合でも、影響度の高い媒体に絞って対策するのがおすすめです。
例えば、20~30代向け商材ならInstagramやTikTokに注力する、40代以上が多い業種ならFacebookやYouTubeで丁寧に情報発信するといった具合です。
また、予算に応じてネット広告(リスティングやSNS広告)を試すのも有効です。「どの媒体から来たお客様が購買につながったか」を計測しながら、小さくテストして効果の高いチャネルに投資を集中させるデータドリブンな姿勢が、中小企業にも求められています。
参考リンク:
MarkeZine:主要オンラインメディア接触で購買意向が全世代で上昇(VOSTOK NINE調査)
4. 調査:生成AIの利用経験者は企業のAI活用に高い期待
概要:
ボストン コンサルティング グループ(BCG)が公表した最新の消費者心理調査で、生成AI(ChatGPTなど)を使ったことがある人の多くが、企業が提供するサービスへのAI活用に期待を寄せていることがわかりました。
調査対象者(全国18歳以上8260人)のうち約22%が生成AIを「使ったことがある」層でしたが、その層の83%が「AIによる迅速な問い合わせ対応」を企業に期待し、77%が「クーポンの個別最適化(お客ごとのパーソナライズされた割引)」への期待を持つと回答しています。
一方で、AI未経験者ではこれらの期待は5割前後にとどまり、生成AIを体験した人ほど企業サービスのAI活用に前向きな意見を持つ傾向が明らかになりました。
価格に関する意識では、同調査で一物多価(同じ商品でも提供条件により価格が異なること)を過半数が許容**するなど、消費者の価値観変化も報告されています。
中小企業への影響:
生成AIが話題になる中、消費者側もその利便性を実感し始めており、中小企業にも無関係ではなくなってきました。
特に問い合わせ対応やクーポン提供といった顧客接点でのAI活用は、小規模企業でも取り入れやすい領域です。
例えば、簡易的なチャットボットを導入すれば営業時間外でも基本的な問い合わせに答えられ、顧客満足度の向上につながります。
また、会員顧客に対して購入履歴に応じたおすすめ商品クーポンを自動発行するといった仕組みも、今やサービスとして利用可能です。
調査結果からは「AI活用に積極的な企業=先進的で顧客思い」というプラスのイメージを持つ消費者も増えていると推察され、中小企業がAIを活用することは差別化のチャンスと言えます。
経営者の視点:
自社でAIをどう使うかピンと来ない場合でも、まずは身近な業務のどこにAIツールを活かせるか考えてみましょう。
問い合わせ対応なら、よくある質問をまとめたチャットボットをホームページやLINE公式アカウントに設置するだけでも効果があります。人手不足で電話対応が追いつかないといった課題を補完できるでしょう。
マーケティング面では、顧客データを分析して「常連さん向けに次回使える割引を自動配信」など、小さなパーソナライズ施策から取り組むのがおすすめです。
ポイントは難しい開発を自前で行う必要はないことです。最近はAIサービスを月額利用できるソリューションも増えているため、外部のサービスや専門家の力を借りて構いません。
重要なのは、経営者自らが新しいテクノロジーに関心を持ち、小規模でも試してみる姿勢です。それが将来的に大企業との差を埋め、顧客から選ばれる理由につながるかもしれません。
参考リンク:
MarkeZine:生成AI利用者は「問い合わせ対応」や「クーポン最適化」に企業のAI活用を期待(BCG調査)
5. ゴールデンウィーク消費動向:Z世代の「推し活」需要に注目
概要:
広告プラットフォーム企業Criteo(クリテオ)が発表した2025年度ゴールデンウィーク(GW)消費動向レポートによると、今年のGWにおける“推し活”消費がZ世代を中心に盛り上がる見通しです。
「推し活」とは、自分の“推し”(応援しているアイドルやキャラクター等)のためにグッズ購入やイベント参加などを行う活動のことで、レポートによればZ世代の58%が「GW期間中に推し活をする可能性が高い」と回答しました。
これはX世代・Y世代(主に30~50代)よりも高い割合で、若い世代ほど推し活に積極的な傾向がうかがえます。
またGW前~期間中に購入が増えそうな品目として、食品・スナック類、清涼飲料やアルコール飲料、日用品などが挙げられており、大型連休に向けて日常消費財の売上が伸びることも示唆されています。
さらに「お祝い」「プレゼントを贈る」といった消費も若年層ほど高めで、GWはお祝い需要やギフト需要も含めた消費行動が活発化しそうです。
中小企業への影響:
このトレンドは、小売業やサービス業を営む中小企業にとって見逃せません。
まず、若者の推し活需要に関連する商品やサービスを提供している場合、大きな商機となります。
例えば、アイドルやキャラクターとコラボした商品、ライブイベント向けのグッズ、推しカラーのスイーツなど、「推し活」を後押しするような商品展開やキャンペーンはZ世代の心を掴むでしょう。
逆に直接関係ない業種でも、GW期間は人々の消費マインドが高まる時期です。飲食店であればテイクアウト用のパーティーメニューや限定セットの販売、日用品店であればまとめ買いセールの実施など、連休ニーズに合わせた販促を仕掛けるチャンスです。
また、ギフト需要が増えるという点から、お客様が家族や友人への手土産・プレゼントを選びやすいよう提案する(ラッピングサービスやメッセージカードの用意など)工夫も有効でしょう。
経営者の視点:
GW商戦に向けては早めの計画と準備が鍵です。
経営者は、自社の商品・サービスがこの期間にどう活用されるかを想像し、需要に合った売り方や宣伝方法をチューニングしましょう。
もしターゲットにZ世代が含まれるなら、SNS上で推し活に絡めたハッシュタグキャンペーンを行ったり、推し活ユーザー向けの特典を用意したりするのも効果的です。
例えば、「#推し活応援セール」と題して特定グッズを割引販売したり、来店時に推しカラーの服を着ているお客様にドリンクサービスをするといった遊び心ある企画も考えられます。
さらに、食料品や日用品を扱う企業は連休前の需要ピークに在庫を切らさないよう調整したり、追加発注を検討したりしましょう。
GW後半には母の日も控えているため、その先のイベントも見据えて準備しておくと万全です。
参考リンク:
MarkeZine:2025年GW購買トレンド調査—Z世代の58%が「推し活」を予定(Criteo)
まとめと来週に向けたアクション
以上、マーケティング関連ニュース5件を振り返りました。
SNSの新機能からは顧客との新たな接点や口コミ拡散のヒントを得られ、集客支援サービスからはデジタルマーケティングの効率化策を知ることができました。
さらに、消費者調査からは年代問わずオンライン施策が重要であることや、AI活用への期待といった今後のマーケティング戦略に役立つ示唆が得られています。季節トレンド(GW商戦)も把握し、目前のビジネスチャンスに備えることができそうです。
忙しい中小企業の経営者こそ、これらの情報を踏まえて即行動に移すことが肝心です。
例えば、気になったSNS施策やAIツールがあれば小規模でもテスト導入してみる、週末や連休の販促計画をすぐに見直す、といった具合に「まずやってみる」スピード感を大切にしてください。
また、自社だけで難しい場合は今回紹介したような外部サービスの力を借りるのも一つの戦略です。
市場や技術の変化は続きます。常にアンテナを張りながら、得た情報を自社の経営にどう活かすかを考え、実践していきましょう。そうすることで、変化の激しいビジネス環境においても着実に競争力を高めることができるはずです。
今後も最新のニュースをウォッチしつつ、チャンスを逃さず掴んでいきましょう。