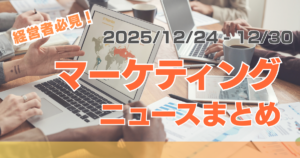マーケティングニュースまとめ(2025年10月29日〜11月4日)
マーケティング分野では国内で重要な発表が相次ぎました。中小企業経営者が押さえておくべき重要なニュースは、(1)プレイドの新事業「KARTE Offers」開始、(2)LINEヤフーの「DS.INSIGHT Basic」UI刷新、(3)三菱HCキャピタルらのオフィス内サイネージ実証、(4)ギフティの購買成果型プラットフォーム「PMN」、(5)楽天LinkSurge提供開始です。クッキー規制、AI検索、屋内OOH、購買データ活用という4つの潮流が、集客と収益化の設計を大きく変えます。本文では、具体的な影響と実践の要点を解説します。
1. プレイドがコマースメディア事業「KARTE Offers」を開始
概要
プレイドは11月4日、顧客体験プラットフォーム「KARTE」の企業向け新事業として、メディア保有企業やEC企業などが自社の会員・購買データを活用して広告収益化できるコマースメディア事業「KARTE Offers」を開始しました。KARTEのサイト行動データや購買履歴、レビュー、在庫情報などを基に、広告主の目的に合わせてオーディエンスを構築し、オンサイト/オフサイト配信を横断して最適化できるのが特徴です。広告掲載はKARTE連携のレコメンド枠やメール、アプリ内メッセージ、プッシュ通知なども活用可能で、媒体側はユーザー体験を損ねない設計でマネタイズ手段を増やせます。出稿側は3rdパーティCookieに依存しない形で高精度なターゲティングが可能となり、コンバージョンや来店など実績ベースで評価できます。
中小企業への影響
自社にオウンドメディア、EC、会員データベースがある企業は、新たな収益の柱として広告在庫の造成が現実味を帯びます。たとえば、会員数が数万人規模でも、カテゴリや購買周期を切り口にすれば、広告主に価値あるセグメントを提供できます。広告出稿側の中小企業にとっても、クッキー規制の影響を受けにくい“1stパーティ基盤”への出稿機会が増えることで、少額でも成約に近い層へリーチしやすくなります。一方で、過度な広告露出は離脱やブランド毀損を招くため、配信面の選定と頻度管理、クリエイティブの文脈適合が重要です。さらに、広告収入を狙う側は編集・販促・広告運用の権限分担やレビュー体制を整えないと、体験価値を損ねる恐れがあります。規模の小さな企業ほど、まずは限定カテゴリで試行し、体験品質の検証を優先すべきです。
経営者の視点
(1)会員規約やプライバシーポリシーを見直し、広告利用の明記とオプトアウト導線を整備。(2)会員属性×購買履歴×行動イベントで簡易セグメントを3〜4個作り、配信頻度上限と除外条件を設定。(3)広告評価はCPA・ROASだけでなく、アシストやリピート率、LTV寄与も追跡。(4)出稿側は既存の検索・SNSに加え、リテール/コマースメディア枠へ1〜2割を試験配分し、短期と中期の指標を併走させましょう。
参考リンク
MarkeZine:プレイド「KARTE Offers」開始
2. LINEヤフー「DS.INSIGHT Basic」UI刷新と個人設定機能
概要
LINEヤフーは10月31日、ビッグデータ分析サービス「ヤフー・データソリューション」の「DS.INSIGHT Basic」をアップデートし、11月13日提供開始と発表しました。検索・購買・位置情報などの多様なシグナルを横断的に分析しやすくするUI改善に加え、ユーザーごとの課題や興味に合わせて分析体験をカスタマイズできる「個人設定機能」を新たに実装。頻出する分析軸やレポート書式、比較期間などを保存でき、チーム内での再現性の高い分析運用を支援します。非エンジニアでも“生活者のいま”を素早く把握できる構成となりました。
中小企業への影響
自前のデータ基盤を持たない企業でも、検索ボリュームの変化、季節要因、エリアごとの関心度を掛け合わせ、需要の山谷や競合の仕掛けどきを把握しやすくなります。たとえば、地方の飲食店であれば「観光×ご当地メニュー」の検索増加を捕まえ、広告入札・クーポン発行・仕入れの調整を前倒しで意思決定できます。モール出店のECなら、関連ワードの伸びと在庫・レビューの相関を見ながら、商品ページの改修や広告の見直しに反映できます。BtoBでも、製品カテゴリー名や課題系ワードの上昇地域を特定し、展示会の出展場所や営業強化エリアの選定を合理化できます。
経営者の視点
(1)毎週の定例で“指名ワード/商品系ワード/新規ワード”の三層をウォッチ。(2)検索・SNS・実店舗POSなど手持ちデータと見比べ、因果ではなく相関として仮説を高速に回す。(3)ダッシュボードの主要KPIは3つに絞り、意思決定の行動様式(値引き、在庫、広告、販促)に直結させます。(4)属人化を避けるため、保存テンプレを使い、同じ分析を誰でも再現できる状態を作る。導入初月は“使い倒す担当”を一人決め、サンプル分析と勝ち筋のテンプレ化までやり切ることが肝要です。短期のCVだけでなく、検索指名増やレビュー改善など中期指標も併走させましょう。 また、可視化の整備は“やらない施策”を決める武器にもなります。トレンドが下がるエリアや季節を見極め、広告入札を抑え、人手を繁忙期へ振り向けることで、限られた予算と人員でも粗利を守る運用が可能になります。データで会議を短くし、現場で動く時間を増やすことが最大の効果です。
参考リンク
MarkeZine:DS.INSIGHT Basic アップデート発表
3. オフィス内デジタルサイネージ広告の実証実験(三菱HCキャピタル×AGC×jeki)
概要
三菱HCキャピタル、AGC、ジェイ・エム・エー(jeki)は10月31日、オフィス内のデジタルサイネージ広告に関する実証実験を実施すると発表しました。ビル共用部やオフィスフロアに設置されたディスプレイを活用し、入居企業の従業員や来訪者に向けて情報配信を行う取り組みで、表示コンテンツの最適化、視認性、広告効果の測定、プライバシー配慮の運用などを検証します。就業者デモグラや時間帯別の視聴機会データを広義のOOHとして整備できれば、屋内での新たな媒体価値が生まれます。屋外と違い、滞留時間の長い昼休みや始業前後に“音なしでも伝わる静止+短尺動画”が効きます。
中小企業への影響
駅や商業施設ほどの人流はなくても、入居テナントの関心に合った情報を届けやすいのがオフィス内サイネージの強みです。採用・福利厚生・BtoBサービスのリード獲得など、社内外向けの訴求が考えられます。ビル管理会社側の規約に沿えば、小規模の告知から試せる可能性があり、地域密着の事業者でも“働く人”に的を絞った継続的な接点が作れます。静音・字幕中心の設計や、視認距離・滞留時間に合わせた秒数設計が鍵です。特にBtoBは、検討者の職種が比較的絞れるため、役職別の悩みに刺さるコピーに落とし込みやすい点が利点になります。
経営者の視点
(1)商圏内のオフィスビルの属性(入居業種、平均年齢、来訪者数)を把握。(2)“3秒で伝わる1メッセージ”とQR導線を基本形とし、LP側で業種別の出し分けを用意。(3)広告枠が買えない場合は、ビル内の協賛やイベント連携で露出を確保。(4)効果測定は、QR遷移、指名検索、問い合わせ、来店・来場の4点セットで短期/中期を分けて見る。(5)制作費を抑えるには既存のSNS動画を転用し、3サイズ程度のテンプレ化を進める。さらに、ABテストは“背景色/コピーの語尾/QR位置”の3要素に限定し、1サイクル2週間で回すと学習効率が上がります。安全面では、顔認識・個人識別を伴う計測は避け、集計ベースの指標を使いましょう。 また、入居企業向けの福利厚生やランチ割引、ビル内店舗の回遊促進など“館内経済圏”の活性化にも寄与します。広告だけに頼らず、社内広報や災害時案内と共存する編成を組むことで、掲出の許諾が得やすく、長期的な媒体運用につながります。
参考リンク
MarkeZine:オフィス内デジタルサイネージ広告 実証実験
4. ギフティ、購買成果型プロモーション基盤「PMN」を提供
概要
ギフティは10月29日、購買成果型プロモーションプラットフォーム「PMN(Purchase Marketing Network)」を提供すると発表しました。生活者向けの複数アプリと連携し、店頭やECの購買実績に応じてインセンティブを配布できるのが特徴で、クーポンやデジタルギフトを起点に、認知から購買までを一気通貫で設計します。媒体(アプリ)側は送客・送客後の可視化で収益化し、広告主は“実購入”に紐づく支払いで費用対効果を管理できます。購買データの連携により、従来のクリックや来店だけでは見えなかった“レシート起点の評価”が可能になります。
中小企業への影響
従来のポイント付与や紙クーポンでは追跡が難しかった“どれだけ買われたか”を測りやすくなります。特に小売や飲食、日用品メーカーの販促で相性が良く、少額の試験出稿でも「アプリ露出→クーポン獲得→来店→購買」という流れが作れます。販促費を売上に連動させられるため、キャッシュフロー負荷を抑えつつ、新商品のトライアル獲得や来店頻度の底上げを狙えます。在庫リスクの高い生鮮や季節商品でも、曜日別・時間帯別に配布を最適化すれば、廃棄率の改善が見込めます。一方で、粗利が薄い商材は過剰な値引きに注意が必要です。
経営者の視点
(1)来店目的の強い曜日・時間帯を避け、客数の底上げが必要なスロットに集中配布。(2)1回限りの来店で終わらないよう、2回目来店までの“二段クーポン”を設計。(3)販促の評価指標は、クーポン獲得率、来店転換率、購買率、増分売上、粗利寄与まで一気通貫で見る。(4)SKU別の損益をシミュレーションし、値引き上限と在庫下限を設定。(5)店舗スタッフの声かけ台本やレジ運用を合わせて設計し、現場の負担を最小化します。成功パターンは、店頭サイネージやSNSと連携し、同一メッセージで反復接触させることです。紙チラシがまだ効く地域では、QRでクーポン取得を誘導し、オンラインと同じ計測軸に載せましょう。 なお、プライバシー配慮の観点では、個人を特定しない集計ベースでの購買分析に限定し、同意取得と利用目的の明示を徹底することが信頼確保の前提です。まずは対象商品を3SKU程度に絞り、2週間単位で配布量と粗利を検証すると無理なく運用できます。
参考リンク
5. 楽天LinkSurge:SEO・AIO・GEOの統合分析を低価格で
概要
楽天グループのリンクシェア・ジャパンは11月4日、ベンジーと共同開発したSEO・AIO・GEOの統合分析ツール「LinkSurge(リンクサージ)」の提供開始を発表しました。検索エンジン最適化(SEO)に加え、生成AI検索での露出最適化(AIO)、各種生成AIエンジンでの回答面露出(GEO)を横断的に分析し、対策提案まで一体で行えるのが特徴です。初期費用なしで月額1万円から利用でき、最新モデルのチャット機能も搭載。キーワードごとの可視領域や競合状況を俯瞰し、従来の検索結果だけでは捉えにくくなった“発見経路の多様化”に適応する設計です。料金はライト、スタンダード、プレミアムの3プランで段階的に拡張できます。
中小企業への影響
生成AIが検索入口として存在感を強めるなか、従来のSEO偏重では機会損失が生まれます。LinkSurgeのような統合型の可視化を使えば、「検索結果(SEO)」「AIの回答面(AIO/GEO)」「SNS・口コミでの想起」といった接点をまとめて把握しやすく、限られた予算でも優先順位が付けやすくなります。特に指名検索が弱いブランドは、質問文ベースの露出や比較系クエリでの登場機会を点検し、コンテンツ改善やFAQ整備に直結させることで、獲得の底上げが期待できます。ECでは、在庫やレビュー、配送条件といった“購入の最後の一押し”要素も同時に点検しましょう。
経営者の視点
(1)今の集客のうち“AI経由”の割合を推定し、3か月で1.2倍を目標に改善。(2)商品カテゴリごとに“質問文トップ5”を抽出し、回答品質・信頼根拠・画像の3点を磨く。(3)計測は、流入だけでなく問い合わせ率・CVR・粗利まで追い、費用は固定費と変動費を分けて評価します。(4)低価格プランから開始し、改善提案が利益に結び付くことを確認してからスケール。なお、生成AI回答面での露出は、誇張表現よりも“一次データに裏打ちされた明快な情報設計”が効きます。ツール任せにせず、ブランドの独自性を語る一次情報の発信を欠かさないことが差別化の王道です。 社内体制としては、検索・SNS・カスタマーサポートの担当が月一で同席し、“よくある質問”と否定要因を洗い出して更新する運用にすると、スピーディに成果が出ます。
参考リンク
まとめ
クッキー規制の深まりとAI検索の普及、屋内OOHや購買データの活用など、集客の“勝ち筋”は多層化しています。経営者としては、(1)1stパーティ基盤の強化、(2)検索とAI回答面の露出管理、(3)販促の実購入評価、(4)オフライン接点の再設計の4点を優先すると効果が出やすいです。まずは小さく試し、2〜4週間で学習→改善のループを回しましょう。次回も、意思決定に効く国内の動きを厳選してお届けします。