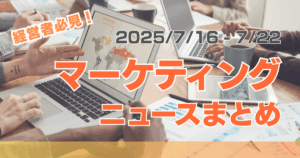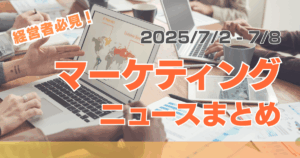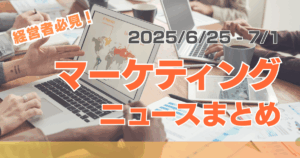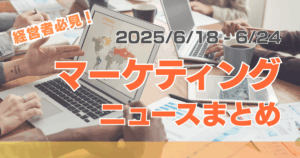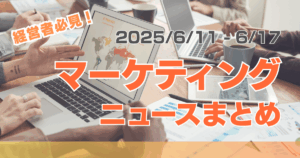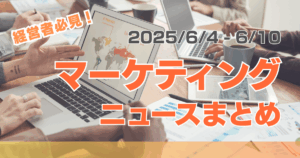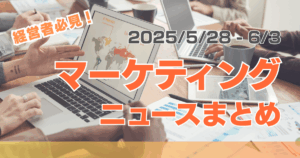マーケティングニュースまとめ(2025年7月23日〜7月29日)
マーケティング分野では国内外で注目の動きが相次ぎました。日本企業と海外大手の戦略提携や、AI技術を活用した広告手法の進化、さらにSNSプラットフォームの安全性向上への取り組みなどが発表されています。中小企業経営者が押さえておくべき重要な5つのニュースを、ポイントとともに解説します。
1. ADKが米Stagwellと提携、グローバルマーケティング支援を強化
概要
日本の広告大手ADKと米マーケティング企業Stagwellがグローバル規模の協業に基本合意しました。 ADKグループは海外事業を自社運営からパートナーシップ型に切り替え、双方のデータやツールを共有することで、日本企業の海外進出支援や海外企業の日本市場開拓を強化します。ADKは7月に社内に「グローバルプロジェクト開発局」を新設し、Stagwell傘下の専門エージェンシー群と連携して包括的なマーケティングサービスを提供する体制を整えました。この提携により、両社のクライアント企業は世界各地域で一貫したマーケティング支援を受けられるようになります。既に日本企業の海外キャンペーン企画やAPAC地域でのメディア運用など、具体的な協業プロジェクトも始動しています。
中小企業への影響
大手広告代理店同士の提携は、マーケティング業界のサービス水準を押し上げる可能性があります。 新しいツールやソリューションが国内市場にも導入されれば、中小企業でも先端のマーケティング手法を利用しやすくなるでしょう。例えば、海外の最新データ分析ツールが手頃な価格で提供されれば、これまで大企業しか扱えなかった高度な分析を自社でも活用できるかもしれません。また、マーケティング手法の高度化が進むことで、顧客の目も肥えていくでしょう。消費者は洗練されたデジタル体験を当たり前に期待するようになります。中小企業も自社サイトの使いやすさ向上やパーソナライズされた情報発信など、顧客体験(CX)の質を高める努力が欠かせなくなるでしょう。一方で、大手による競争激化で市場が成熟すると、自社の独自性や強みを明確に打ち出す戦略が一段と重要になります。
経営者の視点
経営者としては、グローバルな視野を持った戦略づくりの必要性を改めて感じるニュースです。海外市場への進出を検討する際、今回のような大手企業連携の動向を参考に、専門パートナーとの協業や新手法の導入を積極的に模索しましょう。また、自社マーケティングにも最新トレンドを取り入れる姿勢が求められます。例えば、海外で成果を上げているデジタル広告の手法やツールをリサーチし、スモールスタートでも導入してみる柔軟さが中小企業の成長につながるでしょう。
参考リンク
PR TIMES:ADKグループ、Stagwellとグローバル規模での協業推進に基本合意
2. サイバーエージェント、生成AI時代に対応する専門組織「GEO Lab」新設
概要
インターネット広告大手のサイバーエージェントが、生成AI時代の検索最適化を研究する新組織「GEO Lab.」を設立しました。 生成AI(Generative AI)が検索に利用される新潮流を見据え、ユーザーのAI活用実態やAIが回答を生成する仕組みを専門に分析します。ChatGPTなどで情報収集する動きが欧米で広まる中、企業のブランド情報がAIの回答に表示されないと機会損失につながる恐れがあります。サイバーエージェントはこうした「Generative Engine Optimization(GEO)」の重要性に着目し、AI時代の検索対策ソリューション開発につなげる考えです。例えば欧州では、「情報収集はChatGPT、比較検討はPerplexity、最終確認にGoogle検索」という新しいユーザー行動も生まれています。
中小企業への影響
検索エンジン経由の集客に頼る中小企業にとって、検索行動の変化は見逃せません。 今後ユーザーが従来のGoogle検索だけでなくAIチャットボットに答えを求めるようになると、SEOの概念も拡張が必要になります。自社の商品やサービス情報がAIの回答にきちんと反映されるよう、コンテンツの書き方やデータ構造を見直す必要が出てくるでしょう。例えば、よくある質問に対する詳細な回答コンテンツを用意したり、AIに認識されやすい公式情報の発信を強化したりすると、AI時代の“検索結果”にも自社情報が表示されやすくなる可能性があります。例えば、自社サイトに製品ごとの詳細なFAQページを設けたり、専門知識を紹介するブログ記事を蓄積したりしておくと、それらがAIの学習材料となり、ユーザーの質問に対して自社の情報が回答に引用される可能性が高まるでしょう。
経営者の視点
経営者としては、SEOの次に来るGEO(生成AI最適化)への意識を早めに持つことが重要です。具体的な対策がまだ模索段階でも、社内で最新の検索トレンドをウォッチし、ウェブサイトの構造化データ対応やQ&Aページの拡充など、できる準備から始めましょう。サイバーエージェントのような業界リーダーの研究発表やセミナーにはアンテナを張り、得られた知見を自社のデジタル戦略に反映させることがポイントです。時代の変化を先取りして柔軟に戦略転換できる経営判断が、中小企業の今後の集客力につながります。なお、同社は調査結果の公開や無料セミナーの開催も予定しており、業界全体でノウハウを共有する動きが進みそうです。
参考リンク
Web担当者Forum:サイバーエージェントが生成AIの検索利用と回答傾向を研究・分析する「GEO Lab.」を新設
3. 博報堂DY、AIで動画広告を分析する「動画分析AIエージェント」開発
概要
広告大手の博報堂DYホールディングスは、AIエージェントによる動画広告分析機能を開発し、社内利用を開始しました。 ディスプレイ広告制作支援プラットフォーム「CREATIVE BLOOM DISPLAY Ads」に実装されたこの機能では、動画広告をシーンごとに自動分割し、各シーンの重要度やテロップ(コピー)の注目度を分析します。さらに、媒体別の予想インプレッション数やクリック率など広告効果指標をAIが予測し、事前にクリエイティブの改善点を提案できるようにしています。これにより、人手では困難だった大量の動画素材の評価を効率化し、広告のブラッシュアップが可能になります。なお今後は音声の解析機能を追加し、AIが広告の具体的な改善案を提示できる機能も導入予定です。
中小企業への影響
AI活用による広告作成・分析の効率化は、中小企業にも恩恵をもたらす技術です。 従来、高度な広告効果分析は専門人材や費用が必要でしたが、今後はAIが自動でクリエイティブの良し悪しを評価してくれるため、少人数のチームでも質の高い広告を作りやすくなるでしょう。例えば、自社で制作した動画広告をAIツールにかけるだけで「どのシーンで視聴者の関心が離れやすいか」といったデータが得られれば、予算内で動画を改良してより高い成果を狙えるようになります。近年は、動画広告制作のハードル自体もAIによって下がりつつあります。最近ではスマホで撮影した映像にAIが自動でテロップや音楽を入れてくれるサービスも登場しており、少ない手間と予算で動画マーケティングを始められる環境が整いつつあります。一方で、大企業がこうしたツールで広告効果を最大化すれば競合も強化されるため、中小企業はクリエイティブな発想や地域密着の視点など独自路線で魅力を出す工夫も必要です。
経営者の視点
もちろん、キャッチコピーの微妙なニュアンス調整やブランドイメージの最終判断など、人間にしかできない部分も残ります。AIを賢く使いこなし、人の創造力を引き立てることで、中小企業ならではの温かみや独自性を保ちつつ、マーケティング成果を高めることができるでしょう。経営者としては、AIによるクリエイティブ分析は「使わない手はない」ツールと言えます。現在利用できるオンライン動画編集サービスやSNS広告管理ツールにも、簡易的なAI分析機能が続々と搭載されています。難しい専門知識がなくとも、まずは身近な無料ツールなどでAIの力をマーケティングに取り入れてみましょう。例えば、Facebook広告マネージャの自動最適化機能を試したり、YouTubeの分析データを活用して動画内容を改善したりすることが考えられます。AIに任せられる部分は任せ、人間は戦略と創造に注力するという発想が、中小企業の限られたリソースを最大限に活用するポイントです。
参考リンク
MarkeZine:博報堂DYホールディングスら、AIエージェントによる動画広告の分析機能を開発
4. Instagram、未成年ユーザー向けに新たな安全機能を導入
概要
Meta社はInstagramにおいて、10代利用者の安全確保を目的とした新機能を発表しました。 具体的には、未成年(ティーン)アカウントのDM画面上部に相手アカウントの登録日時やブロックボタンを表示し、やりとり相手の情報をより見えやすくしています。怪しい相手からの詐欺被害を防ぐ狙いで、メッセージ画面からワンタップでブロック・報告できる仕組みです。さらに、13歳未満の子どものアカウント(保護者が管理する場合)にはDM受信設定を最も厳しく自動適用し、攻撃的なコメントを非表示にするフィルタ機能も有効化されます。加えて、未成年にブロックされた大人のアカウントは検索やおすすめに表示されにくくし、そのようなユーザーのコメントも非表示にする対策が取られました。こうした安全機能の導入とともに、日本独自の啓発キャンペーンも展開されます。
中小企業への影響
SNSプラットフォームの安全性向上は、企業にとっても健全なマーケティング環境づくりにつながります。 特に若年層向けの商品・サービスを扱う中小企業にとって、10代ユーザーが安心して利用できるInstagramは貴重なコミュニケーションの場です。今回の機能強化により、DMを使ったプロモーションやアンケート収集を行う際、未成年ユーザー側でブロックが容易になるため、企業は一層慎重なアプローチが求められるでしょう。例えば、DMで広告メッセージを大量送信すると敬遠される可能性が高まり、代わりにタイムライン投稿やストーリーズで役立つ情報を提供して自発的な関心を引くマーケティングが重要になります。また、安全性への配慮が進むことで、SNS全体のユーザー信頼が高まれば、企業アカウントの発信もこれまで以上に前向きに受け取ってもらえるメリットも期待できます。
経営者の視点
中小企業の経営者は、プラットフォームのルール変化に敏感になり、自社のSNS戦略を微調整することが大切です。Instagramの新機能に合わせ、未成年ユーザーとのコミュニケーションでは節度を守り、公式アカウントからの問い合わせ対応でも押し付けがましくない丁寧さを心がけましょう。加えて、「安全・安心」は企業イメージにも直結するキーワードです。SNS上での発信内容や広告クリエイティブも、過度に刺激的な表現を避け、信頼感や共感を得られるトーンに統一すると良いでしょう。今回の取り組みを機に、社内でもSNSポリシーを見直し、健全なオンライン対応についてスタッフと共有しておくと、トラブル防止とブランド価値向上につながります。
参考リンク
ケータイ Watch:「Instagram」10代保護で新機能 ブロックや報告が容易に
5. 調査データ:SNS利用者が「最もイラッとする」のはX(旧Twitter)
概要
マーケティングリサーチ会社のRJCリサーチが、SNS利用中の「イラッとする経験」に関する調査結果を発表しました。 それによると、普段使っていて腹が立つSNSプラットフォームの第1位はX(旧Twitter)で、回答者全体の32.6%が選択しました。2位はInstagramで約13%となっており、Xが他を大きく引き離しています。特に20~30代の若年層でXにいら立ちを感じる人が多い傾向がありました。イラッとする投稿内容として最も多く挙がったのは、「デマやフェイクニュースなど不確かな情報の拡散」(約5割)で、次いで「迷惑行為、突然のDM、誹謗中傷」が挙げられています。また、コメントに関しては「攻撃的なコメント」が52.8%でもっとも多く、「上から目線のコメント」が約39.5%で続きました。全体として、事実に反する情報や高圧的な言動がSNS利用者の反感を買っているようです。
中小企業への影響
SNSは顧客との重要な接点ですが、ユーザーの不満が高まる場での企業発信には注意が必要です。 調査結果から、特にXではフェイクニュース的な情報や高圧的な発言への嫌悪感が強いことが分かります。中小企業がSNSマーケティングを行う際、自社アカウントで誤解を招く表現をしてしまったり、一方的な宣伝ばかり発信したりすると、ユーザーに敬遠されるリスクが高まります。逆に言えば、信頼性の高い情報発信や双方向のコミュニケーションを心がければ、他の発信者との差別化につながるチャンスです。例えば、自社の専門分野で有益な豆知識や業界ニュースを正確に伝える投稿は、SNS利用者にとって価値あるコンテンツとなり、ブランド好感度の向上につながるでしょう。また、プラットフォームごとのユーザー層の違い(若い女性はInstagramで苛立ちを感じる割合が高い等)も考慮し、メディアミックス戦略を調整することが大切です。
経営者の視点
本調査は、企業の発信姿勢を見直す良い契機と捉えられます。経営者はSNS運用担当者とともに、自社発信が独りよがりになっていないかチェックしましょう。お客様の声に耳を傾け、クレームに対しても誠実に対応することで、攻撃的なコメントがあっても他のファンが庇ってくれるようなコミュニティの信頼を築けます。また、Xなどネガティブな感情が起きやすい場では無理に炎上マーケティングを狙わず、顧客に寄り添った丁寧な情報提供に徹する方が長期的に得策です。複数のSNSを運用している場合、それぞれの特性に応じて投稿内容や頻度を最適化し、ファンとの良好な関係維持に努めましょう。SNSは企業のブランドイメージを左右する重要なツールであることを改めて肝に銘じ、戦略をアップデートしていくことが求められます。
参考リンク
nippon.com:〖イラっとするSNS〗1位はX デマやフェイクニュース拡散に不満
まとめ
以上、マーケティング領域で注目された5つのニュースを振り返りました。グローバル企業の提携から最新AIの活用、そしてSNS環境の変化まで、マーケティングを取り巻く潮流は日々進化しています。 中小企業経営者にとって重要なのは、これらの動きを他人事と捉えず、自社の戦略にどう応用できるかを考える姿勢です。例えば、グローバル展開のヒントはないか、AIツールで効率化できる業務はないか、SNS運用で信頼を損ねるリスクはないか—こうした視点で常に情報収集し、社内で議論することが求められます。
マーケティングの世界はスピードが命と言われますが、闇雲に飛びつく必要はありません。今回のニュースを踏まえ、自社にとって本当に有効な施策は何かを見極めましょう。例えば、リソースが限られるならSNSチャネルを厳選し、質の高い発信に注力する、あるいは安価に導入できるAIサービスでまず試行してみるといった形で、小さく始めて素早く学習することが大切です。幸い政府や大企業から様々な支援策や情報発信も行われています。これらを上手に活用し、社外の知見も取り入れながら、変化に対応できる柔軟なマーケティング戦略を組み立てていきましょう。
今後もマーケティング業界では、新技術や市場動向に関するニュースが次々と登場するでしょう。中小企業としては、最新情報へのアンテナを高く張りつつ、自社の強みと組み合わせてチャンスに変える発想が求められます。引き続き学びと工夫を重ねることで、時代の波を味方につけて自社の成長につなげていきたいものです。